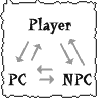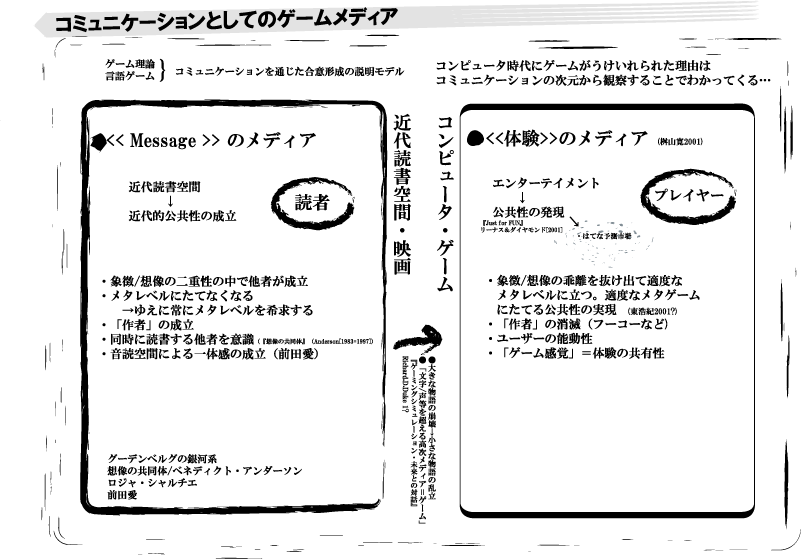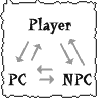
ゲームの物語や、メディア特性をめぐる多くの議論は、プレイヤー、プレイヤー、ノンプレイヤーキャラクターの三項関係をどのように捉えるか、によって整理できる。
意味 †
Real Money Tradeの略。
主に、MMORPGにおいて生じる行為であり、オンラインゲーム内の財物を、日常世界(Real)において流通している財物(Money)と交換(Trade)することから、リアルマネートレード、略してRMTと呼ばれる。
誤解など †
現在は、法的にグレーなところが多く、RMTに関する非常に基本的な議論も十分に共有されているとは言い難いところがある。
一つだけ、よくある誤解について書いておくと、RMTは違法である、というのは誤解である。
RMTそのものは違法ではない。あくまでグレーである。
RMTを禁止しているのは、主にMMORPGのサービス提供を行っている会社の側の規約であり、法的に罰せられるわけではない。ただし、規約を破っているという点でサービス会社がアカウントを剥奪する理由とはなりえる。また、「規約違反である」ということが、ある種の契約違反に類するのではないかというような法解釈的な話もあるらしい。詳しくはわからないが
現在、RMT関連の事件で捕まっているのは、基本的にはRMT行為自体が罰せられているわけではなく、RMTで利益を得ることを目的とした詐欺、不正アクセス、不法就労などである。RMT自体はRMT取引業者が倫理委員会などを作るなど、RMT業界内における違法な手段を用いた組織/個人とそうでない組織との差別化が図られている。
また、ゲームメーカー自体が行っている「アイテム課金」制度は、RMTを行う欲望がプレイヤー側に存在する、ということを前提として登場した、RMTの正規化をはかるビジネスであるといえる。
欧米での"RPG"概念の誕生 †
通常、1974年にD&Dの誕生をもってRPGの誕生とする議論が多いが、「RPG」という言葉の誕生は、実際には1974年より後である。1974年のD&Dの中では「RPG」という言葉は使われていない。「RPG」という言葉が使われはじめるには1980年前後まで待たなければならない。
日本における「RPG」概念の受容史 †
「RPGとはなにか」という説明をめぐって †
さて、では「RPG」とはなんだろうか。ゲームをまったく知らない人にとっては、聞いたことはあるが、中身はまったくわけのわからない言葉だろうし、ある程度ゲームに詳しいマニアックなゲームプレイヤーならば、ほとんどの人は、「RPGとは、1974年に、D&DというTRPGが開発されたことにはじまり…」というRPGの歴史を一通り語ることができるだろう。
マニアックなゲームプレイヤーたちが「RPG」を語る際の説明の典型的なパターンは以下のような説明だろう。
「RPGとは?
ロールプレイングゲームとは、役を演じる、役になりきるゲームだと、何度も紹介されている。でも、コンピュータRPG以前から遊ばれている、ボード版(本当はゲーム盤のあるRPGは少ないのだけど)RPGも含めると、どんな歴史を持っているか、知っている人は少ないかもねっ。
最初にRPGがプレイされたのは、たぶんアメリカの「ダンジョン&ドラゴンズ」あたりだろうと思う。これは、ファンタジー小説の名作「指輪物語」の世界にあこがれた人たちが、自分が勇者になったつもりで、段ジョンを冒険していく、冒険ゴッコゲームとして作りあげたものだ。
この「ダンジョン&ドラゴンズ」(略して「D&D」)が、ほかのゴッコ遊びと大きく違っていたのは、ゲームの中に「経験地」という考え方をいれ、「成長―レベルアップ」を楽しむゲームにしたことだ。最初は貧しい力の弱いゲームの主人公を、少しずつ成長させて、その過程を楽しむゲームとして、RPGは完成され、じょじょに広まっていったのだ。
さて、このRPGにとって、コンピュータは強い味方になった。複雑な計算(戦闘のときのダメージの計算など)、偶然性の出し方(怪物との遭遇など)、枝道の処理(右へ行くか左へ行くかで変わる物語をつなげていく処理)などで、コンピュータは、本によるRPGや、後のRPGの遊び方のところで書く、ゲームマスターによるRPGより、手間を省くことができるからだっ。
「D&D」をコンピュータRPGに作りあげた「ウィザードリー」や、「ウルティマ」などの大ヒットによって、RPGは、全アメリカで遊ばれる、有名なゲームになっていったんだぜっ。」
これは、週間少年ジャンプのゲームコーナーから独立したかたちで出版された、『ファミコン神拳奥義 大全書 特別編』(1987、集英社)、P22〜P23のからの引用である。
ある程度詳しい人間の間では、もはやテンプレート化された感すらあるこのような説明によって、確かに「RPG」の起源と、それがコンピューターRPGの『ウィザードリィ』『ウルティマ』、そしてそこから日本の『ドラゴンクエスト』などといった作品が製作されていった系譜を知ることは、可能だ。最低限度の「RPGの歴史」としてはこの話で十分だろう。
だが、日本における「RPG」の歴史には知っておくと興味深い、もう少し多くの紆余曲折があった。
ここでは、テンプレート化された「RPGの歴史」に欠如している点を確認しつつ、日本における「RPG」受容がどのような変遷をたどったのか、ということを確認していく。
まず、(1)1974年に、D&Dがアメリカにおいてヒットし、(2)1979年〜1980年にかけて、コンピューターRPGの初期の傑作といわれる『ウィザードリィ』『アカラベス』(後のウルティマ)――加えるならば『Rouge』――などが製作された、という歴史まではいいだろう。
そして、日本において「RPG」というジャンルを考えるとき、それは当然、「輸入」という形で「紹介」がなされ、80年代初期に日本の中に突如として現れたものだった、ということが、日本における「RPG」の受容において今日まで重要な意味を持っている。
まず、第一に、単純な普及率のレベルの問題として、アメリカ、イギリスなどにおいては『D&D』をはじめとする、コンピューターRPGではない「TRPG」と呼ばれるアナログのRPGが普及していたのに対して、日本では、TRPGはほとんど大規模な普及を見ていない。そして、ファミコンブームの85年〜86年にかけてファミリーコンピュータ用ゲームソフトの「RPG」が広く一般的に普及するまで、「RPG」という名称はあまりメジャーに知られるところではなかった。
日本におけるTRPGの紹介は、目立ったところでは、主に80年代初期あたりから海外SFの翻訳者であった安田均などを中心にパソコンゲーム誌「ログイン」などで行われていた。それによって、一部のappleIIユーザーなどが82年、83年頃には、海外版の『ウルティマ』『ウィザードリィ』を輸入してプレイしていたり、『D&D』日本語版が80年代初期に売り出され、TRPG等を扱うアナログゲームの専門誌が、1981年には「タクティクス」、1986年には「ウォーロック」などもあいついで創刊されることになるが、それでも、日本のユーザー数は後にヒットする『ドラゴンクエスト』や『ファイナルファンタジー』の売り上げからすれば、少数に過ぎなかった。80年代中盤以降、日本では少数の「マニア」の趣味として、TRPGは定着してしまったというイメージがもたれるにいたる。 *1
第二に、「輸入」という形でRPGがやってきたことによって、CRPG/TRPGを問わず、アメリカのRPGは、日本におけるRPGの「元祖」という位置づけから、なんらかの権威付けがなされていることが多くなっている。これは、「RPGの歴史」を語るテンプレートにおいても象徴的にあらわれており、先に引用した文章にも「その世界そのものを楽しむゴッコ遊びの精神は、アメリカのようには受け継がれなかったような気がするぜっ」などといった形で確認することができる。
アドベンチャーのサブジャンルとしてのRPG 1983年、1984年 †
そのような形で80年代初頭に日本に輸入された「RPG」である。日本において「シミュレーション」「アクション」「アドベンチャー」などといったゲームのジャンル分類が頻繁に使用されはじめるようになった83年には「RPG」というジャンルもマイコンゲーム雑誌で一つのジャンルとしての地位を得るわけだが、具体的にはどのような扱いを受けていたのだろうか。
1983年10月1日に初版を発行している旺文社の『パソコンゲームランキングブック』におけるジャンル分類のページをのぞいてみると、そこでは当時のパソコンゲームが「シミュレーション」「アクション」「アドベンチャー」「ノンセクション」の四種類に分類され、「RPG」はその四分類のレベルでは発見できない。だが、細かく見てみると、「アドベンチャー」と分類されるジャンルのサブジャンルがさらに細かく分けられており、「ミステリータイプ」「SFタイプ」「リアルタイムアドベンチャー」「ファンタジータイプ」そして、「ロールプレイングタイプ」と、ここにRPGを発見することができる。さらに、同83年5月25日初版の『マイコン大百科 ゲーム編』においても事情は同様で、ロールプレイングゲームを以下のように解説する。
「ロールプレイングゲームは、きみ自身が主役となり、さまざまな道の世界を訪ねて、不思議な体験をしたり、冒険とロマンの物語の中で活躍したりするゲームだ。
このゲームは怪獣や魔法使い、騎士、お姫様、ドラゴン(魔法の竜)などが登場する。怪奇冒険の世界をテーマにしているものが多いので「SFアドベンチャーゲーム」などと呼ばれることもある。また、広い意味ではミステリーや殺人事件を解決する推理ゲームも、このゲーム分野だ。」
このような形で、マイコンゲーム、パソコンゲームといわれる市場において、国産初のコンピューターRPGといわれる『ブラック・オニキス』がパソコンゲーム市場でヒットする以前は、「アドベンチャー」のサブジャンル、あるいは類似ジャンルとして扱われていた。
そして、『ブラック・オニキス』をめぐる感想もまた、アドベンチャーゲームとの差異において語られる、という自体が発生していた。当時の『ブラック・オニキス』を振り返る文章の中では
「方向ボタンを押せば自由に自分のキャラを動かせる・・・、視点固定のAVGが全盛だった当時としてはこの自由度が無限の可能性を約束されたように思えました。町を歩いているだけでも「この先には一体何があるのだろう?」と秘密基地を探すようなワクワク感がこの作品にこめられていたと思います。」 *2
と語られており、「自由なアドベンチャーゲーム」という視点によってRPGが語られているのはちょっとした驚きであるといってよい。
『ドラゴンクエスト』以前に「RPG」は流行していた 1985年 †
さて、ここで家庭用のゲーム市場に目をうつすことにしよう。家庭用のゲーム市場での「RPG」といえば、一般的には、1986年にエニックスから発売された『ドラゴンクエスト』シリーズが、ファミリーコンピュータ最初の「RPG」としてよく知られている。そして、ほとんどの日本のコンピューターゲームの歴史をつづったものの中では、86年に『ドラゴンクエスト』が発売されて、同作品が週間少年ジャンプとタッグを組んだことで、100万部以上の売り上げを記録し、日本に「RPG」が根付いた、としているものがほとんどであるが、実は、86年初頭のいくつかのファミリーコンピューター向けゲーム雑誌を見てみると、なんとすでに、「今、一番流行のRPGだ!」「今はなんといってもRPG」といった記事が踊っている。
これは、一体何のことか。
実は当時、『ゼルダの伝説』や『ハイドライド』といった、日本独自の発達を遂げた「アクション・RPG」と呼ばれる分野がファミリーコンピューター市場で大きな存在感を誇っていた。これが、「RPG」として、「流行」していたのである。
そして、これは、単に流行していた、というのみならず、その後のRPGについてしばしばいわれるような言説をも少なからず生産している。例えば、86年6月の「ファミコン通信」創刊号にて、ゲヱセン上野は『ゼルダの伝説』のレビューで以下のように書いているのは興味深い
「(RPGというのは)主人公が弱すぎもせず、強すぎもしないなんといっても、"努力すれば、必ず報われる"ゲームなんだよね。よくあるでしょ、いくら努力しても全然先に進めない、いたずらに難易度をあげてあるゲームって。難しい=面白いじゃなく、いかに主人公に感情移入できるか=面白さ、という気がします」
といった形で、「感情移入」が「RPGの面白さ」とする言説がこの頃にすでに誕生していたことを観察できるのは興味深い。
『ドラゴンクエスト』の誕生 †
そして、そのような「アクションRPG」の日本の「RPG」イメージのみならず、日本のゲーム市場そのものの動向に決定的に大きな影響を与える、『ドラゴンクエスト』が1986年の5月に発売される。しかし、これはすでに、多くのところで言われていることであるが、決して当初から売れ行きがよかったわけではなく、発売当初の売り上げは20万部ほど。発売当初、『ドラゴンクエスト』の開発者である堀井雄二は、自身が連載を持つ雑誌「月刊OUT」1986年7月号に以下のような告白をしている
「やた! ついに『ドラゴンクエスト』が完成したっ。いうまでもなく、これはファミコン用のロールプレイングゲームで、OUT7月号、つまリこの号と、ほとんど同時発売!
正直いって、ウケるかどうか心配だぜっ。
というのも、『ドラゴンクエスト』は、『ゼルダの伝説』、『ハイドライド』のようなアクションロールプレイングじゃないからだ。つまリ反射神経は、いっさいいらない、そのかわり、自分のキャラクターの各種ステータス(生命力、攻撃力、守備力、ゴールドなど)が常に数値で表現され、戦闘の勝敗はすべてその数値による計算式で結果が出される(もちろん、計算はファミコン側がやってくれるわけだけど)。
つまり、ものすごくべーシックな正統派のロールプレイングゲーム。それだけに、ある種マニアックな感性が要求されるわけ。
こんなのをファミコンでつくってよかったのだろうか。う〜ん、不安だ。
もしファミコンで初めてロールプレイングをやったという人がいたら、感想とかを聞かせてください。次回作のモニターになってもらうかもしれません。というわけで本題へ!」
今こそ、最新作が400万部以上の売り上げを誇る『ドラゴンクエスト』シリーズもはじまりはこのようなものだったわけである。
これがその後、週間少年ジャンプによって大きく宣伝を打たれることで、結果的には『ドラゴンクエスト』は120万部を超える売り上げをあげ、一躍話題作となる。そして、「RPG」というそれまでに家庭用ゲーム市場に確固として存在していなかった特殊なジャンルと出会ったプレイヤー、その世界に衝撃を受け、驚きをもらしている。
まず自分の名前を登録すると、画面内のキャラがその名で呼びかけてくれる、という遊びのノリがたまらない。
(省略)
なんと言っても楽しいのは、画面に登場するキャラクターすべてが話し好きなことだ。ある者はヒントを、ある者はただのおしゃべりを答えてくれる。城の外にはデートをする若者までいる。必要なアイテムには「王女の愛」なんてものまである。王女がプレイヤーにたずねる。「○○さまはわたしのことをあいしてくださいますか」、ここで「いいえ」といれたり、悪の竜王から「手をくもう」と言われて「はい」と答えたりすると、物語は意外な展開をする。
もちろん戦いはあるが、相手によっては逃げてもいい。「にげる」なんてコマンドは絶対にアクションやシューティングにはない。攻撃力もランダムに設定されていて、「渾身の一撃」で相手を倒したりすると、道で一万円札を拾ったような感動がある。
もちろんゲームは途中でセーブできるし、持っているアイテムは消えない。途中で死んでしまうと、王のお叱りの言葉が待っているし、手持ちのゴールドも半分になってしまう。お金がなければ宿屋にも泊まれないし、武器も買えない。「ゼルダ」もそうだが、金がなければ何もできない資本主義の枠がばっちりとはめられているところが、現代人の自虐性にぴったりとマッチしているのだ。
(1986年11月20日、小林正樹『大人のためのファミコン必勝講座』より)
今ではほとんどのプレイヤーにとって自明視されているゲームの中で「金を使う」という行為をさして「金がなければ何もできない資本主義の枠がばっちりとはめられているところが、現代人の自虐性にぴったりとマッチしている」などという誉め言葉は2004年現在のテレビゲームプレイヤーにはまず出てこないだろうし、ドラクエ1のNPCのを見て単調だと思いこそすれ、「話好き」などと表現しようなどとは思わないだろう。
その後の「RPG」概念の変容をめぐって †
この語も「RPG」は「正統派RPG」などという言葉を関される形で多少の変容を遂げていくことになるが、「RPG」という言葉の定着は、おおまかにはこの『ドラゴンクエスト』の普及が決定的な役割をはたし、日本で「RPG」といえば、『ドラゴンクエスト』とその後『ドラゴンクエスト』と双璧をなす大人気シリーズとなる『ファイナルファンタジー』シリーズの二つにイメージが代表される言葉となっていく。
80年代後半に、「RPG」という概念ははじめて現在のような形での「定着」をみせていった。
なお、その後の「RPG」概念の受容をめぐる変遷については、下に年表の形で整理した。
表:「RPG」概念の受容をめぐる変化
| 1974 | RPGの誕生:ダンジョン&ドラゴンズ |
| 1980 | コンピューターRPGの「古典」の誕生:『ウルティマ』『ウィザードリィ』『Rogue』など。この頃、欧米でも「RPG」という言葉使われ始める。 |
| 1983 | 日本にコンピューターRPGが多く紹介される。
ジャンル分類としては、アドベンチャーのサブジャンルとして紹介
安田均などが、RPGは「世界観とゲームの融合したものである」という位置づけを持ちつつ、RPGを日本に紹介。 |
| 1984 | パソコンゲーム市場で、国産初とされるRPG『ブラックオニキス』のヒット。 |
| 1985 | 家庭用ゲーム市場で、アクションRPG『ハイドライド』『ゼルダの伝説』などのヒットでアクションRPGが「RPG」の代名詞に。
TRPGファンが「TRPG/CRPG」の区別を多用するように |
| 1986 | 家庭用ゲーム市場で初のRPG『ドラゴンクエスト』の発売、 |
| 1988 | 家庭用ゲーム市場で『ドラゴンクエスト』『ファイナルファンタジー』シリーズの定着 「正統派RPG」という言葉の登場 |
| 1990 | シミュレーションRPG、アドベンチャーRPGなどサブジャンルが多数登場 |
| 1992 | 『摩訶摩訶』などが「RPGの常識を打ち破る」と宣伝 |
| 1996 | 『MOON』がアンチRPGという位置づけで登場 |
| 1997 | 『ファイナルファンタジーVII』が「銃とバイクでもファンタジー」として発売。「映画的」という言葉のイメージがネガティブに変化。
MMORPG『ウルテイマオンライン』がヒット。 |
参考(というかほぼまるまる引用) †
Ludologyを提唱するGonzalo Frascaの概念。日本語で言えば「押し付け感」とでも言うべきか。
ゲームをやっているときに感じるミッションを「押し付けられている」という感じをいだくこと。
分類と問題の構成 †
また、一言で「押し付け」とは言ってもいくつかのものを分けて考えてみることができる
- (A)プレイヤーが快楽的/自主的に選び取りたい、とういう自発的な動機への否定:やりたくもない経験値稼ぎなど(→直接に押し付けられている、というよりも、やりたくもないイベントでこれを求められると、大変にダルい気分に満ちてくる、という意味で。ときには、undermining効果。内発的的動機付けがうまく成立していない状態。ド・シャームの分類で言えば、originであるよりもpawnであると感じられるような状態。「〜への自由」が成立していない状態。)
- (B)体験選択のアーキテクチャの幅の狭さに対する不満:ストーリーが一本道でしかないことに対する不満、音ゲーなどで、決められた操作しか入力できない(自由な演奏ができない)ことに対する不満。状態を変化させる権限が内的な水準ではなく、外的な水準で制限されていることに対する不満)
- (C)プレイヤーを「観客」としてしまうことへの不満:ムービーシーンで、一切操作入力ができない時間に対する不満
など、「押し付け」という言葉によって一様に語られるていることにも意外と多くのパターンを見出すことができる。
(A)、(B)、(C)を構図的に整理してみると、
まず(C)では、まずプレイヤーが行為すること自体が否定されている。
次に(B)では、プレイヤーの行為そのものは否定されていないが、プレイヤーの行為の種類/選択肢の多様性が存在しないことが問題とされ、そこにプレイヤーの能動的なコミットメントの欠損が見出されている。
最後に(A)では、プレイヤーの行為を支える複数の選択肢の種類はは複数存在していることが前提としてある。だが、その中で勝利のための効率的な解として与えられる選択肢に強い偏りがあるため、実質的にプレイヤーの能動的に多様な戦略や楽しみを選び取る自由が奪われているということが見出されることになる。
これを、I.バーリンの「消極的自由/積極的自由」という概念に沿って考え直してみよう。消極的自由とは「決定の押し付けから逃げる自由」であり、積極的自由とは「主体的に決定ができることの自由」である。
ゲームの中における(A)(B)(C)の自由の喪失は、はたして消極的自由の喪失だろうか?それとも積極的自由の喪失だろうか?これを簡単に分類することは難しい。いずれにおいても積極的自由が成立していないという状況を見出すことはできるが、消極的自由についてはこれが疎外されている、と考えることがはたして妥当なのかどうかかなり微妙な問題である。
なぜか?ゲームにおける「押し付け」は人間対人間という構造においてではなく、アーキテクチャ対人間という構造の中で成立している。だが「消極的自由」という概念がそもそも、人間対人間というモデルを基礎付けにして成立している。ゲームを語る上で人間対人間というモデルにたった上での「自由」を語る議論は必ずしも効力をもたない。ゲームを語るとき、人間対人間、ではなく、アーキテクチャ対人間 という構造の上で議論を考え直していく必要があるということをこの一例は示している。*3
対応策 †
この押し付け感に対しては、例えば、以下のような議論をGonzalo Frascaは行っている。
- 1.「ミッションの内容自体の出来がよければ、押し付けなんか忘れて楽しいと感じるはずだ」
- 2.「ストーリー上で、ミッションに重要な意味づけがきちんと与えられていれば、押し付けではなくて、むしろ義務感がめばえてくる」
など。
また、言うまでもないことだが、「押し付け」というのは、単純になくせば済むようなものではなく、安易にこれを無くしてしまうと多くのゲームが、ゲームとしての構造そのものを破綻させてしまうことになりかねない。そもそもゲームのデザインをする、ということは「プレイヤーに何かをしてもらうこと」のデザインなわけだから、「押し付け」が消えうせることはおそらく永久にありえない。
ゲームの開発論議という視点から、この問題を語るとすれば「押し付け」そのものをなくすことではなく、「押し付け」とアーキテクチャの層と、「押し付け感」というプレイヤの感性の層を別の問題として区別し、「押し付け感」がどういったときに発生してくるのかを考え、「押し付け感」の部分に対する対処法を発見していくことではないだろうか。
そう考えると、Gonzalo Frascaの議論もゲームのアーキテクチャの層ではなく、プレイヤの感性の層の話としてしかこれへの対処法を語っていない、ということにも気がつくだろう。
Gonzalo Frascaは、「ゲームの持っている<勝つか負けるか>という二進法のロジックが、勝つためにはどんな手段でも用いるようにプレイヤーに推奨してしまうことで、それによって、どんな「シリアスさ」さえ台無しにされてしまう」として、コンピューターゲームで「シリアスなもの」を表現することが極めて困難であると主張している。その具体的な要素としては「再プレー可能性」(replayability)や、アクション可逆性(action-reversibility)といった点を挙げている。(→一回性参照)
物語表現や、ドラマティックな一回性のある体験というものが、「ゲームの論理」という別次元の論理と共存することによって生じた弊害という観点からの議論であるが、これに対して、Shuen-shing Leeは、むしろゲームシステムによってこそ、「悲劇」や「シリアス」さを表現することが可能である、と反論している。(→現実解釈としてのゲーム?参照)
関連 †
一回性、世界解釈
例えば「あとちょっとでクリアーできたのに」とか「あとちょっとで倒せたのに」という場合は「もう一回やらなければ気が済まんゾ。」という気分になってきたりする。あるいは「あとちょっとで死ぬかと思った」というのも緊張感があってよい。「これは全然話にならない」というぐらい難しかったり、簡単すぎたりすると今ひとつやる気がしぼむ。もっとも「あとちょっと」の度合いというのも上手いプレイヤーと下手なプレイヤーとか向き不向きとかあったりして調整が難しい。万人にとっての最大公約数的な「あとちょっと」ポイントのゲームバランスを作っていくのは実に大変な労働。(あとちょっと、というバランスを作るだけではなくそれをやってやろうというテンションを保たせることも大切)
この「あとちょっと」というリアリティがゲームのおいて大きな役割を果たす、というのは単にゲームの開発技法として注目すべきだ、という議論のみにはおさまらない。「同じ作業を何度もやりなおさせる」というような一般的には飽き飽きとさせるような行為を、強制的にではなく、自発的に促すという性質をゲームがもっているというようなゲーム・メディアの独自性をここに見ることも可能だろう。
パッと思いつく「おもちゃ」の定義といえば、「遊び道具」ということだろうが、おもちゃとは何か、という問題も「遊びとは何か」「ゲームとは何か」という問題同様に実はけっこうややこしい。おもちゃの定義としていくつか思いつくものをとりあえず以下にならべてみる。
- 1.「ゲーム」を成立させるための道具(将棋の盤と駒、バット)
- 2.ごっこ遊びの道具(人形)
- 3.大人の道具のミニチュア(子供用ミシン)
- 4.他者の代理(いとまき、人形)
- 5.工作などのための道具(粘土、積み木、塗り絵)
- 6.パズル(クロスワード、ピクロス、知恵の輪)
- 7.不思議なもの(手品、万華鏡)
- 8.かわいいもの、きれいなもの。宝物。(人形、万華鏡)
- 9.イリンクスのための道具(スケボー、スキー板)
"game"と"toy" †
ウィル=ライトは『シムシティ』はgameではなくtoyだと語る。これをコスティキャンは引き合いに出してでは、gameとtoyの境界線を分けるのは何なのか、と論じる。
コスティキャンはその境界線を「目的」の有無に見出す。「目的」をもって何か行為する場合は、目的の成立/不成立という結果をもって自動的に勝ち/負けといったコードとも強い関連を持つに至る。こうした「目的」をもってtoyを遊ぶことができれば、それはgameである、というのだ。
たとえば、『シムシティ』を単に何の目的もなく、自分好みの街を作ろうとするように遊べば、そのとき『シムシティ』は"toy"である。だが『シムシティ』をプレイする際に、人口を50万人まで増やす、という目的をもってプレイすればそれは勝敗条件が加わり、"game"として機能する、というのである。
情報環境、メディア論的な意味での「アーキテクチャ」と、経営学的な意味での「アーキテクチャ」について、それぞれ解説する。
濱野智史は、東浩紀、ローレンス・レッシグらの議論を参照しつつ、アーキテクチャという語を「情報環境」の言い換えとして採用している。下記、濱野の議論を要約する。(http://wiredvision.jp/blog/hamano/200705/200705231549.html)
- 1)任意の行為の可能性を《物理的》に封じてしまうため、ルールや価値観の内面化のプロセスが必要ない。
- アーキテクチャとは、法律のことでも、規範(慣習)のことではなく、行為そのものを原理的に制限してしまうような仕組みのことである。たとえば、「自動車にアルコールの検知機能を設置し、そもそも飲酒している場合にはエンジンがかからないようにする」という規制方法などがそれにあたる。「アーキテクチャ」は、どんな考えや価値観の持ち主であろうと、技術的・物理的にそこに従わせてしまうことが可能なものである。(東浩紀は、価値観の「内面化」プロセスを必要としないという点を、フーコーの「規律訓練型権力」と対比させ、「環境管理型権力」という概念を提示する。白田秀彰は、アーキテクチャによる法の実行を、一般的な法の実行形態と区別し、「法の完全実行」と呼んでいる。)
- 2)さらにその規制(者)の存在自体を気づかせることなく、被規制者が《無意識》のうちに規制を働きかけることが可能
- このような「アーキテクチャ」を基盤にした権力装置の下においては、行為をコントロールされている側が、行為をコントロールしているものの存在自体に気づくことが難しくなる。たとえば、「マクドナルド化」(マクドナルドにおける客に対する工学的管理方法)と名指されている事態などは極めて気づくことが難しい。あるいは、DRM(電子著作権管理)技術や、CCCD、コピーワンスなどもこの例として挙げられる。
以上、アーキテクチャとは、人間によって作り替えてしまうことが可能な、行為の環境である。アーキテクチャ=インターネットやVRの世界は、この数十年の間に急速に拡大を迎えてきている。「アーキテクチャ」の操作による、人間の行為・意識の変容といった事態は急速に深刻な事態として現れてきた。論争となっている際たる事例は、著作権論争にだが、アーキテクチャの構築/操作をめぐる最も先端をゆく世界の一つは間違いなくコンピュータ・ゲームの世界だろう。
同じく、濱野による「アーキテクチャ」という観点からゲームについて論じたものとしては、下記二点がある。
- 濱野智史,2007,「第17回 「マリオカート」と「ニコニコ動画」の共通点」(『濱野智史の「情報環境研究ノート」』)
- 濱野智史,2008,「Googleを攻略せよ ―情報環境≒ゲームを通じた「学び」の可能性」(『未来心理』vol.12 モバイル社会研究所発行)
手前味噌ながら、下記も同様の問題意識に基づくものである。
- 井上明人,2006,「第17回: オンラインゲームの現在 ―拒否されるゲームジャーナリズム―」『情報通信ジャーナル』所収
藤本隆宏は、日本の自動車産業の競争力について論じる文脈の中で、「アーキテクチャ」の概念を「どのようにして製品を構成部品や工程に分割し、そこに製品機能を配分し、それによって必要となる部品間・工程間のインターフェイス(情報やエネルギーを交換する「継ぎ手」の部分)をいかに設計・調整するか」と位置づけ、i.モジュラー型(組み合わせ型)/インテグラル型(摺り合わせ型) ii.オープン(開)型 /クローズ(閉)型のという類型を提示している。
- モジュラー型とインテグラル型(機能と部品の関係性、部品間の相互依存度についての分類)
- モジュラー型アーキテクチャとは、機能と構造(部品)の対応関係が一対一となっており、部品関係の相互依存性が低い設計物を指す。代表的なものとしては、IBM/360などが挙げられる(→関連:モジュール化)。一方で、インテグラル型アーキテクチャとは、機能と構造(部品)の関係が錯綜しており、特定の部品が特定の機能と一対一対応になっていないようなもののことである。代表的なものとしては、自動車が挙げられる。
- オープン型と、クローズ型(インターフェイス公開度合いについての分類)
- オープン型アーキテクチャとは、部品間を連結するインターフェイスについての規格が、個別の企業を超えて共有され、業界標準となっているようなものである。基本的にモジュラー型であり、代表的な事例としてインターネットのTCP/IPや、パッケージソフトとハードウェアの関係性などが挙げられる。一方で、クローズ型アーキテクチャとは、インターフェイスについての情報が、一つの社内で囲い込まれているような場合のことを指す。
上記の二分類×2のセットから、藤本は表1のようなマトリクスを作り、三つの類型がありうることを指摘する。
| インテグラル ← | →モジュラー |
クローズ
(囲い込み)
↑ | クローズ・インテグラル | クローズ・モジュラー |
↓
オープン
(業界標準) | - | オープン・モジュラー |
ゲーム産業においてこの三類型を当てはめると、おそらく以下のようになるだろう。
- 1.クローズ・インテグラル
- 一つの社内で、特定のゲームエンジン(ミドルウェア≒インターフェイス)を共有せずに、開発を行っていくようなソフトウェア開発スタイル。中・小人数によるアジャイル型開発のような場合には、その柔軟性の強さから強力に機能する場合があると考えられる。
- 2.クローズ・モジュラー
- 一つの社内で、ゲームエンジン(ミドルウェア≒インターフェイス)を共有しながらのソフトウェア開発。例えば、カプコンやEAなどが挙げられる。自社でゲームエンジンを開発する体力のあるような大手の開発会社での、大人数での開発には適したスタイルだと考えられる。
- 3.オープン・モジュラー
- ゲーム業界全体で、ゲームエンジン(ミドルウェア≒インターフェイス)を共有しながらのゲーム開発。例えば、Unreal Engine3や、Doom Engineなどミドルウェア産業が強力に機能している北米のゲーム業界の状態は、この状況に近い(ただし、きわめて高価なミドルウェアであるためミドルウェアを「共有している」という状況とは違うだろう)。自社でゲームエンジンを開発する体力のない、中小のゲーム・デベロッパーが開発を行う際の業態としては適した状況だと考えられる。
- 日本国内では、nScriptや、吉里吉里といったミドルウェアを公開ミドルウェアをベースに中・小規模開発を行っている美少女ゲームのノベルゲーム界隈などは、ほぼ完全な、オープン・モジュラー型であると言える。
- または、ゲームハード/ゲームソフトの分離、インターフェイス公開の状況も準オープン・モジュラー方式と言うべきだろう。とりわけ、プログラム仕様を公開してサードパーティによるゲームソフトの開発・販売を可能としていた、Atari VCS(Atari 2600)などは、ほぼ完全なオープン・モジュラー方式である。一方、任天堂やソニーなどハードメーカーによるソフトウェア販売の「許諾」を必要とするような方式は、準オープン・モジュラー方式と言うべきだろう。
参考
ジャンルの成立と変遷 †
ジャンルの呼称としては1983年ごろに頻繁に使われ始めた。
それまでは、アクションという言葉が使われずに「反射型ゲーム」「ゲームセンターであるようなゲーム」「アーケード」「リアルタイムゲーム」などという呼称が乱立していた。83年にジャンル区分けがなされるころに使われ始めた後、84年にゲーム雑誌等のレベルで普及していく。おおまかに「反射神経に頼るゲーム」という意味では、現在の意味と近い。
80年代中盤ぐらいには、まだ「アクション」の分野に含まれているジャンルが現在と比べて非常に多かったという特徴がある。たとえば現在なら「シューティング」として独立したジャンル名称を与えられているジャンルの当時では「アクション」のサブジャンルとして語られていたし、「スポーツ」などもアクションのサブジャンル扱いを受けている。それらのジャンルがサブジャンルとしてではなく、独立した一ジャンルとしての扱いをうけるようになってくるのは、「シューティング」は80年代中盤〜後半にかけて、「スポーツ」は80年代後半になってはじめて、といった具合だった。
「アフォーダンス」はアメリカの心理学者のギブソンが作った造語。「説明しなくても意味が与えられるもの」ということ。桝山寛が『テレビゲーム文化論』(2001)にて説明している。
単に直感的に理解できるインターフェイスをデザインすること?といった感じの意味だという理解が一般になされているが、もうちょっときちんと説明をすると、人間がモノに向かって行為したときに、そこで返ってくるフィードバックを手がかりに、モノに対してどういう風に扱えば最適なのかというバランスを人間は調整していく。モノに対してなんらかのアクションをしかけることではじめて、人間はモノに対する関わり方を了解し、調整する。そういった形の環境世界と生物との相互関係の中での意味理解・調整の発動のありかたのことが「アフォーダンス」と呼ばれている。(というのが、私の理解。)
日本で読めるわかりやすい入門書として『アフォーダンス―新しい認知の理論』(佐々木正人、1994)、『知性はどこに生まれるか』(佐々木正人、1996)などを私は読んだが、詳しい友人に言わせれば、日本でのアフォーダンス理論の受容は、あまりにも佐々木正人さんに集約されすぎて「佐々木アフォーダンス」といえるような節があるため、きちんとギブソンの『生態学的視覚論』を読むべし、とのこと。
特にスクウェア・エニックスの作品などでは昔から深く意識されていることであるといえる。ゲームの世界観を保ったり、プレイヤーにゲームをプレイするテンションを保ってもらうために、ディズニー的なイメージの管理をほどこすこと。グラフィック、音楽はもちろん、インターフェイス、セリフのセンスなどにわたってイメージ管理が施されていないとちょっと雰囲気がよくない。
こうしたイメージ管理の徹底は、作品内においてなされると同時に、作品の広報・プロモーションにおいても重要視される。たとえばディズニーはディズニー作品を無断で用いた擬似商品などの流通を徹底的にとりしまることで、ディズニー商品のクオリティに一定の担保を図ろうとしている。
しかし、ディズニー的なイメージ管理戦略をゲーム会社がとるということは諸刃の刃であるともいえよう。(1)まずは、ゲーム内のキャラクターがプレイヤの想像力に喚起されてポリフォニカルに戯れるためには、そのソースとしてのキャラクターのイメージが無残な消費のされ方をしないように管理していくことはまずは重要な意味が認められる。(2)だが、おなじく、ゲームというメディアはその性質からして*4、ゲームプレイヤによるどうじん的文化と極めて強く結びつくような性質をもつものであり、どうじん文化によって逆に作品そのものがエンパワーメントさせられるという側面がある。
例えば、『ドラゴンクエスト4コマ漫画劇場』シリーズはどうじん的な文化との親和性を上手く利用したものであると捉えることができるが、一方においてはスクウェア・エニックスによる著作権上のとりしまりの厳しさは一部のゲームプレイヤからの反感もまた買っている。実際に、スクウェア・エニックス社内においてどうじん誌を発行したことによる退職問題などといった事件も噂として流されており、この折り合いをどのようにつけていくのか、というのはゲームのパブリッシャーにとっての一つの課題であるといえよう。
眩暈(イリンクス) カイヨワの遊びの四分類の中の一つ。メリーゴーランド、ぶらんこ、ワルツ、スキー、登山、空中サーカスなど。(『遊びと人間』)
コンピュータ・ゲーム、あるいは遊びをめぐる批判の一つとして、人間の自覚的な選択、責任といった範疇の外側の領域に拡がる、「イリンクス(目眩)」をめぐるものがある。それは、カイヨワにおいても次のように懸念されている。
「なにか魅惑的なものに引きつけられることをすべて眩暈と名付けねばならないが、その最初の作用は、不意に生存本能を襲ってそれを麻痺させることである。その結果人間は自らの破滅に向かって引きずられ、自分自身の滅亡の幻影ヴィジョンそのものの働きから、恐怖によって彼を誘惑しようとする牽引力に逆らうまいという信念のようなものをいだく。この強い牽引の力は、否(ノン)と言うための力を奪ってしまうが、よく考えてみれば、この拒否の力の中にこそ、理解力のある思考の土台と自由な決断の基礎とが同時に認められるのである。[中略]眩暈はまずもって人間の自律性を破壊する」
(ロジェ・カイヨワ『本能』p.55、強調部分筆者)。
このような観点から、イリンクスを批判的を検討していくことが、ゲームの悪影響論を考えていく上での争点になっていく。
ここで何点か確認しておこう。
- イリンクス=ゲーム、遊びの全てか。
- イリンクスへの批判とは「ゲームや遊びに関わることによって全ての人々が判断能力を失う」という批判とは必ずしも一致しない。カイヨワも挙げている通り、「遊び」の楽しみとは、多元的なものである。ミミクリ(模擬)、アレア(賭け)、アゴン(競争)、などの様々な要素がある中でその一つとしてイリンクスは存在しているに過ぎない。
- イリンクス=善悪を問えるか
- 「イリンクス」という領域の特徴は、それが良くも悪くも意識的な思考や判断力の外側に位置するものだ、ということである。それゆえに、イリンクス自体が悪か善か、といった問いはある意味でナンセンスである。悪を選び取るわけでもなく、善を選び取るわけでもなく、「判断せずに選び取ってしまうようになる」ものである。それゆえ、そこには、責任を引き受けるべき主体の「選択」というような行為を見て取ることは難しくなる。たとえば、快楽中枢を電気で刺激して操られているマウスのような生物について、マウス自体の責任を問うことは難しい。
- 参考
- 近藤秀樹「「遊び」と「虚構」――カイヨワ『遊びと人間』を読む――」2008
- カイヨワ『遊びと人間』(増補版)多田道太郎・塚崎幹生訳、講談社学術文庫
- カイヨワ『本能 その社会学的考察』野村二郎・中原好文訳 思索社 1974
ゲームにおけるインターフェイスとは何だろうか、と考えてみると、いくつかの段階に分けて考えられる
- (1)コントローラー、キーボードといったデバイス(ハードウェア)
- (2)モニター上に投影されている矢印など (ソフトウェア1)
- (3)モニター上のプレイヤーキャラクターの身体 (ソフトウェア2)
インターフェイスの設計は、インタラクティビティの設計に関わるもっとも重要な要素であると言えるが、アーケードゲーム、家庭用ゲーム、PCゲームによってインターフェイスはまったく別の発展を遂げている。
アーケードゲームの場合、コントローラーやキーボードといったデバイスは、筐体ごとに自由にデザインされてきた。
一方で、家庭用ゲームや、PCゲームは、ゲームマシンやPCといったインターフェイスが最初から所与の条件として与えられているため、ソフトウェアのインターフェイスのデザインが発展することとなった。
コンピュータ・ゲームのインターフェイスデザインは、コンピュータ史にとっても大きな意味をもっている。たとえば、スティーブ・ジョブズが、元アタリの社員であった。
インターフェイスは、ゲームにおける身体の問題と直接に関わるが、たとえば、次のような議論がある。
(東浩紀他『不可視なものの世界』P251〜252 )
「現代思想系の身体論はたいてい「計測不可能性」に焦点をあててきたわけだね。世界の表面には言葉で文節化された―――丸山圭三郎の言う「言分け」された世界があって、その下に記号では文節化できない身体があるといった話ね。メルロ=ポンティ風にいえば、まさにその身体こそが「見えないもの」なわけだけど、これはつまり、浅い/深い、見える/見えない、計測可能/計測不可能の対立でできている世界観だ。けれどオタクの身体性はどうも違っていて、もっとガジェット感覚というか、身体も機械みたいに捉えられている。
実際、そういうことは現代思想でも八〇年代から言われ続けていて、サイボーグとかテレプレゼンスとかが注目されているのは、そういう文脈だよね。
(中略)
実際に、その変化が九〇年代に最もラディカルに現れたのが格闘ゲームの身体でしょう。三つのボタンのみを媒介にキャラクターと同一化する、というのはつまり、まったく計測可能な約束事でしかないのに、プレイヤーはそこに計測不可能な身体を感じてしまっているということだよ。ボタンをそのまま身体として感じられる、というのはとても不思議な現象だと思うんだ、少なくとも、メルロ=ポンティのような身体論では説明できそうにない」
「双方向性の」「対話式の」という意味を表す、interactiveの名詞形(英語)。例えば「ボタンを押す」という動作をプレイヤーが起こすと、ゲームの側で何かの「反応を返してくる」ということは、互いにアクションを起こすわけだから「Inter」+「Active」。
これこそがビデオゲームの本質的な要素である、と指摘されることの最も多い用語の一つ。「インタラクティビティ」がゲームにとって重要な要素の一つであることは確かだが、インタラクティビティだけが特権的に「これぞゲームの本質」として無反省に祭り上げられるのはちょっと、いかがなものか。
また、細かい議論で恐縮だが、「ゲームなんてただのプログラムなんだから、こっちのアクションに対して、ゲームがアクションを返してるんじゃなくて、単に<ボールを落としたらボールが落ちる>というような物理現象とたいしてかわらないんじゃないの?」とかそういう話をする人もいたりして、「じゃあ、インタラクションっていうのはどういうことさ」ということを、こういう形で聞かれると、結構みんな答えにつまってしまう。
ここで強引に答えてみると「インタラクション」の問題系統の整理の仕方は「Inter」と「Action」の二つにわかれる。
「Inter」というのはつまり、主体と主体の間で情報の送信と受信がきちんとなされているか、という問題。主体と主体はきちんと結ばれているか、という問題である。
それに対して「Action」というのは、例えば、テレビゲームというのは「私」と「何か」の間でのやりとりが成立しているわけだが、「私」と「何か」は本当にActionを起こしているのかどうか。「何か」は本当に自律的な意志を持った主体なのかどうか。という私に対する「何か」の主体としての認定論に関わってくるという系統の問題である。人間の友人は確かに「主体」かもしれないが、人工無能だとかと言われる擬似AIなどは「自律的な意志をもった主体」として、人間と同格の存在として認めていいのかどうか、という問題が残る。
で、まあ、だいたい、現在インタラクションとか何とかと言っているのは、厳密には、「Inter」の部分だけで「Action」の部分が本当にあるのかどうか、と言われるとそれはちょっとあやしい。だから、「インタラクション」みたいな「ヒト対ヒト」という主体間の関係性を想定した相互作用の言葉を使うんじゃなくて、「アフォーダンス」みたいな、「ヒト対モノ」「ヒト対環境」のフィードバックを想定した概念を用いた方がビデオゲームを語るのに適当な概念だ、という人もいる。個人的には、そこんとこに、こだわらない人は「インタラクション」でも別にいいと思うけど、こだわる人は「アフォーダンス」を推奨。「いや、俺はそんなわけのわからん言葉は使わん!」という人は、「俺のヤマト言葉」で新しい言葉を作ってみることを推奨。
参考:
エリック・ジマーマン『Rules of Play』:過去の「interaction」の定義をいろいろと参照している。
安川一 1993 『現代のエスプリ』掲載論文
ある業界における、企業間連携や、人材間の連携の動的構造は、しばしばエコシステム(生態系)として捉えられて説明がなされる。
A.企業間連携について(キーストーン戦略) †
マルコ・イアンシティと、ロイ・レビーンは企業間の連携における役割を、大きく三つに分類する。1.キーストーン種、2.ハブの領主、3.ニッチ・プレイヤーの三種類に分類する。
- 1.キーストーン種
- Microsoft Windowsなど。エコシステム全体を活性化させるような役割を果たす、ハブ的存在。
- 2.ハブの領主/ハブの支配者
- エンロンなど。エコシステム全体の中で、エコシステム全体にとってのハブとして機能するが、ハブとしての役割を利用して、他の企業から利益を簒奪するような戦略を採る企業。エコシステム全体を活性化させることができない。
- 3.ニッチ・プレイヤー
- 特にハブとしての役割を担わないような、個別の事業者。
キーストーン種が、システム全体の一部しか担わないのに対して、支配者は「システムの大部分を占有し、自ら排除した種の機能を乗っ取ったり、他の種の機能そのものを除去してしまうという性質を持つ」という。
また、ハブの「支配者」はネットワークをコントロールすることに注力し、価値獲得と価値創出の双方に単独で責任を負う。ハブの「支配者」は、システム全体の価値を必ずしも下げるわけではない。ただし、エコシステムそのものが、半自動的/サステイナブルに駆動するような状況を作り出すことができない。一方で、ハブの「領主」は価値横奪のみに注力する存在となる。
「キーストーン種」なのか「ハブの支配者」なのかという見極めは少し難しいが、ゲーム産業の例で言えば、
- 1.任天堂や、ソニーといったハードメーカーは、基本的にはキーストーン戦略を採り、実際ある程度までキーストーン戦略が成功しているという側面が見受けられるというべきだろう。だが、2006年〜2007年にかけての日本のゲーム産業における売り上げ比率を見てみると、任天堂一社の占める割合が著しく計らずしも、「ハブの支配者」になりかけている、という状況がみてとれる。
- 2.欧米における、ゲームエンジン・デベロッパーなどはキーストーン種としての位置を上手く成立させている、と言えるだろう。
B.人材間の連携について †
例えば、ウィル・ライトがシムズ・コミュニティなどのCGMサービスについて、エコシステムの比喩で語っている。
(→井上明人 2008,「CGMサービスにおけるユーザーの振るまい」『智場111号』参照)
参考:
- マルコ・イアンシティ/ロイ・レビーン,2007,『キーストーン戦略』翔泳社
- 井上明人,2008,「CGMサービスにおけるユーザーの振るまい」『智場111号』国際大学GLOCOM
カイヨワは20世紀フランスの思想家。社会学、哲学、文化人類学などに業績を残している。ゲームに関する議論で主に扱われるのは1958年に出版された『遊びと人間』である。カイヨワの議論の対象はフランス語における遊び"Jeux"についてであり、「ゲーム」についての議論ではない点に注意を払いたい。
定義 †
『遊びと人間』の中でカイヨワは以下の6つの要素により「遊び」を定義した
1.自由な活動
2.隔離された活動
3.未確定の活動
4.非生産的活動
5.規則(ルール)を持った活動
6.虚構の活動
分類 †
その定義の上で、カイヨワは「遊び」を、
1.競争(アゴン)、2.運(アレア)、3.模擬(ミミクリ)、4.眩暈(イリンクス)
の四つの基本要素によって分類可能であることを主張した。
ゲーム関係の議論だと以下の図がしばしば、不用意に引用される。
だが、それは日本のコンピュータ・ゲームの論者の不注意だといっていい。実はカイヨワ自身の作った構図ではなく、翻訳者の多田道太郎が、ホイジンガの発想を借りながら独自に図式化したものに過ぎないので、以下の分類図は日本でしか流通していない。そもそも、カイヨワの4分類において用いられる四つの遊びの類型は、イメージこそわきやすいが遊びを要素として抜き出したものであって、網羅性とは結びつかないのだが、日本ではカイヨワの分類が網羅性を持つという勘違いが(特にゲーム関係の文脈では)広くひろまってしまっている。
意志
↑
競争│模擬
ルール←──┼──→脱ルール
運 │眩暈
↓
脱意志
意志
↑
脱 競争│模擬 脱
所 計算←──┼──→混沌 自
属 運 │眩暈 我
↓
脱意志
もちろん、これはこれで、分析概念として面白くもある。だが、「A/非A」の構造を持つ対立項に、「B/非B」の二つをかけあわせてれば、なにをどうしようが網羅性は確保されるのであって、「A/非Aという構造が網羅性を持つ」というのは発見でもなんでもない。(たとえば、「全ての空間はトイレとトイレでない空間に分類される」という分類であっても空間についての分類としての網羅性を持ちうる)
問題は、A/非Aの境界を引くことによって何が明らかになるのか、ということである。
分析 †
カイヨワの分析対象は、遊びそのものではなく、『遊びと人間』というタイトルからもわかるように、遊びが人間社会の形成にとっていかに影響しているのか、という点である。
そこでカイヨワは人間社会は「遊び」という変数をもとに人間社会を次のようにマッピングしてみせる。
こうした比較や、相互関係を通して「遊び」という変数が社会にどのような影響を与えているのかを考慮してゆく。
ルドゥスとパイディア †
「ルドロジー」の研究文脈では、アレア、アゴン、ミミクリ、イリンクスではなく、カイヨワの提示した概念の中でも「ルドゥス」と「パイディア」という分析概念のほうが主に使われる。
ルドゥスとは、形がはっきりとしたルールなどもある程度まで確定的な遊びのことであり、パイディアとは、子供の遊びのような比較的縛りのうすい遊びである。
分析のしやすさ、という点からゆくとルドゥス的な遊びのほうが、パイディア的な遊びよりも、分析の俎上に載せやすく、『Rules of Play』などでもそういった形の遊びが中心的に扱われている。
批判 †
カイヨワへの批判は数多くある。「遊び」の概念的分析の妥当性に関する批判としては、たとえば、ジャック=アンリオ『遊び』(白水社、1986)などを参照のこと。
遊び論に関しての発展や、先行研究についての紹介としては、山田敏『遊び論研究』 (風間書房、1994)や、高橋たまき・中沢和子・森上士朗『遊びの発達学−基礎編−』 (培風館、1996)などを参照のこと。
その他、参考文献についてはhttp://www.critiqueofgames.net/data/booklist_date.htmlを参照。
参考:ロジェ=カイヨワ『遊びと人間』多田道太郎・塚崎幹夫訳 講談社学術文庫
ムービーシーンの中でも、特にユーザーが操作不可能になるシーンを「カットシーン」と呼ぶ。
欧米のゲーム開発教育などでは、いかにカットシーンを使わずにうまくストーリーテリングをするか、というようなことが教えられているらしい。
ジャンルの成立と変遷 †
「ギャルゲー」「エロゲー」「美少女ゲーム」「アダルトゲーム」「恋愛シミュレーション」……似たような言葉であるが、それぞれ、微妙に意味が異なっている。四つの言葉の意味のバランスがいつ、どのように変わったかについてすべて詳細に記していくと、大変長くなるので、省略する。
「ギャルゲー」という言葉について中心的に見ていくと、この表現が登場するのは、おそらく80年末ごろぐらいから使われ始めたのが初期の使用だと思われる。使用法は、90年代中盤の大ヒットゲーム『ときめきメモリアル』以前/以後でかなり変化が見られ、90年代前半には、「女の子がウリになっているゲーム」や「女の子のキャラクターが出てくることを楽しみながらプレイできるゲーム」というようなきわめて広い意味で使われる。あるいはそこにエロティックな表現が含まれるかどうか、ということで、「エロゲー」との差異において「ギャルゲー」という名称が用いられることが多かった。それが、『ときめきメモリアル』のヒット以降は、「女の子と恋愛することを主眼にすえたゲーム」という「恋愛」行為がゲームの中に入り込んでいるかどうか、という要素によって「ギャルゲー」が語られることが増えてくる。
このことによって、90年代前半/後半で「ギャルゲー」だったものがそうでなくなってしまったゲームを挙げると、例えば『ワルキューレの伝説』『マドゥーラの翼』等といった、単に女の子が主役(プレイヤーキャラクター)であるゲームが「ギャルゲー」という扱いを受けなくなってきた。
ジャンルの成立と変遷 †
はじめ使われはじめたのは87年ごろの「Beep」誌上のみうらじゅんによるコラムである、といわれている。これに類似した言葉使いとしては、「ダメゲー」という言葉が「迫るダメゲーの嵐!」として1986年9月19日号のファミコン通信の表紙の掲載されているトピックスとしてある。「ゲーム」を「ゲー」と省略する、という使用法がこの頃すでに存在していたようである。「クソゲー」と表現する以前にこのような類似表現が使われていたことは面白いが、この言葉以前は、単に「期待はずれのソフト」「面白くなかったゲーム」といった表現が使われていた。みうらじゅんが使用しはじめた後、他の雑誌でもこの表現が多く見られるようになるのが、80年代末。
1998年に書籍『超クソゲー』が発行されたことで、単につまらないゲームをけなす、というのみならず、つまらないゲームを、「ネタ」として消費する文化を生み出している。「クソゲー」に関する出版物をみてみると、1992年に一件出た後、1998年の『超クソゲー』が出た年にまとめて5件も出版され、その後も、99年2件、2000年1件、2001年2件、2002年2件、2003年1件、 2004年1件、と定期的に出版されており、確実に一定数の読者がみこめる分野として定着している様子をうかがうことができる。
→バカゲー?
クリス=クロフォードは、アタリ期のゲームデザイナーとして『バランス・オブ・パワー』などを制作し、ゲームの理論家としても知られている。
バランス・オブ・パワー デザイナーズノート †
『バランス・オブ・パワー』の制作時に何を考えたか、という話が載っている。
クロフォードによれば「ゲーム」の分類は、以下の5つになる。
1.ボードゲーム:各自のコマがボード上でどんな位置関係にあるかを分析することが最大の関心事
2.トランプゲーム:カードの組み合わせを分析することが最大の関心事
3.体を使うゲーム:勝つために自分の体を効率良く動かすかが最大の関心事
4.子どもたちのゲーム:いかに社会的なスキルを使うかである
5.コンピュータゲーム:
※下記の記事は5年以上前もので、現在はかなり変わっています。井上による2008年7月現在のゲームの定義論については、モバイル社会研究所発行の機関紙『未来心理 vol.13』http://www.moba-ken.jp/theme/msr/msr_cover/msr_013 にて掲載されたものをご参照ください。
→「遊びとゲームをめぐる試論 ―たとえば、にらめっこはコンピュータ・ゲームになるだろうか―」http://www.moba-ken.jp/wp-content/pdf/vol.13_inoueakito.pdf
ゲームの定義はさまざまなものが提出されているが、当サイトではとりあえず以下の三条件を「狭義のゲーム」の成立要件とかつて、していた(ただし、ビデオゲームが必ずしも以下のような意味での「ゲーム」である必要性があると論じるつもりはない。ビデオゲームと狭義のゲームはイコールの関係にはない)
- 1.ルールのよって行動のパターンが限定されていること
- 2.行為、行動、意思決定の指針が目標や評価システムによって方向付けられていること。
- 3. ゲームの参加者のとった行動(選択)の差によってゲームの結果および過程が異なるものであること。
もっとも、こういった「ゲーム」の定義を行う基準は、数多くのものが考えられ、細かい話をすれば、あの場合はどうなのか、この場合はどうなのかというようなところで、重箱の隅をつつくような議論が何ヶ月も繰り広げることができるような議論である。だが、そういった議論というのも結局は、「ゲーム」の範囲設定をどの程度のところまで置いて考えるか、という点に大きく依存している。どんなに細心の注意を払った定義をしたところで未来においてその定義の境界例となるような作品が出現する可能性は永久に否定できない。
重要なことは、「完璧に妥当なゲームの定義」などというものではなく、たくさんの定義がある中で多くの人が納得するようなものをどれか一つ採用しまったり、議論に応じて必要な定義を選び取れるような多種の定義が参照できることだろう。
他の定義もいくつか紹介しておこう
- ○コスティキャン(2002)「内部的な意味でゴールの方へ努力することをプレーヤーに要求するようなインタラクティブな構造(an interactive structure of endogenous meaning that requires players to struggle toward a goal)」
- ○ざるの会(1997)「「ゲーム」に近似した関数を核とし、人間の入力に対して、快感を供給するべく映像・音響に類する刺激に変換された出力を行なう、関数群体系」
また、これらの定義群を大別してみると、
(A)「楽しみ」という形でゲームプレイヤーの中に沸き起こる主観的な感覚を軸に定義を考えるもの
(B)ゲームプレイヤーの主観的感覚は無視して、観察可能な構造に着目するもの
というような2つの形に分けて考えることができるだろう。
対象について †
特に問題となることの一つが、どこからどこまでがゲームか。という話である。
境界例としてしばしば議論となるものをいくつか挙げてみる。
(詳しくはゲームの範囲設定を参照)
- 1.「遊び」と「ゲーム」の区分はどこで引けるか
- 2.「play」と「ゲーム」の区分はどこで引けるか
- →Zimmerman&Satie『Rules of Play』の議論を参照
- 3.「パズル」はゲームか
- →結果の多様性がない、という意味ではあまりゲームではない部分もある。だが、パズルを完成させられるかどうか、ということは結果が不確定なのでゲーム。
- 4.「宝くじ」はゲームか
- →戦略性が機能しうる宝くじなどであればゲーム。たとえば、運の要素がでかくても、競馬はゲーム。
- 5.最適解が明らかになっているもの(○×ゲーム)はゲームか
- →最適解が明らかになってからはゲームとして遊べないが、最適解が明らかになる瞬間まではゲームかも。
- 6.推理小説はゲームか
- →読者の行為のありようによっては、ゲームをやっているのに近い状態でありうる
- 7.恋愛やビジネスはゲームか
- →通例、ゲームとしての要素をいくつか含むので「広義のゲーム」とするか、「パイディア」とする。
関連 †
ゲーム性ゲームデザイン論遊び研究狭義のゲーム性?ゲームの範囲設定
「ゲーム」の定義と、「ゲーム」の範囲設定は、同じようなことに思えるだろうが、ちょっと違っている。ゲームの定義は、定義を作る人がだいたいこういったものが「ゲーム」だろう、というイメージを元にして、定義が練られ、その定義によって、あいまいに存在した「ゲーム」の範囲設定が、逆照射される形で、うきあがってくる。両者は、一見同じようなものに見えるが、一方が一方に対して影響を与え合うようなフィードバックの関係性におかれているものである。
それはさておき、「ゲーム」としてカウントされたり、されなかったりする境界例にどういったものがあるのか、簡単に見ていこう。
(1)競技:「勝つことが目的であって、楽しむことが目的じゃないから」などという理由でゲームとされないこともある
(2)パズル:「駆け引き要素がない」という理由でゲームでないとされることもある。
(3)ギャンブル:「完全に運の要素しかなく、プレイヤーの努力のしようがないから」という理由ではずされることもある。
(4)遊び:「ルールを持たない行為である場合があるから」という理由ではずされることもある。
(5)プロのやるゲーム(プロボクサーや、プロゲーマーなどの):「楽しむことが目的でない」という理由で。
以上は、「ゲーム」の議論だが、「コンピューターゲーム」となると、また範囲設定の境界例となるものがちょっと違ってくる。
(1)エディター:「ツクール」シリーズなど。「ソフト内部に目的が存在しないから」という理由で。
(2)将棋、囲碁など:「コンピューターでなくとも、ゲームとしてはもとから存在するから」という理由で。
(3)データベースソフト:「ソフト内部に目的が存在しないから」といった理由で
などなど。挙げていけばキリがないが、「えっ、これも外しちゃうの?」みたいな部分は人それぞれでけっこうわかれるものがあるのじゃなかろうか。
ゲームデザイン論遊び研究狭義のゲーム性?ゲームの定義論
概念の成立と変遷 †
一般に日本ではじめて、「ゲームデザイナー」という肩書きを使いはじめた人物として遠藤雅信氏がピックアップされることが多いが、「ゲームデザイナー」という肩書きを用いはじめたのは、日本で言えば、ボードゲームのウォー・シミュレーションゲームの開発者であった、鈴木銀一郎のほうが、数年早い。さらに「ゲームデザイン」という言葉に限っていえば、1980年に雑誌「スーパーアート悟空」の特集タイトルとして「ゲームデザイン」という言葉が使われたのが、発見できる限り一番古いものだった。
なお、「ゲームデザイン」「ゲームデザイナー」という言葉を関していたり、そのことを中心とした出版物に関しては1990年に1件、91年に1件、94年に3件、95年1件、96年1件、97年1件、98年1件、99年1件、2000年1件、2001年1件、2002年3件、2003年1件、2004年1件といったペースで出版されている。これと比較して他の出版件数のジャンルを見たときに、ゲーム業界への「就職本」のジャンルがちょうど似たような時期に似たような件数出版されており、「ゲームを作りたい人」というジャンルの読者がちょうど同じ90年代初期から一定数以上の数が定着し、その後だんだんに増えていったことがわかる。
日本語で簡単に読めるものとしては、クロフォード『The Art of Computer Game Design』(1982)、コスティキャン『ゲーム論』(1994)、田尻智『新ゲームデザイン』(1995)、ざるの会(1994-1997)などが挙げられる。
蛇足かもしれないが、「ゲームを考える」といったときに真っ先に「ゲームデザイン論」的なものしか考えない人がけっこういる。だが、ゲームデザイン論はゲームを考える上での一分野でしかない。プログラマーの問題意識、グラフィッカーの問題意識、広報担当の問題意識、批評の問題意識、ゲームを買う親の問題意識と、そういった問題意識の多様性を考慮せずに、「おまえの言ってることは下らない」とお叱りをいただくことがあるが、立場の違いの問題を、議論の水準の問題にされても困ってしまう。「あなたにとって役に立つこと」と、「私にとって役に立つこと」との差異というのは確実にあるのわけで。
クロフォードのゲームデザイン論?
http://www2.airnet.ne.jp/ojima/acgd/Coverpagej.html
コスティキャンのゲーム論?
http://www01.u-page.so-net.ne.jp/da2/babahide/library/design_j.txt
コスティキャン用語。
「ゲームにおける行動は,ゲームトークンによって実行される。ゲームトークンとは,直接プレーヤーが操作できる任意のものである。ボードゲームにおけるコマ,カードゲームにおけるカード,RPGにおけるキャラクター,スポーツにおいてはプレーヤー自身が,ゲームトークンである。
「資源」と「ゲームトークン」は別物である。資源は,目標を達成するためにうまく管理しなければならないものであり,ゲームトークンは資源を管理するために使われる手段である。」
ただ、微妙なケースとして、ババ抜きにおけるトランプのカードの存在が挙げられる。このときトランプのカードがゲームトークンであり資源でもある。
(この項目ははてなキーワードの「ゲーム性」とほぼ同じです)
主にビデオゲーム雑誌やゲームファンの間で日常的に使われる言葉だが、その定義ははっきりしない。
一言で言うとすれば「そのゲームならではのおもしろさや醍醐味」程度の意味とでもいったらよいだろうか。
特にこの言葉の用法として議論の俎上にのぼりやすいのは、ビデオゲームソフトを誉めたりけなしたりするときに使われるような「ゲーム性が高い/低い」「ゲーム性がない」などといったものいいである。言葉の定義が曖昧でありながらも、評価軸として決定的に重要なものとして作用する、という矛盾ゆえに多くの議論を呼びやすい言葉であるといえる。
言葉の起源と流通 †
言葉の起源からすると、そもそもからしてビデオゲームの言葉であったというわけではない。トランプやダーツなど各種の「ゲーム」が語られるようなところでいつのまにか使われていたような言葉だったようだ。
厳密な時期がいつのことだかは判然としないが、「ゲーム」に「性」をつけただけの言葉なので、たぶんどこかの誰かがそれほど強く意識もせずなんとなく使った、というのがホントの最初のことだろうと思われる。
ビデオゲームの登場以降ではビデオゲームの黎明期である1970年代後半にはすでに「ゲームマシン」誌などで使用されていた事例を発見することもできるが、その当時には現在のようなニュアンスが成立していた、という雰囲気ではない。
「ゲームの面白さ」のような意味で使われたっぽい比較的初期の事例としては、たとえば「Beep」誌の1985年5月号「ゲーム評論家入門」のコーナーにて亜蘭仁氏が「プログラマータイプ」の評論家を「(評論の内容が)ゲーム性よりプログラミングのテクに傾きがちで、文章がぎこちなかったら、ほぼこのタイプと思って間違いはない。」と書いていたりするのがかなり初期のものだろうか。
その後、言葉としての使用が定着していったのはおそらく1980年代後半だろうかと思われる*5。少なくとも1990年ごろのゲームレビューを読むとビデオゲームのよしあしを語るのに「ゲーム性がある/ない」「ゲーム性が高い/低い」といった言葉はすでに頻出している。
そして、1990年代中盤にもなれば、「「ゲームはゲーム性」などといった紋切型のコメントしかできないライターや批評家ばかりでは困ってしまいますね。」*6などといった議論すらサラっとなされており、「ゲーム性」にばかりこだわるような言説を冷ややかにみるような立場もこのころには成立している。
その後、一般的には『ファイナルファンタジーVII』の発売時期(1997年)を前後によく使われるようになったといった印象がもたれているようで、ネット上のあるゲーム辞典*7そこまで明確な言葉の流行があったというデータはない。(下に挙げる参考資料では雑誌「ゲーム批評」誌を調査しているが、「ゲーム批評」誌ではそこまで明確な差はあらわれなかったらしい)
なお、起源においてビデオゲーム以外のフィールドでも「ゲーム性」という言葉が使われている、と書いたが、現在でもビデオゲームとは関係のない文脈で「ゲーム性」という言葉が使われていることはしばしば存在する。
その他の言葉の用法について。 †
文脈によって複数の意味が使い分けられている。いくつか事例を挙げよう。
- 個々のゲームに固有の性質を表す場合
- 「ゲーム性が違う」というような言い回しによって捉えられる。具体例としては「インベーダーとゼビウスでは全然ゲーム性が違うよね」「FFとドラクエって実は別々のゲーム性があるよね」など。 → 「作品性」とか作品の個性、といった意味にも翻訳可能。または、「ゲーム性」という明示化できないアーキテクチャーが文脈において暗黙のうちに前提とされており、その差異を明示していると思われる。(ここには評価的な意味合いが含まれないこともあるし、含まれることもある)
- ゲームとしての要件を満たすかどうか、その程度を表す場合
- 「ゲーム性がある」「ゲーム性がない」といった言い回しによって捉えられる。具体例としては「人生ゲームにはゲーム性がない」「たとえば小説にゲーム性をつけていくと、ゲームブックになる」など。 → 「ゲーム」というカテゴリーに括ることが可能であるかどうか、という問題。「ゲーム」の定義が問題とされている。
- ゲームとしての面白さの評価を表す場合
- 「ゲーム性が高い」「ゲーム性が低い」といった程度を表す言葉によって捉えられる。具体例としては「風来のシレンはものすごくゲーム性が高い」(⇔低い)「最近のFFはゲーム性が薄くなった」(⇔濃い)など。 → ゲームに対する評価項目として機能してしまっているゆえにこの言葉の使用法が最も不評。具体的にそれってナニヨ?みたいな批判が続出。
などなど。
井上[2003]*8では、この概念が使われ方が、(1)「ゲーム性」という言葉の表現と、(2)「ゲーム性」という言葉の指す対象によって異なるという指摘を行われている。
以下の表は、「表現」と「対象」がどのような場合に、どういう言語使用がなされるのか、という点についての議論を簡単にまとめたものである。
→言葉の表現
↓議論の対象 | 「ゲーム性」の有無
(ゲーム性がある/なし、という表現の場合)
=ゲームの定義の問題とセット | ゲーム性の一元的比較
(ゲーム性が高い/低い、という表現の場合)
=ゲーム評価の絶対軸 | ゲーム性の多元比較
(××的なゲーム性が高い/低い、という表現の場合)
=多元的なゲーム評価 | ゲーム性の比較不可能性
(新規の/独自のゲーム性、という表現の場合)
=経験の新規性/独自性の表現 |
| 「ビデオゲーム」の特質が問題とされている場合 | インタラクティブな要素があるかどうかによって、ゲーム性(テレビゲーム性)の「ある」「なし」が問われる | インタラクティブな要素がどの程度充実しているかどうかによって、ゲーム性の「高い」か、「低い」かが決まる。 | あるタイプを持った「面白さ」が存在していることを前提とされて評価される。たとえば「ドラクエ的なゲーム性で言えば、ドラクエVが一番だった」といった表現。 | 独特の/新規のビデオゲームならではのインタラクションを実現していると感じられるかどうかで、「新規の」、「独自の」という褒め言葉がつくかどうかが決まる。 |
| 「遊び(=面白さ)」の特質が問題とされている場合 | 面白いと感じられるかどうかによって、ゲーム性の「ある」「なし」が問われる。面白さを成立させているものの中身は何でもよい。 | どの程度面白いか、によってゲーム性の「高い」か、「低い」かが決まる。面白さの中身は何でもよい。 | あるタイプの「面白さ」が存在していることを前提とされて評価される。たとえば「ドラクエ的なゲーム性で言えば、ドラクエVが一番だった」といった表現。 | 独特の/新規の面白さが感じられるかどうかで、「独自の」「新規の」という褒め言葉がつくかどうかが決まる。(面白さの中身はどういった種類のものに支えられていてもよい) |
| 「ゲーム」の特質 | ルール・目標・自由などの「ゲームの成立要件」を満たすかどうかによって、ゲーム性の「ある」「なし」が問われる | 駆け引きや、戦略性、トレードオフといった要素の充実度合いによってゲーム性の「高い」か、「低い」かが決まる。 | あるタイプの「駆け引きの面白さ」のようなものがが存在していることを前提とされて評価される。たとえば「二人零和ゲームでは、囲碁を越えるゲーム性を持つゲームはない」といった表現。 | 独特の/新規の駆け引きや、トレードオフのシステムの実現と感じられるかどうかで、「独自の」「新規の」という褒め言葉がつくかどうかが決まる。 |
ここに示された、三種の「対象」は例示でしかなく、これらの対象の設定の仕方は必要に応じて変えられてゆけばよい、としている。
概念の可能性 †
注意深くこの語を追っていくと、様々な言葉の使用例を発見することができるが面白いことの一つは、この語に対するさまざまな形での批判や、あるいはその逆に「俺はゲーム性信者だ」と言うような肯定派(?)もいるなかで、とりあえず曖昧だなんだと問題もありつつもこの言葉によってなんとなくゲームファン達のコミュニケーションはなりたっていることだ。曖昧だけれども、この言葉によってコミュニケーション可能だ、ということだ。
それはつまりゲーマー達にはこの言葉によってある程度のズレはありつつもお互いに何かしらの形でこの言葉によってイメージが交換できてるということなのだろう。
統合的な捉え方 †
ゲーム開発者の桜井政博はこの概念を「リスク&リターン」という枠組みで捉えればよいのではないか、と提案している。ほかにも、多くの論者がいろいろと考えた末に、この概念を「駆け引きの妙」だとか「トレードオフ」といった側面から捉えられるのではないかと論じており、ここには一定の共通性がみられて面白い。
また、他の有力な捉え方としては、「トライアンドエラーでスキル向上をしていく学習過程」というような方向性も挙げられる。こちらは"A Theory of Fun for Game Design"(邦題:『「おもしろい」のゲームデザイン』2005)のRaph Kosterあたりが代表格だろうか(「ゲーム性」って言葉は実は使ってないけど、ゲームの面白さの本質を記述しようとする姿勢は海外の人もおんなじ)。Raph Kosterはゲームプレイ時において生じる学習過程を「チャンク」「パターン」などというようなゲームプレイヤーによる意識の形成から説明し、ここにゲームの面白さの発生の仕組みを見出している。
両者は、双方ともにゲームの「面白さ」を説明しようという点においては一致点を見出せる。だが、なぜこのような差異が生じるのか?
私見を述べると、前者の「トレードオフ」「駆け引き」といった捉え方ではゲームのルールの形式や構造に着眼されており、後者の「チャンク」「学習過程」といった捉え方では、ゲームのルールをプレイするプレイヤーの意識、感覚に着眼されている。そう見るならば、両者の定義するところには異なっていても実は着目する対象が少し異なっているだけということであって、両者の立場は対立しているというよりも相互補完的なものであると考えられるだろう。
対象について †
→ゲームの定義論を参照
参考 †
概要 †
日本大学文理学部体育学科教授の森昭雄による造語。
ゲームを多く遊ぶ人間の、ゲームプレイ時の脳波が一般的な状態と異なることを発見し、これを「ゲーム脳」と名付け、ゲームを遊ぶことの危険性を訴えた。
批判 †
ネットを検索すると、ほとんど批判しか出てこないといってもいい。
批判を要約すると「本当に普段と違うのか?」「違ったとして、それは本当に危険なのか?」という二点に集約される。
1.脳が本当に一般的な状態と異なると言えるのか。 †
- 調査として、「異常」を発見するための手続きがおかしいのではないか(統計手法の記述などが信頼に足る水準のものではない)
- 「脳波」は脳の状態を変化を測定するための手段としては、そこまで確実な意味を持つものではないのに、脳波の変化を重視しすぎているのではないか。
- スポーツをしているときも、似たような脳波が見られるときがあるのだが、これに対する言及がない。
2.異なったとしてそれが本当に危険なことなのか †
- 提唱者の森がゲームやサブカルチャーについて基本的な認識を欠き、ネガティブな意識を一方的に持ちすぎている。そして、森の言う「危険性」の立論は、論証を含まない推論ばかりである。
現在では、森氏の様々な失言*9により、「ゲーム脳」概念は、一般に広がってしまったトンデモのガセ知識という評価がネット上では基本的である。ただ、仮にも名の知れた大学の教授による議論なので、PTAなどが主催する形での講演会などが定期的に組まれている。
「デジタル・ネイティブ」 †
「危険性」を唱える森のようなネガティブよりの立場が存在する一方で、マーク・プレンスキー(Marc Prensky)などによって、デジタル機器を当然のようにして使いこなす世代の子供たちのもつ特有の思考力についてポジティブな立場からの研究をする立場もある。
参考 †
- James.Paul.Gee & Marc.Prensky "Don't Bother Me Mom-I'm Learning!: How Computer And Video Games Are Preparing Your Kids for Twenty-First Century Success - And How You Can Help!" (2006/)
- 森昭雄『ゲーム脳の恐怖』 2002
ゲームのマップには、単に色/形として描画されているだけの描画データの他に、「歩けるところ」「歩けないところ」であるとか「ダメージを与えられる場所」「ダメージを与えられない場所」といった当たり判定(コリジョン)と呼ばれるデータがある。この当たり判定とは、プレイヤーにとってみれば、ゲームの世界と自らがどのように関われるのか、というデータの塊であるといっていい。
それまでのゲームで、ただの背景にしか過ぎなかった「タンス」が開けられたり、破壊できたりする対象になっただけでも、プレイヤーにとっては、その世界との関われる幅が拡大したということであり、その世界のリアリティを増大させるのには一役買うことだろう。
しかし、こういった形の操作可能なものの数を増大させるという力技の作業だけが当たり判定の楽しみとは限らない。たとえば、『ジェットセットラジオ』で、電柱やガードレールが「スライディングできるもの」というそれまでにない意味づけをあたえられたり、『塊魂』ではネコや人や家屋が「巻き込めるもの」という特殊な行為の対象として成立することによって、我々の日常的に自明視している「電柱」や「ガードレール」「人間」などを見つめる感覚が、ゲームの側の世界の意味づけによって食い破られ、プレイヤーが世界を見つめる意識に、新たな形がもたらすことになる。
ゲームの世界における当たり判定の力業による拡大行為が、ゲームの外の「現実」からの意識を輸入する行為であるのに対して、ゲームの世界においてモノとの新しいかかわり方を提示する行為は、ゲームの外の「現実」へと向かって感覚を輸出する行為であると言える。そして、その輸出された感覚を持ったままで、ゲームの外の「現実」の街を歩けば、プレイヤーはおそらく街に対して、新たな感覚を手に入れることすらできるだろう。
『ワンダと巨像』では、リアルタイム・コリジョンと呼ばれる技術を用いている。
なぜ、コンピュータ・ゲームはこれだけ世界的な普及が可能になったのか。
おおざっぱに議論を整理すると、技術の変化、社会の変化、歴史の発展といった変数に注目した三つの仮説に整理できるだろう。
A.コンピュータとゲームの親和性 †
もっともわかりやすいものは、コンピュータという機械の持つ特質と、ゲームという行動様式が持つ特質の親和性を指摘するものである。
一つは、「ルールとコンピュータ」の関係性への着目である。コンピュータはルールのロジックを遺漏なくうつしとることができる。これはゲームの複製技術…とまはいわないが、これがゲームの大衆化を可能にした。 *10
そして、もう一つ、1960年代にコンピュータの発展の中心にいたハッカーたちにおける「ゲームをつくること」と「コンピュータシステムを改良すること」との両者の動機が地続きであったということを指摘するものである。ノイマン型コンピュータ上での世界初のシューティングゲームである「SpaceWar?!」*11の作者の一人であるアラン・コウトクはW3C副会長であり、世界で最初のアドベンチャーゲームである「アドベンチャー」を書いたウィル・クラウザーは実はARPANETの技術者である。現在でも、時代を象徴するような優秀なハッカーたちにプログラミングを促した動機がゲーム・プログラミングであったという事例は数多い。 *12
B.ポストモダン社会とのゲームの親和性 †
東浩紀は、現代の情報社会を二層構造で捉えることを提案する。*13東によれば、ポストモダン社会は人間的な欲求の回路と、動物的な欲求の回路とが分離しそれがゲームの消費構造に反映されている、という。
以下、私なりに言い換えると、前者はMMO的なオンライン・コミュニティに参加することによってゲーム世界内での社会性を獲得する欲望へとむかったり*14、あるいは桝山寛*15が指摘するような「コミュニケーション」の欲求を満たすツールとして発展し、これは『おいでよ どうぶつの森』の大ヒットのようなものを生み出している。
後者は、逆にコミュニケーションを極力まで縮減し、コミュニケーションの単位を最小かするようなFPS的なあり方や、記号的に「萌え」のデータベースの中で戯れる現代日本のオタク的な消費形態を生み出す*16。
#この解説は、参考:東浩紀+濱野智史ほか『InterCommunication?』No.55 Winter 2006「情報社会を理解するためのキーワード20」の「ゲーム」項目
C.高次のコミュニケーション・メディア説 †
Ricard.D.Duke『ゲーミングシミュレーション:未来との対話』では、ゲームという形式が、テキストによるコミュニケーションや、声によるコミュニケーションを越える高次のコミュニケーション手段として捉えられている。
この観点を下敷きに、進歩主義史観的な発想にたてば、コミュニケーションメディアが、小説/新聞のような文字メディアから、ラジオのような音声メディア、そして映画のような音声と映像を備えたマルチメディアへと発展してきたここ数世紀の歴史的発展の頂点に、ゲームというメディアの到来を据えることができる。
テキトーな図式。 †
なお、以下は2005年の9月頃になんとなく盛り上がって描いた図。「コミュニケーションの次元から」とかって書いているのは、いわゆる「言ってみるテスト」みたいなもんです↓
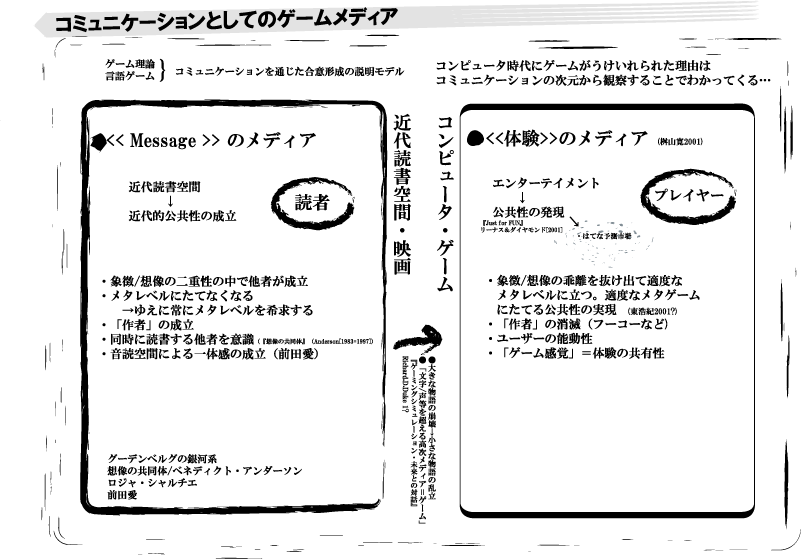
フランスの思想家ボードリヤールが彼の思想を語るキーワードとして用いて有名になった言葉。基本的な意味としてはオリジナルに対する「まがいもの」という意味。
だが、「まがいもの」だからダメだ、というのではなく、《模造品No3》は《模造品No3》としては世界に一個しかないオリジナルである、という考え方もできるし、ものごとには「本物(オリジナル)」も「まがいもの(コピー)」も実はきちんとした区別などつけられない。言い方を変えればある意味、現実に存在するものはすべて「まがいもの」である(=ハイパーリアルの世界)というような考え方というのもできるわけだから、「まがいもの」は「本物」に劣るものである、といったような形で貶めて考えるような必要というのはあんまりない。
だから例えば、ゲームの世界が現実の模造品である、というような言い方もできるけれども「ゲームを体験しているその人の時間」というのは、現実に体験されている時間なのであって、虚構の時間なのではない。
simulate は「まねる」、「擬態する」、「〜のふりをする」という意味の動詞。
simulation はその名詞形である。ふつうシミュレーションといえば,現実に存在する自称をシステムとして見なした上で、そのシステムのモデルを作り,これを使った実験を行うことを指す。
ゲームは、シミュレーションとは縁が深い。そもそもチェス、将棋をはじめとする、各種のボードゲームは、戦争のシミュレーションとしてはじまったものが、後に娯楽用に洗練されていったものである。
また、フォンノイマンとモルゲンシュタインによる「ゲーム理論」は現実の意志決定をシンプルにモデル化したものだし、近年では「シミュレーション&ゲーミング学会」という学会も存在する。(2007年現在、日本シミュレーション&ゲーミング学会会長は市川新)
「シミュレーションゲーム」というジャンルの定義は1980年代中盤に日本で成立した。
『信長の野望』のようなウォーシミュレーションゲーム(ストラテジゲーム)、『ときめきメモリアリル』のような恋愛シミュレーションゲーム、『シムシティ』のような都市運営シミュレーションゲームまで含めて、すべて「シミュレーションゲーム」と呼ばれる。
2.シミュレーションとエンタテイメント・ゲームの違い †
クロフォードによれば、シミュレーションとゲームの違いは次のように記述されている。
「シミュレーションの研究者は、あまりに複雑で計算が追いつかないとか、現象がややこしすぎて理解できないという場合に、仕方なしに現象の単純化を行う。それに対して、ゲームデザイナーはデザイナー自身が一番大事だと思っているパラメータにプレイヤーの意識を集中させるために、喜んで現象を単純化するのである。両者の目的には明確な差があるのだ。シミュレーションは、何かを計算したり評価したりするために行われるのに対して、ゲームは娯楽のため、そして何かを教育するために行われるのである(もちろん、その中間的なものも――)」(クロフォードのゲームデザイン論)
つまり、「娯楽」を重視すれば「ゲーム」であり、「再現性」を重視すればシミュレーションである、という立場がここでは表明されている。
こうした議論の妥当性はともかく、エンターテイメント産業に従事する形でゲームを作っている現場の実制作者たちからは、こうした言明がたびたび繰り返されている。
だが、一方で、こうした「ゲーム」と「シミュレーション」の違いを相対化して捉え、「娯楽重視」の立場も一つの選択肢でしかない、という議論も存在する(→http://d.hatena.ne.jp/hiyokoya/20041006、http://d.hatena.ne.jp/hiyokoya/20041007)
シミュレーション・ゲームを評価する際にはほとんど常に、「シミュレーションとして成立しているか」「ゲームとして楽しいか」という二つの評価軸のバランスが問題となる。典型的なのは「シミュレーションとしては良くできているが、ゲームとしては楽しくないリアルなフライトシュミレーション」として『エアロダンシング4』が評価されたり、「ゲームとしては面白いが、まったく現実の恋愛をシミュレートしていない」として『ときめきメモリアル』が評価されるといった事態だろう。
理想的なのは、シミュレーションでもあり、娯楽でもある、という状況であるが、この点に対して、割り切った姿勢をとっているのが『グランツーリスモ』シリーズである。『グランツーリスモ』を開発する山内一典は、「車を運転することは一般の人にも可能であり、楽しいのだから、それを忠実に再現すれば、現実と同様に楽しいはずだ」といった旨の発言をしている。
つまり、再現の対象である、現実が楽しければ、「シミュレーション(現実)/娯楽か(非現実)」という二項対立は成立しなくなる、ということだ。
ただ、この発言は実は「車の運転を楽しいと感じる人々がいる」という現実を前提としてはじめて発言が可能になっている、という点には注意しておきたい。「車の運転を楽しい」と感じない人間は、結局『グランツーリスモ』シリーズを楽しむことはできない。
現実(リアル)の参照項が消え失せ、それっぽい現実(ハイパーリアル)の内容だけが、現出するような事態をフランスの思想家ボードリヤールは「シミュレーション」と呼んだ。
日本でのボードリヤールの議論を参照しているものの一つは椹木野衣『シミュレーショニズム』(1991)である。
椹木によれば、「あらゆる事象が情報化されつつあるいま、すべては等価なものとして扱うことが可能である、そうであるなら、歴史とか地域的固有性といったものはすべて括弧に括ってしまって、いかようにも編集可能である。」*17という前提に立ち、現代アートの「カットアップ/サンプリング/リミックス」のキーワードによって説明してみせ、現代アートの展開に新しいビジョンを与えた。
さらにボードリヤールの現代日本における議論は、東浩紀『動物化するポストモダン』(2001)を抜きにして語ることはできないだろう。→動物化?,消費?
4.Richard D. Duke『ゲーミング・シミュレーション 未来との対話』 †
Dukeによれば、事象の構造そのものを理解をさせる、ゲーミング・シミュレーションとは、文字によるコミュニケーションや、音声によるコミュニケーションによってもたらされる理解よりも、より高次の理解をもたらす、伝達システムであるとされる。
こうした、高次の伝達手段としてみなされるゲーミング・シミュレーションは、さまざまな教育利用が研究されており、社内研修や、体験型学習といった形での応用が試みられている。
近年では、教育関係の文脈からはじまったゲーミング・シミュレーション研究とは別途にエンターテイメントゲーム文脈からの「シリアス・ゲーム」研究と、方向性が重なるところもあり、今後の協働が求められている。
日本のゲーム産業においては、1980年代後半より、急速に売れ筋タイトルのシリーズ化、および、新ジャンル勃興がシュリンクしてきた。
これについてファミリーコンピュータ以降のデータを実証的に検証したものとしては、生稲史彦、米倉誠一郎「日本のゲームソフト産業」(『一橋ビジネスレビューWIN2005』所収、53巻3号)に詳しい。
基本的だが非常に有効な手法。プレイヤーを簡単には決定不可能なジレンマの構造の中に置くことによってゲームの世界の中に迷い込ませる。基本的には「A」という側を優先すれば、魅力的な「B」という側の可能性をすてることになり、「B」という側を優先すれば「A」という側の魅力を断念することをプレイヤーは要求される。「Aの方が優れているのか、それともBなのか」という状況ではなく、AもBも捨てがたい、AもBも互いに微妙なバランスになりたっているのがベターだろうと思う。
それと人に聞いた話では、心理学のタームで以下のような用語があるらしい。
・回避−回避コンフリクト
→選択肢Aも選択肢Bもできればどっちも回避したい時の葛藤
・接近−接近コンフリクト
→できれば両方選択したい、どっちもオイシイという時の葛藤
・接近−回避コンフリクト
→気に入ったのを選ぶと嫌なことまでセットになってついてくる時の葛藤
混合戦略などでも、ジレンマはしばしばおとずれる。
関連 †
混合戦略読み?嫌な選択肢
ズレを成立させることは、ゲーム/遊びにとって極めて重要な要素の一つである。
(あとで書く)
当たり前の話だが、作品のカラーによって、プレイヤーに向き、不向きがあるし、そもそもその作品がターゲットとして想定している層も異なっていたりもする。基本的には難易度がどのくらいか、ということでプレイヤーがわかれるし(単に難易度が高い、低いというのではなく、幅広く用意して幅広い層を狙うものもあるが)、他にも操作方法がどうしてもしっくりこない人がいたり、ゲームの雰囲気が苦手な人がいたり、ルールがのみこめない人がいたり様々。どんなに面白い作品でも合わない人はいる。
数値表現の問題(数のコミュニケーション)と、テキスト表示の問題を嫌うゲームのあり方をまとめて「テキストレス」と呼ぶことにする
文章や数値を用いないこと。アクションゲームなどでは珍しくもなんともないが、RPGやアドベンチャーゲームにおいては『ICO』『L.O.L』などがある。また、近年の売れ筋の和製RPGでは、人がベラベラとしゃべるが、80年代のRPGでは記憶容量の乏しさも手伝って、しゃべるということがあまりなかった。
文章や数値表現はなぜ、嫌われるか †
文章や数値による表現を行うか行わないか、は、コンピュータ・ゲームにとっての一つの肝であると言っていい。なぜか。
簡単にいえば、その空間が「ゲームであること」を伝える手段として、文章や数値の表現は存在しているわけであるが、それはゲームをゲームとして成り立たせる一方において、ゲームをゲームでしかない、と認識させるものともなり得てしまう。「数のコミュニケーションなど嘘くさい!」という立場である。
『ICO』などでは、その徹底ぶりは激しく、HPを排除した結果として「一緒にいる女の子がさらわれるかどうか」がHPの役割を果たし、ヒントを出され方も言葉によるのではなく、ヒントとなる場所がゲーム内の登場人物によって指し示されるだけだった。
『ICO』がこうした形に落ち着くまではかなりいろいろな困難を乗り越えている。通常の手段である、数値や文章によるゲーム状況の表示をまったく行わないことは、ゲームをゲームたらせるためにはかなりの茨の道であるといえるだろう。たとえば『ICO』の次回作として制作された『ワンダと巨像』はテキストや数値による表現が極力抑えられてはいるものの、右下に小さなメーターを付けざるを得なくなっている
では、テキストレスの表現を目指すことはコンピュータ・ゲームというメディアの特性とはまったく親和性のないことなのかというとそんなことはない。
むしろ、1970年代や、80年代のコンピュータ・ゲームにおいてはテキストレスな表現こそが支配的だった。そして、当時は、テキストレスであることこそがゲームの感動を作り出していたといってもよい。あるゲームプレイヤーは『ドラゴンクエストII』の感動を表して「テキストなどなくともこれだけ強い感動を得られるということに驚いた」と言っている。
このゲームプレイヤーが感じているのは、粗く言ってしまえば、ゲームという経験が映画や、小説とはまったく別の経験に裏打ちされている、ということだが、より具体的にいえば、リピータブルであるがゆえの、繰り返しの日常生活の表現や、経験の積み重ねによる感情移入の成立といったことをこのプレイヤーは感じていたのだろう。
生活表現 状況主義?
「テレビゲーム」という概念はいつから登場したのだろうか。
コンピューターゲームの歴史は通常、1958年のウイリー・ヒギンボーサム(William A.Higinbotham)による"Tennis for Two"か、1962年の"SpaceWar?!"を起源として数えることが多いが、これは1980年移行のコンピュータ・ゲーム全盛期以降にはじめて「起源」として発見された歴史である。かつて「ゲームマシン」という言葉の指す対象は、決してコンピューターゲームを指すものではなかった。
まず、「テレビゲーム」それ自体を指す言葉が日本で使われはじめたことを70年代には確認できる。コンピューターゲームを世界ではじめて商業化しようとアタリ社が活動を開始し、アメリカで『ポン』が一定の成功を得るのが70年代中盤である。商業的に「テレビゲーム」が成立する70年代中盤までそれを指す言葉がほとんど存在していなかったことはごく当然のであると言える。
「テレビゲーム」の登場初期にこの表現が一般化していたわけではない。特に日本ではインベーダーブーム以前は、ゲーム業界紙「ゲームマシン」紙などをみても「ゲームマシン」がコンピューターゲーム一辺倒とはほど遠かったことがわかる。それを象徴的にあらわしているのは、インベーダー前夜の1978年の1月1日号(第87号)の「アミューズメントマシンのたどってきた100年」という特集記事である。
ここでは、「アミューズメントマシン」の歴史を日本とアメリカで比較し、アメリカでは「アミューズメントマシン」の歴史は、1978年から約100年前の1877年からはじまったことになっている。
1877年に何があったのか。
それは1877年「トーマス・エジソンが蓄音機を発明」である。「ゲームマシン」紙における「アミューズメントマシン」の歴史はそこからカウントされている。
なぜ、蓄音機の発明が、アミューズメントマシンの歴史の発端としてカウントされているのか。同紙の解説によれば、「蓄音機が娯楽用となるのに指して時間はかからず、今世紀はじめにはすでにロウ管式のジュークボックス、「カラマズーマルチホン」が硬貨作動式で出ている」という説明がなされている。つまり「ジュークボックス」という娯楽マシンの歴史として蓄音機がとりあられているのである。
また、1977年1月15日号(第64号)のアミューズメントマシン業界が今後どのようにあるべきかを論じた「対談放談」の中では当時コンピュータ・ゲームを産業として形成させるのに成功をおさめつつあったが、それもアミューズメントマシン業界全体から見れば、「一つの潮流」でしかなかった。
「アメリカのメーカーではその点はっきりしてますね。フリッパーはゴットリーブ、ウィリアムズ、バリー、ジュークボックスはシーバーグ、ロウAMI、ロックオーラ、ワーリッツアー。バリーなんかは、スロットマシン、ビンゴ、フリッパーがその生産の主軸だし、アタリはビデオTVゲームしか作らない。それぞれのメーカーが独自で自社で製造する製品のカテゴリーを守っている。」(P7)
「アタリ」はコンピュータ・ゲームを産業として成立させた輝かしい企業なのではな、ある特殊カテゴリーの専門業者、という位置づけで語られているのである。
インベーダー・ブーム †
さらに、「ゲームマシン」紙を続けてみていこう。
「ゲームマシン」紙において、コンピューターゲームの記事がメインを占めていなかったことはすでに述べたが、インベーダーブームの頃から急速にコンピューターゲームの記事が伸びていくことになる。
78年にインベーダーゲームがブームとなった翌年最初のゲームマシン紙1979年1月1日号の「新年展望」の特集では、当時アミューズメントマシン業界の大手企業であった、株式会社シグマ社の代表取締役真鍋勝紀氏が、昨年を振り返って
「さて、1978年を振り返り概観しますと、発展し続ける当業界にとって、よりいっそう大きな転換を成し遂げた一年であったと存じます。それを現象的に表現するとすれば、「ヴィディオ・ゲームがゲーム・マシンとして市民権を獲得した一年であった」と表現できると思います」(P5)
と述べる。この後、アタリ社の『ポン」からはじまる「ヴィディオ・ゲーム」の歴史を述べ「スキル・ゲーム「スペース・インベーダ」のフィーバーの内に、新しい年を迎えた」としている。
また、「ゲームマシン」紙に見える広告も77年から79年にかけて大きく様変わりしていることを見て取ることができる。77年の広告は、フリッパーや、スロット、ジュークボックスなどの広告が過半数を占めているのに対して、78年には『ブレイクアウト』および、その類似商品の広告が増加しはじめ、79年になると、広告の過半数は、『スペース・インベーダー』およびその類似商品、前年同様『ブレイクアウト』の広告、『コンピューターオセロゲーム』など、そのほとんどがコンピューターゲームなどによって占められるという事態が起こっている。
多様なハードの登場 †
さて、このような形で、「ヴィディオ・ゲーム」が市民権を得た、とされるのは、真鍋氏の言うように、78年、79年にかけてのことであったわけだが、「テレビゲーム」という言葉が、広義の意味でも狭義の意味でも、現在に近い形で使われるようになるには、さらに数年以上あとのことになる。
現在「テレビゲーム」という言葉の使われ方は、広義の意味では、コンピューターゲーム全般を指す言葉であり、狭義の意味では家庭用のテレビ投影型のコンピューターゲームのことを指しているわけだが、そもそも広義の意味での「テレビゲーム」が現在のような意味になるためにはコンピューターゲームがゲームセンターに置かれているアーケードゲームのみならず、パソコン用ゲームや、家庭用ゲームなどの多様な広がりが用意されていなければ、そもそも「広義」になりようがなく、狭義の意味では、家庭用ゲームの普及をまたなければならない。
もちろん、そのようなハードの普及だけが問題なわけではない。70年代後半から、80年代前半にかけて、様々なゲームマシンが一挙に普及してきたときに、それらを区別する言葉が最初から整然とした形で整理されたわけではない。
それらのハードの登場を整理しつつ、どのような言葉が使われていたのかを簡単に概観してみよう。
まず、先に述べた70年代末にインベーダー・ゲームがブームを引き起こし、「ゲームセンター」「ゲーム喫茶」が普及していった際に、同時多発的に、様々なコンピューターゲームの市場が勢いを増している。80年には、任天堂から「ゲーム&ウォッチ」がブームとなり、同じく80年代初期には、雑誌『I/O』や『マイコンBASICマガジン』などに代表される「マイコンブーム」が起こり、「マイコン」(今でいうパソコン)での海外からの輸入、国内開発共にゲームが充実してくる。
そこで、コンピューターゲームを指す言葉にも、同時に複数の言葉が登場してくることになる。まず「ゲーム&ウォッチ」のブームを主な対象として、コンピューターゲームを含め、電動オモチャ全般を指す言葉として「電子ゲーム」という言葉がメジャーになっている。そのような「電子ゲーム」を紹介する書籍としても1982年には実業之日本社から『電子ゲーム大作戦』(こどもポケット百科)『電子ゲーム大作戦 最新版』(こどもポケット百科) 、翌83年には講談社から似たような名前で『電子ゲーム必勝法』『新 電子ゲーム必勝法』が、84年には徳間書店から、これも似たような名前の『電子ゲーム大図鑑』『電子ゲーム決定版大図鑑』『電子ゲーム必勝法 大図鑑』 などが相次いで出版されており、「電子ゲーム」という言葉が非常にメジャーなものであったことをうかがわせる。
次に、「マイコン」のゲームを指す言葉としては、「パソコンゲーム」や「マイコンゲーム」といった言葉が登場している。この二つの言葉の違いは、わかりにくいのだが、appleIIなどのパソコンで遊ばれていた『ウルティマ』『ウィザードリィ』などといったゲームは「パソコンゲーム」として括られるのだが、当時はコモドールの出していた「マックスマシーン」や、ソード電算機の「ゲームパソコン」といった「ゲーム機でもあり、パソコンでもある」というようなハードが多数売り出されていた。これらのゲーム機でもあり、パソコンでもある、という形のハードの多くは、ファミリーコンピュータ以前の家庭用ゲーム機として世界的にも数千万規模の売れ行きをあげており、「パソコンゲーム」がハードの値段からして数十万するため、ややマニアックなファン層を獲得しているのに比べて、マイコンゲーム機は一万円前後からの予算で購入することが可能なため子供向けの手軽に遊べるゲームマシンとして、子供向けおもちゃとして売れていたため、同じ「マイコン」でも両者は区別されることが多い。
ファミコンブーム †
「パソコンゲーム」と「家庭用ゲーム」「マイコンゲーム」の差がより明確になるのが、83年に売り出され、85年〜86年にかけて大ブームとなったファミリーコンピュータの普及である。ファミリーコンピュータ用のゲームは当時コンピューターゲームを扱っていた雑誌の多くでは、パソコンのゲームや、ゲームセンターのゲームと区別するために、「ファミリーコンピュータゲーム」「ファミコンソフト」「ファミコンゲーム」といった形で区別した形で呼ばれていた。特に変わった呼称を設けていたのは、84年末に創刊し、創刊当時はコンピュータゲーム全般を扱う雑誌であった「Beep」誌の呼称で、ファミリーコンピュータなどの家庭用ゲーム機のゲームのことをパソコンゲームと区別して「テレホビーゲーム」などといった呼び方で呼んでいる。
「パソコンゲーム」という言葉は、80年代後半以降も残っていくが、「電子ゲーム」「マイコンゲーム」という言葉は80年代中盤ぐらいでほとんど名称として使われることがなくなり、「テレビゲーム」という言葉にとって変わられていく。「テレホビーゲーム」という独自の呼称を用いていた「Beep」誌においてもそれは同様で、80年代後半にはそのような独自の呼び方をすることもなくなり、「Beep」誌自体が家庭用ゲーム機を中心とした雑誌内容になってゆき、89年には、任天堂のライバル企業であった、セガ・エンタープライズ社の家庭用ゲーム機「メガドライブ」の専門誌となっている。
以上のように「テレビゲーム」という言葉が定着するまでに数々の紆余曲折があり、「ファミリーコンピュタ」の登場によって、いきなり「テレビゲーム」概念が定着していったわけではないことが、わかるだろう。
なお、混乱を避けるため、70年代から80年代中盤にかけての当時のメジャーな呼称を一覧で載せておく。
- 電子ゲーム:携帯ゲーム機であるゲーム&ウォッチを中心として、電動オモチャ、マイコンゲーム機などを含む呼び方。コンピューターゲームというより「電気で動くゲーム」といったものを多く含む。
- マイコンゲーム:マイコンゲーム機(マックスマシーン、カセットビジョン、ぴゅう太、光速船など)を中心とした呼び方。
- テレホビーゲーム:主に雑誌「Beep」誌において使われていた呼称。家庭用ゲーム機のゲームを指す。マイコンゲームは含まない。
- ファミコンゲーム、ファミコンソフト、ファミリーコンピュータゲーム:任天堂のゲーム機ファミリーコンピュータ専用のゲームのこと
- ビデオゲーム:80年代中盤まではコンピューターゲーム全般のことを指していたが、80年代中盤にはゲームセンターのゲームのことを指すようになる。(英語では、「videogame」と言えばコンピューターゲーム全般のことを指す)
- アーケードゲーム:ゲームセンターのゲームのこと。70年代においては業界誌である「ゲームマシン」紙において使用されている程度で、一般のゲーム誌でこの呼び方が使われはじめるのは80年代後半にゲームセンターのゲームの専門誌である「ゲーメスト」誌などで。
- アミューズメントマシン:主に業務用の娯楽用機械全般のことを指す。コンピューターゲームだけではなく、ジュークボックスや、フリッパー、スロット、UFOキャッチャーなども含まれる。
- テレビゲーム:80年代前半までは、コンピュータとモニターを用いるゲームの総称として「ビデオゲーム」と大差ない使われ方がしていたが、80年代中盤のファミコンブーム以降には家庭用ゲームとそれ以外のゲームを区別するような形で使われることが多くなる。
- コンピューターゲーム:コンピューターを用いて動くゲーム全般を指す呼称として使用されている。あまり大きな意味の変遷は見られない。
70年代には、まさしく「テレビゲーム」という名前のついた商品が売り出されているが、これが決定打となったと考えるのは難しい。すでに紹介してきたように数多くの紆余曲折の上で、70年代にワンオブゼムだった「テレビゲーム」という用語が生き残っていった、と捉えた方がよいだろう。
参考(というかほぼまるまる引用) †
アクションゲームで言えば「ジャンプする」「敵を踏む」「投げる」までの一連の動作の「ぽーん、ぽん、ぴ、ぽーん」とかってテンポがある。そういうテンポはマリオはマリオ、ソニックはソニックで独特のものがあり、ある種音楽的なもの。このテンポが不自然だったり、ボタンを押すテンポとして楽しいか楽しくないかということは一つの重要な要素。
またRPGなどにおいて「テンポ」という言い方をした場合、はゲーム展開の速度などのことを指すのが一般的。ロード時間の長さや、カットしたくてもカットできないムービーシーンなどが問題として出てきたところで「テンポが…」という言い方がいろいろとなされるようになってきた。確かにそのようなものも問題だが、難易度の高い作品などではゲーム展開のテンポがやや悪くても「悩むのが楽しいんだよね」ということも少ないないので、あまり問題にはなりにくい。問題なのは特に「ぬるゲー」(=ぬるいゲーム。つまり簡単なゲーム)といわれるような作品においては、ゲームのテンポをいかに制御するかということが死活問題の一つと言ってもよく、たとえば『サクラ大戦』などはそこらへんの制御が圧倒的に上手い。これができてないぬるゲーだと本当にただスカスカと進むだけになってしまう。
「トーン」というのは例えば『ばざーるでゴザール』『ピコ―』『ポリンキー』などのCM、あるいは『だんご三兄弟』などの作者として知られ、『I.Q』などのゲームクリエイターでもある佐藤雅彦氏の大切にしている概念で、「世界観」と言ってもいい。佐藤氏の作品を挙げれば「ああ、なるほど」という感じだとは思うが、「例えば映画とか小説とかを何回も読み直すという行為はストーリーを知りたいとかそういうものではなくて、その「世界観」を味わいたい、その世界に何度もひたりたいから、何回も読みなおすんじゃないか。その映画なり小説は何度も繰り返されるだけの力があるのではないか、と思ったんですね」と佐藤氏の言葉。佐藤氏はその他、メディアの転用によってトーンは変えなければいけないだとか、独特な世界を持つキャラクターは独特の音を持つだとか、日記のトーンが持っている力だとか、色々と面白い議論をしている。
イメージ管理
ハレ ケ(日常)に対するハレ(非日常)。
「真面目」「俗」「仕事」などの日常から離れた対立概念として、「不真面目」「遊び」「祝祭」「聖なるもの」などの非日常の枠がある、とかなんとかそういう議論で、ロジェ=カイヨワなんかはこういう議論の文脈の中で遊び研究をはじめた人。
ホイジンガは「遊び」と「聖なるもの」を同じく非日常のフィールドとして同じようにくくっているが、カイヨワは「遊び」と「聖なるもの」は違う、とホイジンガを批判している。
しかし、遊びは非日常なんだろうか?日常と文法を共有するものではないけれど、がっちりと日常生活には食い込んでいるもののように思うのだけれども。
プレイスタイルの一つとして、マルチシナリオやフリーシナリオとよばれる物語システムを持った作品で、「ここでこれをやったらどうなるわけ?」だとか「ここで仮にこの人と一緒に行ったらどんなエンディングになるんだろう」とか、そういうような形でパターンを収集する、というプレイをすること。
このプレイスタイルはやりこみプレイヤーに限ったことではなく、特にサウンドノベルのゲームなどは、はじめからこういったパターンを収集されることを前提にしたものとしてデザインされている。
伊藤悠さんの用語で言えば「読み尽くし型のゲーム」
パフォーマティブ/コンスタティブ、という区分は発話行為論で知られる20世紀イギリスの哲学者、ジョン・ラングショー・オースティン(John Langshaw Austin)によるもの。パフォーマティブとは行為遂行的な発話のことであり、コンスタティブとは事実確認的発話のことである。
コンスタティブな発話とは、何かしらの事実/事態についての発話であり、真か偽かを判断することが可能なものである。たとえば「私の生物学的性は男である」という発言は、話者である「私」というものの指示の対象が確定できる限りは、その発言の真偽を確認することが可能だ。オカマタレントである前田健がこの発言をしたのならばこれは真であり、和田アキ子がこの発言をしたならばそれは偽である。
一方、パフォーマティブな発話とは、その発話事態が状況を変化させる言葉であり、真偽による判定はできない。たとえば「おじいちゃん、ジュース買って!」という子供のおねだりは、この発話事態の真偽を確認することはできない。
ただし、「私の生物学的性は男である」というコンスタティブな発話が、パフォーマティブな側面を持たないわけではない。あらゆる文脈から断ち切られて発話がなされる、ということは現実の状況では考えにくい。前田健や、和田アキ子が「私の生物学的性は男である」という言葉を発したら、その言葉の真偽を機械的に判断することで終わるのではなく、話者がその発言をすることに一体どういう意図をこめたのか、ということを考えてしまうだろう。そして、その発言の聞き手は、発言に対して何かしらの態度決定を行うはずである。たとえば「和田アキ子も、ついに自分が男であることを認めたか(笑)」とか、「前田健は、女になりたいってことを暗に言っているわけ?」とかといった反応を示すはずである。
「批評」という行為はしばしば、コンスタティブな行為だと了解されることが多い。
だが、批評や学問といった営みの中で行われる記述や発言も、一般的な発話行為と同じく、パフォーマティブな側面を持つ。
たとえば、「映画とは何か」という問題を考え抜き、非常に説得的で専門的な議論を積み重ね、100人ぐらいの専門家に読まれるような議論をする。これはきわめてコンスタティブな評価をめざした発想である。
一方で、「映画とは××だ」と半ば暴力的に言い放つことによって、広く論争を呼び、その論争自体に感化された映画の制作者たちによって「映画」の定義を揺るがすような作品を作られたとする。その場合、「映画とは××だ」という発話は、その真偽や妥当性はともかくとして、言及の対象となる「映画」のあり方自体を変化させている。一見、真偽についてのコンスタティブな発話をしているように見せかけつつ、その実パフォーマティブな役割を果たしているのである。この時こうした発言は、パフォーマティブな価値を持っているといえよう。
この二つの違いに自覚的でなく、かつ異なる立場の者が話をするとケンカになることが多い。コンスタティブな議論の価値を信じる者は、ひたすらパフォーマティブな――ある場合にはしばしば暴力的な――議論を繰り返す者に対して「いいかげんなことばっかり言いやがって!このバカ!」と批判する。一方、パフォーマティブな振る舞いの価値を信じる者は、ひたすらコンスタティブな議論を目指す者に対して「部屋にこもって議論してたって、何も変わりやしないだろ!てめえが、議論してる間に、議論の対象自体が変わるんだよ、バカ!」と批判する。
メディア露出の多い批評家は、批評の持つパフォーマティブな役割に対して非常に自覚的にふるまっていることが多い。いや、批評がパフォーマティブなものであることを意識しているからこそ、彼らはマスメディアの中で積極的に発言を行うのである。
→観察?
→語りの非対称性?
→システム論?
→コミュニケーション?
フロー体験 心理学者、ミハイ・チクセントミハイが『楽しみの社会学』『フロー体験〜喜びの現象学〜』などで使っている言葉で、遊びに熱中して昂奮して、楽しんでいるような状態のことをさす。
一つには最適経験のことであり、一つには目的志向的な行動を行っている状況のことである。哲学者バトランド・ラッセルの「私は徐々に自分自身や自分の欠点に無関心になった。私はしだいに注意を世界の状態、さまざまな分野の知識、愛着を感じる人々など、外部の対象におくようになった」という言葉にだいたい集約されている(らしい)
ゲームの遊び方のこと。
「プレイヤー」という重要な要素を捉えるための用語の一つ。プレイスタイルが違うと同じゲームでも感じ方が違ってくることが少なくない。攻略本を読みながらやったのとやらないのとではまた違うし、一日一時間のペースでやっているのと、一日八時間のペースでやっているのとでもまた違う。
芸術の解釈学的な議論では、プレイヤーの属する解釈の共同体のようなことが一つの問題とされるが、プレイスタイルの違いは単なる解釈共同体のような問題にとどまらない。ガーダマー的な「読者」論的な解釈の話というよりも、シャルチエ的な「読書」論的な社会史みたいな話ができるだろう、できたらいいな、と思われる。
この方向性で注目すべき変数といえばたとえば、1.リビングルームにおける「ファミリーコンピュータ」とそれに対する個室化*18、2.連続プレイ時間の長時間化/短時間化、3.ルール・ブレイキングの程度とか、4.やりこみとか。
だろうか。
ビデオゲームのメディアとしての特殊性を考えたとき、そのあり方にとって決定的に、他のメディアと異なってくるのは「プレイヤー」というものの存在である。演劇の比喩を用いて説明すれば、この「プレイヤー」は、演劇にとっての「観客」であると同時に、「役者」や「演出家」でもありうる存在であると言える。もっとも、この比喩は全てのビデオゲームについてあてはまるわけではないが、少なくとも、小説や映画における、「読者」や「観客」とは比べるとかなり特殊な存在だと言っていい。そのため、ここにおいて成立してくる「批評」のあり方も、小説や映画のそれとは全く別の水準のものが成立することになる。
関連 †
P-PC-NPCモデル
ゲームにおける「物語」の作られ方というのは、ゲームの内部ではじめから用意されたものを味わうという側面が存在すると同時に、ここのプレイヤーによって物語が独自に紡ぎだされていくという側面がある。
プレイヤーがコントローラーで指示を出して動かすキャラクターのこと。だいたいの場合は主人公がプレイヤーキャラだということになるのだが、かならずしも常にそうであるとは限らない。例えば、主人公のみならず主人公のパーティキャラ全員を指揮したり、全軍を指揮したり(「指揮する」というより遠隔操作といった感じ方が正しいが)場合は「プレイヤーキャラ」=「主人公」ということにはならない。この問題に気を使ったためか、戦闘で主人公キャラ以外はオート戦闘というシステムをとっている作品もある。
主人公身体ののっとり分身としての身体?
ヨハン・ホイジンガ『ホモ・ルーデンス』は遊び論の古典
ホンジンガは遊びを次のように定義している
1.自由
2.実生活外の虚構
3.没利害
4.時間的・空間的に分離
5.特定のルールの支配
(ホイジンガ『ホモ・ルーデンス』)
ホイジンガは、民族学的、人類学的アプローチを十全に使って、世界各地の遊び文化を論じた。
カイヨワの議論は、ホイジンガの議論を先行研究としてよく参照している。
「ゲームは音楽メディアのもっている表現手段を用いることもできるし、映画メディアの持っている表現手段も用いることができ、そうした複数のメディア表現を組み合わせて自在に行うことができるのが、すばらしい。」
というような議論が、90年代中盤ぐらいまでの間、InterCommunication?や、Hotwiredなどで議論されていた。議論の妥当性はともかくとして、いまや「マルチメディア」という言葉はバブリーに使われすぎた結果、クチに出すのが恥ずかしい言葉となっている。あと10年ぐらいすると、またもう一回転して普通に使えると思うのだが。
まあ、それはさておき、ゲームが複合的な表現メディアであるということは間違いない。
ゲームにおいて一つの目的を強制することは「自由度」を奪うという批判をあびることもあるが、ある一つの目的を間違いなくこなしていく、ということに達成感や、スパイのような緊張感を感じることもある。あらかじめ何かを成し遂げることを強制されることによって「しくじれない」というスリルに満ちた感覚がうまれうるのではないだろうか。
模擬(ミミクリ) カイヨワの遊びの四分類の中の一つ。子供の物真似、空想の遊び、人形、おもちゃの武具、仮面、仮装服、演劇、見世物全般など。(『遊びと人間』)
ボールドウィン、クラーク[2002]によれば「それぞれ独立して設計でき、しかも全体としては統一的に機能するサブシステムを用いて、複雑な製品やプロセスを構築すること」とされている。経営・経済学分野で、脚光を浴びている概念。
たとえば、インターフェースが公開され、固定されており世界中どこでも部品を作れるようなパソコンのような製品は、高度にモジュール化された製品であると言える。対して、全体がひとつになっており、部分に分けにくいような、アナログ時計(?)などは統合型の製品であると位置づけられる。
モジュール化によって生じる利益として次のような議論がある。
- 仮説1:他の部品の開発状況などとのすりあわせを、気にせずに開発できるようになるため、個々のモジュール(部品)の技術革新が行いやすくなる。例えば、CPU技術者はCPUの速度上昇だけに専念し、HDDの技術者は、HDDの容量増加に専念できるようになるため、技術革新の速度が上昇していくという議論。クオリティのレベル上昇がブーストされる。(技術革新促進説)
- 仮説2:部品ごとのバリエーションが増えることにより、製品の形のバリエーションも飛躍的に増加する。例えば、スターバックス・コーヒーでは、小さな店舗であるにも拘わらず、2万通り近い組み合わせのメニューを出すことが可能になっている。選択肢/自由度の増加がもたらされるとする説。(財の多様性増加説)
- 仮説3:モジュール化/標準化の進展により、外部からの調達コストが低下する。これにより、世界中から、最良の部品を調達可能になる。例えばDellコンピュータの部品の調達は、モジュール化の議論抜きに語ることができない。(取引費用説)
- 仮説4:大量生産によるコストの低下。特にソフトウェア分野で顕著に生じる。(収穫逓増説)
近年までの情報通信産業などでは、モジュール型製品は特に強いとされている。一方、日本の自動車産業などでは、モジュール化戦略とは逆向きの「すりあわせ」の調整が強いとされている。
では、ゲーム産業におけるモジュール化とはどのようなものだろうか。
ごくごく大まかにまとめると、3つの段階に整理できるだろう。
第一期:ハードとソフトの分離/統合 †
古典的なゲームのモジュール化/統合型の議論は、ゲームのソフト(ルール)と、ハード(遊具)の問題からはじめることができる。
以下、Classic 8-bit/16-bit Topics「ゲームのなかのモダニズム」*19のhally氏は次のようにまとめている。
近代まで職業的なゲームデザイナが存在しえなかった理由はごく単純で、ゲームを個人作品化する手だてがなかったからに他なりません。伝統的なゲーム遊具は、中世後期までにある種の汎用ゲームシステム化を遂げていました。チェス盤、バックギャモン盤、トランプ……といった定型遊具は、このころ多種のゲームに使用されることが珍しくなくなっており、新しいゲームの考案にあたって専用遊具が考案されるようなことは、滅多になくなっていたのです。つまりソフトウェア (ルール) のデザインがハードウェア (遊具) のデザインから遊離していたわけです。このソフトウェアはもちろん誰にでも手軽にコピーし改変できるものでした。
こうした汎用化の流れから多少なりとも外れていたのは、ルネサンス後期にイタリアにもたらされた「鵞鳥のゲーム」と呼ばれる絵双六くらいでしょう。絵双六は描き出される内容によってゲームのストーリラインが変化するわけですから、その意味でハードとソフトが不可分なものであるといえます。
第二期:コンピュータ・ゲームの誕生 †
柳川範之[2002]によれば、「ゲーム産業は全体として一つの『モジュール化』されたシステムとして見ることができる」という。ここで柳川が指しているのは、具体的には任天堂やソニーのようなハードメーカーと、ナムコやスクウェアエニックスのようなソフトメーカーが独立して開発を行える状況のことである。*20
「ハードの仕様の固定化によって、ハードメーカーとソフトメーカーのあいだで、細かい情報やアイディアの交換を行う必要性が大幅に低減し、ソフトメーカーの自由度を高めることが可能になった。」という。
第三期:開発過程の標準化 †
1990年代後半からゲーム産業に生じている第三の事態として位置づけられるのが、ゲーム開発エンジン(エディタ)産業の発達である。
Quake3エンジン、Half-lifeエンジンなど、ゲーム開発のためのミドルウェア/エディタが北米を中心に高度な発達を遂げたことで、ゲーム開発の規模の効率化が図られると同時に、これを利用した開発の水平分業化が進展していると言われている。北米の水平分業化のパワーが大きな力を持ち、ゲーム開発過程のモジュール化を高く評価する議論も多い。
一方、この数年は、Nintendo DSの大ヒットなどに象徴されるように、小規模な垂直統合型の開発モデルへの評価も高まっており、ゲーム産業においては、必ずしもモジュール化一辺倒という形の議論にはなっていない。
ゲーム産業の国際分業の可能性 †
また、ゲーム開発過程におけるモジュール化は、ゲーム開発の国際分業においても大きな問題となる。中国、韓国、インドなどの企業と連携した、ゲームの国際分業は現在急速な勢いですすめられている。だが、中村彰憲によればキャラクターやシナリオなど高度にその文化ごとのコンクストに依存するような要素の分業化は難しく、サービス産業の「フラット化」(トマス・フリードマン)は、コンテンツ産業においてどこまで可能なのか、今後の状況が注目される。
参考文献/関連文献 †
- キム・クラーク,カーリス・ボールドウィン / 安藤 晴彦訳 『デザイン・ルール―モジュール化パワー』東洋経済新報社 2004
- 青木昌彦,安藤晴彦[編著] 『モジュール化―新しい産業アーキテクチャの本質』2002 東洋経済新報社
- カーリス・Y・ボールドウィン、キム・B・クラーク 第二章「モジュール化時代の経営」
- 柳川範之 第五章「ゲーム産業はいかにして成功したか――アーキテクチャ競争の役割」
- 藤本 隆宏 『能力構築競争-日本の自動車産業はなぜ強いのか』中公新書 2003
かつて、絵画も文学も映画も、リアリズム表現を強烈に目指していた時期があった。
そして、ビデオゲームの映像におけるリアリズムの表現は、コンピューターの発達と足並みをそろえて、この20年ぐらいの間に高速な進化を遂げた。その中で、「リアルな映像」という言葉は、技術的にワンランク上のものが出てくるたびに、ゲームファンならば何度も聞いたフレーズだろうし、それに胸を躍らせる反面、単なる「リアルな映像」に飽き飽きとした感覚を抱き、映像のリアリズムについて言えば、「もはやこれ以上、リアルな映像表現にこだわることに意味がない」という発言すら飛び出すようになってきた。
特殊現実、シミュラークル
光の速度では遅すぎる †
ネットワークを介した「リアルタイム」ゲームでは、処理速度の限界がしばしば問題となる。
光の速度は、一秒間に地球を7週半するわけだが、それはつまり、地球の裏側同士で、対戦ゲームをやろうとしたばあい、7.5fpsの動画が限界ということにだ。だが、ゲームセンターでの格闘ゲームで標準的に求められるfps(Frame Per Second)は、60fpsが通常である。コンマ0.01秒を競うレースゲームでは、60fpsでも十分ではないと言われている。こうしたことから、ネットワークゲームが真にゲームに必要な速度を出すためには光の速度では遅すぎるということがよく言われる。
この速度の限界があるため、現実にアメリカのFPS(First Person Shooter)のゲームなどでは、西海岸と東海岸で戦うときにはサーバーがどこにあるかによってハンデを付けながら戦ったり、西海岸は西海岸で、東海岸は東海岸でコミュニティが形成されるというような状態を作っている。
遅延レイテンシ? †
→リアル・タイム・マシーン展行ってきました。 を参照。
『スーパーマリオブラザーズ』における時間とは、画面右上のタイマーによって象徴される。時間とはゲームオーバーまでの距離である。マリオにおける時間感覚は、常に時限爆弾のすぐ手前で爆弾解体を行う、爆弾処理班と同類のものである。ここでは、規定の時間までにいかに効率的に作業をなしとげるのかということがもっとも重要に意識されることとなる。規定の時間までに爆弾を解体しなければ――その面をクリアしなければ――、爆弾は爆発し、ゲームオーバーが待っている。時間が少なくなればなるほど、緊張感はまし、作業をおこなうものはせっつかれることとなる。マリオで100秒を切ったときの音楽を思い出して欲しい。クリアすることと無縁な行為は、「無駄な行為」であり、時間に余裕のあるときならば可能だが、時間に余裕のないときは一切の無駄な行為は省かれていくことなる。
『ICO』における時間はマリオと同じく「リアルタイム」である。ターン性や、行動順によって行為をするわけではない。だが、ICOにおけるそれは一般のアクションゲームのそれとは大きく違う。常に何かをしなければならないわけではなく、常に高速な反応を迫られるわけではなく「何もしないこと」が選択可能だ。何かを急かさないからこそ、その静謐さは、もっとも生々しい姿でわれわれのまえにたち現れる。また、もう一つ重要なのは、微妙な時間的な「ズレ」が配置されているということだ。 少年が少女を呼ぶ「オファ、オファ」という声をあげてから、少女が反応し、かけつけてくるまでの時間の落差がある。少年が少女の手をひくとき、少女の体がひっぱられるときの微妙なズレ。ICOでは、体の動きのリアルさ、というレスポンスの良さを確保しつつも、一方では匠にこのようなズレを象嵌していく。このようなレスポンスの悪さ、すなわち不自由を配置することによってICOの時間はマリオ的な時間とは全く別のものとして立ち現れることとなる。
ここでたちあらわれる「リアルタイム」の「リアル」は技術的には同様のものでありながら、まったく別の方向を向いている。ここでは、前者を賑やかな時間、後者を静謐な時間と、名付けてみたい。
静謐な時間は、ゲームの時間が普段あまりにも賑やかだからこそ、突如として訪れるその時間のあり方に驚く。静謐な時間は、退屈な時間ではない。退屈な時間は、やることがなくて暇をもてますわけだが、そのような状態ではない。環境がプレイヤーに何も急かしてこないだけであって、やることがない、ということとは異なる。
また、賑やかな時間は、喧噪ではない。あれもやれ、これもやれ、ということにあたふたして、処理能力をオーバーするような時間では(必ずしも)ない。ある特定の時間のセットを与えられて、その時間内になにかしらを処理することがはっきりと見えている状態だろう。
ルールとは何か。
ゲームにとってのルール †
ゲームがゲームとして成立するために必須の要素だと考えられている
→目的、規則を持った活動
Stephen Sniderman[1999]*21やLinda Hughes[1983]*22によれば、ルールを完全に記述することは不可能であり、記述の不可能なルールのありようこそが、ゲームを成立させるミクロな場所では重要な役割を果たしている、という。
→記述可能性、ルール・ブレイキング
ルールを課す、ということは「不自由」を課すということなのだろうか。ある意味それはそうなのだが、そもそも「自由」とは何か、という話から考えていく必要ある。
→自由、不自由、二重創作性、言語ゲーム、拡大ルール、制限ルール
社会学などではルールを次のような形で分けたりする。
〈1〉慣行(usage)→ウェーバー「慣例」:集団内での画一的な行動様式で、強制力はない。乾杯など
〈2〉フォークウェイズ(folkways)→ウェーバー「慣習」:伝統的な社会的慣行で、サンクションはない。お祈りなど
〈3〉モーレス(mores):サンクションのあるフォークウェイズ。村八分など
〈4〉習性(trait):社会的・個人的な行動様式の体系。なんば歩きなど
〈5〉習慣(habit):型が固定化された行動。朝散歩をするなど
〈6〉法(law):社会規範を遵守するために強制するもの。刑法
〈7〉自然法則(natural laws):自然科学的な観察によって導き出された法則性。重力など
参考 †
ジャンルの成立と変遷 †
1988年ごろの「Beep」誌に『ゼビウス』を「レトロゲーム」として記述しているのを見かけたのが最初の記述である。『ゼビウス』は1988年から数えたら5年前にゲームセンターにはじめて登場したゲームだが、たった5年で、「レトロ」という表現が使われるようになる、というのは興味深い。「レトロゲーム」という概念が本格的に脚光をあびはじめるのは、90年代後半以降であるが、そのときはファミリーコンピュータ用ゲームが、「レトロゲーム」といわれはじめることになる。これも、実際には7、8年程度しか経過していないが。
バイヤーズガイド、予算配分、給与策定などの現実的な意志決定を効率化させるための制度として、評価という行為は現代ではしばしばシステム化される。これは、批評行為と地続きではある。だが、文芸批評的な意味での批評が、批評対象となるものに対する「理解」を目指して行われるとすれば、レビューシステムは現実の「意志決定」を目的として行われる。そのような形で成立している制度化は、批評とは多くの点で別種の妥当性や、価値を持つものとして捉えたほうがよい。
有名なレビューシステムとしては、kakaku.com(http://kakaku.com)や、Amazon(http://www.amazon.co.jp)などが挙げられるが、この二つのサイトはレビューシステムを抱えていると同時に、インターネット上でも最大級のインターネット販売サイトである。つまり、レビューシステムは販売促進用のシステムとして作られている。
このことからもわかるように、レビューシステムがもたらす情報はその公正さや妥当性においてはともかく、効率的・迅速な意志決定のための補助的な役割が期待されて成り立つものだと言えるだろう。
だが、利用者の効率的意志決定のために作られたシステムであるとはいえ、レビューシステムがレビューとしての最低限度の妥当性を持つことが保証されていなければ、誰も利用しない。では、レビューシステムが保証する妥当性とは何か。
ほとんどの場合、レビューシステムが提供する妥当性とは「簡易な統計調査」としての妥当性である。つまり、複数人のレビューを点数やタグ付けなどによって、統計処理可能な量的データ/質的データとして蓄積していき、作品ごとに対して平均/最大値/最小値/中央値などを算出する。そして、作品ごとに平均点を比較したり、ランク付けなどをすることにより、たった一人の人間による主観的なデータよりも、信頼性の高いデータを得られる、というものである。
たとえば、私のよく使う映画レビューサイトCinemaScape?(cinema.intercritique.com/)は個人運営のサイトとしてはきわめて高度なデータ処理を数多く行っている。
量的データの処理だけでなく質的データの処理にも工夫が凝らされている。評判の良いレビューの文章を上位にソートする機能や、作品ごとのクラスター分析などによってレビュアーや作品の傾向分析がなされる。それによって特定の作品の類似作品や、ある特定のクラスターの人々の間で評判のよいものを見つけ出してくることも可能である。使い方に慣れるとかなり便利だ。
また、もっと一般的なところでは、amazonの平均点やamazonの「おすすめ」などはよく知られているだろう。
ただし、レビューシステムがあくまで「簡易な統計調査」であることを忘れてはならない。まず、どんなレビューシステムであっても、その設計・運営者・利用者が統計調査に関する基本的を知らければ、そもそもシステムの持つ役割を誤解してしまうだろう。
仮にシステムの設計者が統計やデータマイニングに関わる知識を豊富にもっていたとしても統計的にきちんとした前提を踏まえた上での調査結果をアウトプットとして出すことはしばしば困難である。
最も典型的な問題は、こうしたオンライン上に自由に解放されたシステムでは、サンプリングをきちんと行うことができないため、「書きたい・点数付けした人による意見」に全体に偏りがちになり書きたい・点数付けしたいと思わなかった人の意見がどうなっているかがわからなくなる。ということである。
また、調査の設計の仕方によっては他にも様々な問題が生じることがある。
Amazonのシステムの抱える問題 †
たとえば、Amazon(http://amazon.co.jp)では、レビュアーの書いたレビューをレビューごとの単位ではなく、レビュアーごとの単位でランク付けをしている。これは、レビュアーにレビューを書かせるための動機付けのシステムとしてはよく考えられたものだが、レビュアーがこのランキングを効率的に上昇しようと思うと、マジョリティに迎合するのが最も効率のよい戦略だということに気づく。そのため、Amazonのシステムは全体としては議論の保守化、沈黙の螺旋?化を招きやすい制度設計になってしまっているといえる。(→ケインズの美人投票?)
Playstation mk2のシステムの抱える問題 †
家庭用ゲーム機のレビューシステムとして有名なPlaystation mk2(http://psmk2.net/)ではどうか。
このサイトの工夫の一つとしては、評価項目の分類を「オリジナリティー」「グラフィックス」「音楽」「熱中度」「満足感」「快適さ」などといった形で細かく分類し、項目ごとの点数評価をすることが挙げられる。こうした項目評価を細分化することによって、ソフトごとの特性を表現するような結果を出すことに貢献する工夫である。
だが、こうした工夫は一方では平均的にソツなくできたソフトが最もよいソフトだという評価を生み出してしまう。たとえば、オリジナリティーと快適さが飛び抜けてすばらしくプレイヤーとしては大満足のソフトと、全体的はソツなくよくできているためほどほどに満足したが今ひとつこれといって惹かれる部分のないソフトを比べた場合に、前者よりも後者が高い評価を受けてしまう場合が多い。
表にすると次のようになる。
| 一点豪華主義の傑作 | ソツなくできた秀作 |
| 平均点 | 71.5点 | 80点 |
| 総合評価 | 99点 | 80点 |
| 音楽 | 40点 | 80点 |
| 快適さ | 70点 | 80点 |
| グラフィックス | 40点 | 80点 |
| 熱中度 | 90点 | 80点 |
| オリジナリティー | 90点 | 80点 |
オリジナリティや熱中度は高いが、音楽やグラフィックスがヘボい一点豪華主義の傑作のようなソフトと、全体にソツなくできているだけの秀作というようなソフトを比べた場合、総合評価では一点豪華主義の傑作が優れているということになるが、項目ごとの平均点で評価すると、ソツなくよくできた秀作のほうが優れているということになってしまう。
こうしたソツなくよくできた秀作を生み出す力は、言うまでもなく大手メーカーのような開発の体力のあるところが得意とする仕事であり、「年間一位」の作品などを見ると、大手メーカーへの偏りが多くなる傾向にある。
ファミ通のクロスレビュー †
日本のゲーム業界において最も、大きな威力を誇ったレビューシステムである。
当初は、簡便な統計調査的として機能していたが、権威としての役割を読者―編集者が相互的に認識していったことにより、近年ではファミ通の売り上げ自体もさることながら、ファミ通クロスレビュー自体の重み自体もゆっくりとだが低下しつつある。
critique of games内のファミ通クロスレビュー関連記事 †
- playstation mk2
- ErogameScape?
プレイヤーの意識とゲームの主人公の意識というのが一致しない場合、プレイヤーはゲームに対して冷めているという状況があり、プレイヤーの意識とゲームの主人公の意識が一致する場合、プレイヤーはゲームにのめりこみやすい(もちろん、一概にそうだと言えるものではないが)。そのようなプレイヤーの意識とゲームの主人公の意識という二つの「意識の距離」をどのように作り出していくことができるか、というのはたとえば、ファイナルファンタジーとドラゴンクエストの対立、としてしばしば語られてきた。
そして、ドラゴンクエスト支持者の典型的な言説は以下のようなものである。
- 1.ゲームでは、プレイヤーがゲームの世界に没入したほうが楽しい。
- 2.ゲームの世界に没入していく上で、その回路/インターフェイスとして機能するのは、主人公(プレイヤーキャラクタ)であり、プレイヤーキャラクタとプレイヤの間に意識の乖離があると、ゲーム内世界への没入が難しい
- 3.よって、プレイヤとプレイヤキャラクタの意識に乖離が生じないように、プレイヤを無口にしているドラゴンクエストはすばらしい。
という論法である。
だが、これに対する反論もありうる。
ドラゴンクエストに対するファイナルファンタジーという立ち位置からそれを見出すとすれば、「あえて」プレイヤとプレイヤキャラクタの間に意識の二重性を成立させるということを前提として提示しておいた上で、その二重性を物語の小道具として使用してゆく手法を展開してゆくのがプレイヤ/プレイヤキャラクタの間の意識の二重性のもう一つの展開のさせ方であろう。*23
この意識の二重性に着目した形での議論は少なくない。
東浩紀は『Ever17』を例に出しつつ、ゲームプレイヤがゲーム内世界のNPC(=ギャルゲーというジャンルにおける目的報酬として機能する「少女」たち)と出会うための小道具としてこの二重性が機能していることを論じる。『Ever17』においても、『エースコンバット04』と同様にプレイの中盤までにおいてはプレイヤとプレイヤキャラクタの関係性は極めて曖昧に描かれる。ここでは物語の終盤まではプレイヤがプレイヤキャラクタが一人だと信じていたものが、実はプレイヤが信じていたような形態とは異なり、実は二人の異なる人間であったことが明かされる。そこで、この二人のプレイヤキャラクタを同一のものとして処理していた「メタ意識」の存在がゲーム内世界のNPCによって見出され、とうとうと語られることになる。この「メタ意識」とは言うまでもなくプレイヤの意識である。通常モニターの中のゲーム内世界と外の世界とがほぼ完全に分離していることを前提としているゲームプレイヤは、この「メタ意識」がゲーム内世界の人間に見出されることによってはじめてゲーム内世界に入りこむための経路を与えられるのである。
プレイヤをゲーム内世界に呼び込むための方法論としてこうした「意識の二重性」が使われるゲームをほかに挙げるとすれば、『MOON』や『ベイグラントストーリー』といった作品も重要な位置を占めるだろう。
ベンヤミン『複製技術時代における芸術作品』で議論された言葉として有名。ベンヤミンは複製技術時代の到来によって、一回性、アウラが失われたということを論じた。
一回性とは何か。
現実において全く同じことが何度も繰り返される、ということはなく全てのものごとは一回一回限りのオリジナルなことであり、何度も繰り返されているのように思われるようなものというのは実はコピー(まがいもの)である。たった一度の行為であるからこそ、そこには緊張感が伴い、その時々にどのような行動を選び取るか、ということが緊張感を持って体験される。このような緊張感をもった体験が一回性である、と理解しておこう。
だが、ゲームにおいてはあらかじめ決められている予定調和のできごとや、一回の体験をやり直したりすることが可能である(もちろん、100%同じ体験が存在するわけではないが)。コンピュータ・ゲームをはじめてプレイし、はじめての強敵と対峙するとき、われわれはそこではじめて与えられたその経験に対してしばしば驚喜する。だが、その体験を二度、三度と繰り返すうちにはじめに存在していた「強敵との対峙」は単なるボタンを押すという単純行為の次元へと堕ちてゆく。
ここでは、物体・作品の「複製」ならざる、作品に対峙するプレイヤーの体験の「複製」が行われているといってもよい。
こうした体験の複数性に対して、ネガティブな言説を探すとすれば「ゲームにおける体験はリアルで一回性のある体験ではない」という議論が一方では可能であるが、逆にこうした緊張感がある程度失われた状態こそがゲームの一般的なあり方だ、としてその状態をうけいれるという発想もある。
この緊張感の失われた事態そのものを前提としつつ、そのような状態の中でも強烈な一回性が立ち上がる経験を書いたものが桜坂洋『ALL YOU NEED IS KILL』(2004,集英社)だろう。『ALL YOU NEED IS KILL』の中で主人公は、ゲームでいえば『ガンパレードマーチ』や『クロスチャンネル』『Ever17』といった作品のように同じ世界を何度も連続して体験してゆく。この体験の一回一回は、二度と繰り返されない固有のものであるが、これを20回、30回と繰り返すうちに世界は色を失い、ルーチンワークのように生きることを主人公は覚え始めてゆく。だが、あるときにそのルーチンワークとして提示された世界に決定的な楔が打ち込まれる。そしてルーチンワーク化し、ループする時間の中からの脱出をはかるその瞬間にこそ、強烈な一回性が喚起されることになる。そのただ一度の瞬間にいたるまでの世界の陰鬱さ、無限の同一性が強烈であるからこそ、その一瞬の一回性は強烈な輝きをもって描かれるのである。
カイヨワの言葉を使えば「アレア」。カイヨワは、サイコロや、宝くじといった遊びを「運」に類する遊びとして分類している。
また、この概念は「偶然性」だけでなく、多様性、計算不可能性といった概念とも関わる。
動機付けの議論から言えば、完全に運が左右していることが明らかな状況下では、プレイヤーが結果に関わることが可能だという期待*24が働かず、(学習的)無力感が引き起こされることになる。
完全に「運」が左右する状況では、プレイヤーはやる気をなくしてしまう。だがその一方で、「運」によってもたらされる状況の不安定さは、ゲーム展開の多様性や、計算不可能性を確保することに寄与する。
たとえば、まったく「運」がない競争では、「能力」「努力」といったプレイヤーの属性が重要となり、「努力して強くなったプレイヤー」が常に勝ち続けることになる。だが、一定の度合いで状況に不安定さがもたらされる環境下においては必ずしも「努力して強くなったプレイヤー」ではないプレイヤーにも勝利する機会が与えられることになる。
「運」とはこのように、それ単体では楽しみとなるかどうか危ういものだが、「安定した状況」を崩したり、状況を動かすという性質が認められるときには、全てのプレイヤーにとって等しく勝利を与える可能性をもたらすきっかけとなる。状況をリセットする可能性は、万人に開かれた平等性――すなわち、ゲームへの参加意欲を担保するもの――
となる。
映画とゲームの関係には微妙なものがある。一方では憬れやコンプレックスがあり、一方ではその差異を主張するための例としても頻繁に持ち出されてきた
→映画的
90年代中盤までは、「映画に負けないゲームをつくること」が、ゲームマシンの描画性能を向上させていく大きな動機として機能していた。
だが、90年代中盤にプリレンダリングのムービーシーン(カットシーン)などを多用した97年『ファイナルファンタジーVII』,99年『ファイナルファンタジーVIII』のようなゲームが発売されるにつれて、「映画的なゲーム」という言葉は、一方ではけなし言葉としての機能も持ち始めることになる。
ゲームを語る文脈で「映画的」という場合、TVと映画とか、小説と映画とかといった話ではなく、単に「キレイな映像」という意味である場合が多かった。では「キレイでない映像」とは何のことかというと、ファミコンのドット絵のようなもののことである。
98年に、『メタルギアソリッド』が大ヒットを遂げると、小島秀夫の作品に対して褒め言葉として「映画的」という言葉が用いられることが多くなる。ここでの「映画的」というのは、一つには映像の美しさについてであるが、もう一つにはハリウッド的なシナリオだ、という意味が込められている。なので、ゴダールなどの「映画性」の話などはいまのところ言及はほとんどない。
鈴木香織は、ゲームの文脈で「映画的」という言葉が褒め言葉として機能する場合と、けなし言葉として機能する場合の作品には違いがある、と言っている。
それは映像がキレイかどうかとか、カットシーンでのアングルの作り方などが映画の技法をふまえているかどうか、といった点とはそれほど強く関係しない。問題は、美麗な映像が与えられたときに、プレイヤーがその映像に対して操作権限をもっているか、どうか、というような点に集約されるという。たとえば、『ゼルダの伝説 時のオカリナ』(1998)などは、そういった点に配慮したため、「映画的」という言葉がほぼ賛辞であった。
errand boy syndromeを見よ。
問題の構造 †
解釈の多様性の問題は、美学・文学理論における古典的な問題の一つである。
書いておくべき基本的な事項はいろいろとあるが、疲れそうなので当分外部リンクをとばしておくことにします。
- →Wikipedia 解釈学
- →Wikipedia 意味論
ゲームの特殊性 †
ものごとの解釈が多様であるのは当然のことだが、ゲームにおける物語は、プレイヤーという製作者でもあると同時に解釈者でもある存在が解釈をする、という点で、旧来のメディアとは多少異なる。
制限や禁止をともなったルールではなく、ボーナスルールなど。ぷよぷよの「連鎖」や「コンボ」。あるいは、もっと古典的なところで言えば、「コインを100枚とったので予備が1機増える」とか。
映画『MATRIX』で「イメージすれば身体は無限の可能性を見せていく」というような発想があったが、そういったものを想起してもらえればいい。拡大ルールは、「ルール」が現実ではありえない形で展開する面白さという話だが、こっちは、インターフェイスや身体が、巨大化したり、飛んだり、跳ねたり、高速移動したり、スローモーションになったり、というような、インターフェイスが拡張される面白さ。
カイヨワの遊びの定義の中の一つ。「あらかじめ決められた明確な空間の時間の範囲内に制限されていること」(『遊びと人間』)
ゲームの定義はいろいろとあるが、一つには「プレイヤーのゲームの中の世界で最適化された行動を調整/学習していく過程である」とする人もいる。
この説明はゲームプレイヤーの中で生じている事態を捉えるためのものとしては、非常に的を得た説明の一つである。
アフォーダンスの概念とも近い。
RPGやアドベンチャーゲームの楽しさを規定する要因としてしばしばひきあいにだされる言葉。キャラクターに感情移入することで物語を楽しんだり、あるいは戦闘の時に愛用して楽しんだり、という楽しみが成立しているのだ、というようなことが言われる。
が、しかし感情移入がされていないければRPGやアドベンチャーは楽しくないのか、というと、それはまた偏狭な理屈と言うべきで、『ロマンシング・サガ2』のような必ずしも感情移入を前提としていないものでも成功しているRPGは存在している。
関連 †
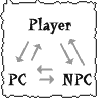
ゲームにおいて「観客」というを語る場合、古典的な映画/演劇などにおける「観客」とは、数多く異なる点があるということに注意がなされる必要がある。通常は「観客」概念にあたるものは用いられずに「プレイヤー」という概念によって語られる。
以下、いくつかゲームにおける「観客」概念に焦点をあててゆきたい。
- A.評価する制度としての観客
- 「評価」という緊張感をもたらされることでゲームが成立する。
- 解釈者という意味ではなく、ゲームの勝者/敗者を評価する「制度」としての観客概念。
- ゲームを成立させるシステムの一部としての観客
- B.解釈者/受容者としての観客
- テクストを解釈する存在としての観客。読者、解釈者とほぼ同義。
- ゲームの表現に対しての観客
通常、「観客」「読者」といった概念が文芸批評などで用いられる場合、後者の意味のみで足りる場合が多いだろう。
しかし、「ゲーム」「遊び」を成立させるために不可欠な要素として重要になってくるのは前者の「評価する他者としての観客」である。これは一人遊びの場合は「内在する観客」概念によって代替されるものと捉えられる。物語などの「表現」を成立させるために重要になってくるのは後者の解釈者としての観客であるが、ゲームにおいては観客は作品そのものを成立させるあまりにも直接的な制度なのである。
モニターの外の身体としての観客 †
作品を成立させるイニシアティブ †
- A.魅了されるものとしての観客
- 映像美などを堪能する側の存在(⇔映像を作る側の存在としての創作者)(受動的な存在) ※「プレイヤー」というものの中では映像美を堪能する側としての体験と、映像を作る側としての体験は同時に存在している。
- B.作品を評論する存在としての観客
- 映像美や、作品の手法について、ケチをつけたり、論理的に議論する存在としての観客
加藤幹郎『映画館と観客の文化史』P17〜P20では、「映画館」と「パノラマ館」が対比的に語られている。以下、要約する。
「パノラマ館」とは、三六〇度の視界によって設計された空間である。だが、三六〇度の視界をもっていることがわかるためには、円形プラットフォームを実際に歩いて回る必要がある。プラットフォームを一周することではじめて、観客は異世界のただ中に投げ込まれていることを理解する。「パノラマ館の醍醐味は、そこを観客が回遊してみなければならない」ことにあるという。
「映画館」は、観客のこうした回遊を禁止する。映画館では観客は座席について正面のスクリーンを凝視することが期待されている。一九〇五年の最初期から現在に至るまでこの構造は変わらない。そのかわり、観客が動かずとも、「いながらにして世界のどこへでも出かけて、また元の世界にもどってくる視覚的回遊性」を与えられている。ここでは、観客は身体的「動性」と引きかえに、視覚的/想像的「動性」をあたえられることになる。
パノラマ館と映画館は、観客に対して別の態度を要請する場所として今日まで続いてきているわけだが、これに対して状況を一辺させるのが、「インタラクティヴ・ヴィデオ・ゲーム」ではないか、と加藤は言う。
「たとえばゲーム・センター内でのゲーム・プレイヤーの様子を見てみよう。彼は両眼を覆う備え付けの電子ヘルメット(ヘッドマウント・ディスプレイ)」をかぶり、立ったまま、その場でぐるり三六〇度回頭しながら視野(ヘルメット内のスクリーン)のなかにいるはずの対戦相手を索敵している。このゲームプレイヤーの身体運動は傍から見れば滑稽きわまりないが、明らかにこの「観客」は「鎖のために首を回すことさえかなわず、眼前のものしか見守ることのできない」古典的ハリウッド映画の観客とは異質の存在となりおおせており、回頭しながらも異世界に没入できる、パノラマ館同様の強い動機を与えられているのである。
関連ワード †
[見る人とやる人][内在する観客][緊張感][二重の身体][解釈][プレイヤー][遊びつつ遊ばれる]
他者を現前させる装置 †
鷲田清和は、中井久夫が阪神大震災において「みつめられる」という経験をしたことを引き合いにだしつつ、他者の顔によってみつめられる、ということを契機として「顔」が単なる光の反射の成す映像以上のものとの現象してくる自体があることを指摘している。
鷲田清和が「顔」をこのようなものとして語るのは、「顔」によって自己をまなざされることで、「顔」は他者を現前させるインターフェイスとしての役割を果たしているものだ、という視点にたっている。(と捉えることができる。)
鷲田の議論からこの話をするのは微妙かもしれないが、たとえば「にらめっこ」をAI相手のコンピュータ・ゲームで実装するのはとても難しい。「にらめっこ」の対象は、あくまでそれが人間だということを感得できなければ、かなり難しいものがある。
ゲームにおける顔はどのような扱いをうけているだろうか。顔のもたらす役割によって、見事に
ゲームの中での顔の扱いは様々であるが、顔の描写が特殊な一例として、美少女ゲーム―――とくに『サクラ大戦』などに見出すことができるだろう。
『サクラ大戦』においては、顔は通常、四段階で描かれる。
- (A)まず、マップ上のゲームトークンとしての顔(二頭身キャラ。フィールドマップ)。
- (B)表情をあらわす記号としての顔(画面左下。顔のパターンが何種類もある)
- (C)鑑賞対象(?)としてのディティールまで描かれた上半身。(人気漫画家の藤島康介によるイラスト)
- (D)重要なシーンなどで登場する、背景画つきの全身画(同じく藤島康介によるイラスト)
ここでは操作対象としてのトークン、識別記号としての顔、表情伝達装置としての顔、鑑賞対象としての顔といった役割がシステム的に区分けされ、必要に応じて適したレベルの「顔」が召還されることになる。
キャラ/キャラクター †
伊藤剛は、漫画を分析する概念装置として「キャラ」と「キャラクター」という区分を提唱している。かなり、おおざっぱに言ってしまうと、「キャラ」とはきわめてフィクショナルな世界の中でフィクションとして作られた類型的で記号的な人物描写である。対して「キャラクター」とは、近代的な自我をもった存在である。
前述の、『サクラ大戦』シリーズはこの分類でいうと、きわめて類型的な「キャラ」たちとの戯れを楽しむことに重点の置かれている作品である。だが、シナリオ上で重要な意味をもつシーン――多くの場合、人が死んだり、強い覚悟が語られたりするシーン――においては、よりディテールの細かく描かれた上半身絵や、全身画つきの顔が呼び出される。
このような形で顔の描写手段と、人間描写は強く関連づけられている。
参考 †
鷲田清和『顔の現象学』
伊藤剛『テヅカ・イズ・デッド』
ゲームオーバーになってしまうような可能性が存在しているかどうか、ということは例えばプレイヤーに緊張感を持続させるのに有効な手段ではある。がしかし、あまりにもずっと緊張感を強いるようだと、プレイヤーの中で張り詰められた糸が切れてしまうこともあり、緩急効果などの手法(例えば、基本的には死の危険性が存在しないゲームで、ときどき死の危険性を強烈に匂わすような手法)を用いた方がよい場合も多くある。
また、時間制限の先に「死」が待っていることによってはじめて、人間は「時間」を管理し、制限された時間を効果的に配分していくことを考えるようになるといわれている。
カイヨワの遊びの定義の中の一つ。「約束ごとに従う活動。この約束ごとは通常放棄を停止し、一時的に新しい法を確立する。そしてこの法だけが通用する」(『遊びと人間』)ただ、この概念が「虚構の活動」や「自由な活動」と時に相反し、矛盾するものであるということをどのようにとらえればよいのか?そこらへんは「言語ゲーム」「二重創作性」という概念を参照のこと。
カイヨワ,ルール,二重創作性,言語ゲーム
あたりまえのことを言うようだが議論が成立するためには、議論をしている対象物についての理解が必要である。そのためには、対象を言語化できるかどうか、ということが議論を発展的に行っていくことができるかどうかの分水嶺となる。トートロジカルなことを言うようだが、言語化できないものは言語での議論が難しい。
映画や漫画といったメディア領域では対象となる事物が文学などよりも引用の難しい形態であることが常に問題になってきた。記述が困難な表現メディアでは、記述の可能な領域――すなわち、物語の筋など――だけの議論は誰にでも行えるが、そうでない部分――アングルや、コマ割り、描線の太さ――などは議論が難しい。そのため記述可能なものは、それが記述可能であるということによって活発な議論が行われやすくなるが、記述不可能なものは、それが記述不可能である、という理由によって一部の専門的職能を持った者たちの間でのみの問題となっていく傾向を持つ。
自動化/日常化された意識の言語化 †
→cogni 美少女ゲームにおける場所の発見
「記述不可能なルール」の価値 †
ゲームにおいては、記述不可能なもの、がしばしば大きな価値を持つことになる。
こうした議論の一つは、たとえばステファン・スナイダーマンによるUnwritten Rule?の議論や、リンダ・ヒュージによる議論などある。スナイダーマンはテニスのプレイなどにおいて、「紳士的」であることなどが、テニスというゲームの成立を支える上で価値を持つことを指摘している。
ゲーム研究におけるプレゼンテーション †
ゲーム研究や、ゲームに関する講演会では、静止画/動画がふんだんに取り入られることが多い。研究者がいかに熱心に、分析概念をこしらえても通じなければ意味がないので、「通じる」ための方途として静止画/動画が用いられる。
そういった方法をとらずに、会場にいる万人に理解されるように努力して例示するとなると、対象として取り上げることの可能なゲームソフトは、『スーパーマリオブラザーズ』、『テトリス』、『シムシティ』など世界で2000万人以上のプレイヤーを抱えるようなものだけで全ての説明を行うことが求められることになるだろう。
→教養?
カイヨワの遊びの定義の中の一つ。「日常生活と対比した場合、二次的な現実、または明白に非現実であるという特殊な意義を持っていること」(『遊びと人間』)
1.カイヨワ
カイヨワ用語でいえば「アゴン」。遊びの四分類の中の一つ。取っ組みあい、運動競技、ボクシング、玉突き、フェンシング、サッカー、チェス、スポーツ競技全般(『遊びと人間』)。
運(アレア)とは違って、特訓したり、思考したりすることによって、ゲームの結果を変えることができる。
2.クロフォード
クロフォードは「個々の参加者が他者と関りを持たずに、自分の成績を上げようと努力するようなものが最も単純な競争であり、参加者同士の相互作用があるような競争こそが、すなわちゲームなのである」と言い、競争とゲームとは別である、と主張している。なかなかに独特な主張。
「競争」というのはそもそも「他者と何かを競う」ということだが、それを参加者同士の相互作用があんまりなくてもどうにか成立するタイプのものと、そうでないタイプのもの、という形で分類しているのはなるほどな、というところだが、相互作用の有無をゲームの本質的問題にしてしまっていいのかどうかは疑問。
ゲームの分類論?、ゲームの定義論、ゲームデザイン論
ゲームをやっていて、ついついやりこんで修行をしてしまうような感覚に陥るような性質のことを指して「禁欲的娯楽としてのゲーム」というような言い方をしてみた。ゲームが娯楽であるにも関わらず「修行」とか「道を極める」とかそういった禁欲的(そしてけっこう不毛)な遊ばれ方をしていることが逆説的であり面白い。
禁欲的、というか、ストイックに、雑念が消えるような瞬間といったほうがよいだろうか。
1.緊張感の増大 †
ゲームをやっている最中の緊張感。スリルなどと言っても悪くはないが全く同じものではない。一般に、常に死(ゲームオーバー)の危険性がある状態や、賭けられているものが巨大であるほどに緊張感は持続・増大する。
2.緊張と弛緩/緩急効果 †
シューティングゲームなどではごく基本的な手法。常に敵の攻撃がバンバンと繰り返されているだけでは単調だし、プレイヤーの集中力もどこかで糸が切れてしまうので、いっせいに攻撃が繰り出されてきたかと思って必死になっているとピタッと止み、止んだかと思うとまたいっせいに攻撃の的になる。このパターンの繰り返しで緊張と弛緩を繰り返すことによって、プレイヤーの緊張感を生かさず殺さず持続させていく。
特に油断していた時に突然何かをやられると非常にあせるので、単に攻撃をバンバン繰り返されるよりも緊張する。特にプレイヤーが弛緩して油断しきった後にいっせい攻撃されたりすると対応できなくなったりするので難易度アップの手法としても有効。シューティングゲーム以外にもたとえば『ぷよぷよ』の「とことんぷよぷよモード」でもこの手法が使われている。
3.緊張という概念のブレ †
ホイジンガ『ホモ・ルーデンス』に、「緊張」という言葉についての考察はなかなかに面白いところを衝いている記述がある
「この緊張の要素こそ遊びの中では特に重要な役割を演じている。緊張、それは不確実ということ、やってみないことにはわからない、ということである。」(36頁)
おそらく「緊張」ということは心理的なものと身体的なものとのイメージがかなり交じり合ってしまっている言葉である。心理的に「緊張する」と言ったとき、それは「この後どうなるかわからない」という不安だと結びつき混沌としたものがある。一方、身体的な「緊張」には「ガチガチに固まる」という硬直したもののイメージがある。
「緊張し、はりつめた線」
「緊張してドジをしている人」
「本番が近づいて緊張してくる」
「緊張感のある作品」
「緊張感を持って仕事している」
これらの「緊張」という言葉の使われ方はけっこう違う。
っていうか「(緊張して)アガル」というのと「集中している」「気をはりめぐらせている」というのはかなり別の意味だろう。
ゲームにおいては様々なものが繰り返される。音楽が繰り返され、戦闘が繰り返され………単に全く同じ行為を繰り返すという作業であればそれはただ苦痛を伴うものとして意識されてくることが多いが、そこでは単に同じ行為が繰り返されているわけではない。省略があったり、上達があったり、創意工夫があったり、偶然による多様性があったりと、微妙にパターンがズレ、繰り返しでありながら一回一回の行為がオリジナルなものでもある。
関連 †
作業化、多様性、省略?、生活表現、一回性、偶有性?
ゲームの物語における、内容/形式 の問題 †
ここで言う「形式」概念は、対義語として「内容」を想定したもの。
ゲームをやりながらプレイヤーが涙し、感動し、あるいは怒りを露わにするとき、そのプレイヤーはゲームの持つ「内容」に心動かされているのか、あるいは「形式」に心動かされているのか。
たとえば、『ドラゴンクエスト』をゲームとしてプレイしても、そのトランスクリプト(文字を書き起こしたもの)を、読んでも、プレイヤーが受け取る文字は同一のものである。純粋に「内容」のみに感涙しているのならば、トランスクリプトでもゲーム・プレイでもそれは同様の感動を与えるはずである。そこには形式の差などない。だが、実際には、多くのプレイヤーはトランスクリプトを与えられたときよりも、ゲーム・プレイという体験のほうを素晴らしいものだ、と軍配を上げるのではないだろうか。
このように考えると、こうしたその問いに対する無難な答えは、「我々は、ゲームの内容のみに感動しているのではない。内容と形式の両方に心動かされているのだ」ということになろう。では、その「内容と形式の両方」とはどのような捉えればよいのか。これが、次の問題となる。
シナジー効果をどう捉えるか。 †
ゲームの感動的な内容を語るとき、それを物語内容の水準だけでなく、物語の形式の水準においても同時に語ることは難しい。それは、語り手が、形式と内容のシナジーを理解していないから……ということは必ずしもいえない。
ゲームの物語を記述することは――とりわけ、その物語が「一本道」のものであるのなら――そう難しくない。また、ゲームの形式を記述することもそう難しくはない。「俯瞰視点による移動式」「選択肢提示によるテキストノベル」「ときめきメモリアル式、恋愛シミュレーション」「立ち絵提示型のキャラクタインターフェイス」など、記述は可能だ。
ただ、難しいのは、両者が相互に、どのような効果を果たしているのか、ということである。「ゲームをゲームとして評価する」というとき、その評価の仕方は多くの場合、こうした形での内容/形式の両面についての考察を同時に果たすということが目指される。内容水準だけでの評価、形式水準のみでの批評は、ゲームというメディアを複合芸術として発展したものとして、捉えるとき、その批評はどこか物足りない印象がぬぐえない。
成功した批評。 †
たとえば、ギャルゲー関係だとサイト「アシュタサポテ」の林さんの議論が評価が高い
- →観測、指し示し、時間性
ギャルゲーの人物がかつての類型的で「ゲーム的」なそれとは異なり「内面的」な「深み」を獲得し始めたかに見えるとしても、その原因は物語(シナリオ)の水準には還元されない。ギャルゲーというジャンルの持つ独特の時間性こそが、そのような「深み」を感じさせる遠近法を可能にしたのだ。
プレイヤーがどちらかに決定することを嫌がる選択肢。「嫌がる決定」を強いる選択肢のこと。『タクティクスオウガ』における選択肢や、ギャルゲーにおける選択肢などが代表的。
これは単に、「ウンコ味のカレーと、カレー味のウンコ、どっちがいい?」みたいな選択肢AもBもどっちも回避したい選択(回避―回避コンフリクト)とかって話ではなくて、
(1)コンフリクト(接近―接近コンフリクト、回避―回避コンフリクトの両方を含む)
(2)行為の一回性
(3)他を選べないことへの機会の喪失
などの要素によって、「あー、選びたくない」感をかもしだしているものだ、と思う。ので、二週目のプレイとかで前に選ばなかったもう一つの選択肢を選ぶときには、コンフリクトも行為の一回性も機会の問題も、全部フッとんでしまいがちなので、あまり選択するのが嫌だなとは思わない。
ゲームの中から見つめ返してくる視線。これを主に四つに分類した。
1.直接対話型(人工知能、ゲームキャラクターとプレイヤーとの直接対話、シーマンなど)
2.内部対話型(ゲーム内部でゲームキャラクターと主人公との対話、サクラ対戦など)
3.中間型(1と2の中間。ガンパレードマーチの岩田など)
4.ネットワークゲーム型(ゲームを媒介にした対人間同士の対話)
→参考:http://www.critiqueofgames.net/talk/005_9.html
映画などでは映像を「見る人」と、映像を「作る人」が分離しているために、作品の受け手は映画を「見ること」に集中できる。だが、ゲームでは映像を「見る人」と映像を「作る人」(コントローラーを操作する人)に重なりがあるために、プレイヤーに対して単に映像を「見る人」としての地位を与えることができない。
例えば、ジョン=ウーの映画のような印象的な映像の見せ方をすれば確かにかっこいいことはかっこいい。だが、視点が一定しないためにプレイヤーがゲームを操作することが難しくなる、という障害がある。たとえば、ゲームの3D化が本格化する時期に大きな役割を果たした『Final Fantasy VII』(1997)では、巨大な原子炉(魔高炉)を描いたプリレンダリングの一枚絵の美しいシーンが登場するが、画面の奥にゆくにつれて、プレイヤーの操作するキャラクターのサイズが小さくなり、ゲームの操作を困難にしていた。
「見る人」と「やる人」を分離するための方法として、レースゲームなどでは「リプレイ」などという方式でそれを妥協的に解決するのが代表的な手段である。RPGなどではムービーシーンなどを導入したり、プレイヤーがコントローラーに触らなくとも勝手に動いていくようなシーンを導入することで両者の分離をはたしているが、「やる人」としての権限を奪われるタイミングが勝手に制御されている、ということに対して一部のユーザーからは不満も多い(→映画的)。他にテロップを入れたり、主観視点などを導入することによって雰囲気をかもし出すという手法(例:『メタルギアソリッド』(1997)のオープニングシーン)や、「操作している自分のプレイが充分かっこいい」という映像を作るように工夫する(『デビル・メイ・クライ』『ジェット・セット・ラジオ』)という方向性も存在する。
参考 †
- 沢月耀「「デビル・メイ・クライ」のスタイリッシュ概念における「見せる」「見る」の二重性」(「ゲームを語ろう」内)
関連 †
[映画的]、[プレイヤー]、[無意識]、観客
哲学者ヴィトゲンシュタインの提唱した概念。
特にヴィトゲンシュタイン後期哲学におけるキーとなる概念。
以下は適当な説明なので、あまり信頼しないように。
言語というものは我々にとって制約であると同時に自由を与える存在である。我々の使用する言語(例えば日本語)の意味の制約の中でしか我々はものを考えることができないが、そもそも言語が与えられていなければ我々はものを考えたり伝えたりすることができない。言語はわれわれにとって道具であるが、同時にわれわれの思考の前提である。
言語は確固とした意味がそこに定まっているわけではなく、言語習得の過程などでは幼児は言語の確たる意味を受け取り学習するという形で言語を習得するのではなく、言葉をとりあえず教えられてその言葉を使う過程――「例えばこういう意味でこの言葉を言ってみてはどうだろう」などと考え様々な文脈で言葉を使用し、その時々にその言葉があっているかあっていないかを大人に諭される。意味使用の中、逸脱のゲームを試行する中で言語の意味がなんとなく決まっていく。
言語は、そうしたゲームの中で意味を編成されてゆく。
日本では、特定のジャーゴンを使ってワラワラとコミュニケーションをしている専門家集団を、軽蔑的に「特定の言語ゲームの中で生きている連中」というような言い方をしたりする。
特に「制約がなければ自由はない」というような発想はゲームにおける「ルール」と「自由」の関係性を捉えるのに的確だろう。
二重創作性
鶴見俊輔が1960年代に提唱した概念。
鶴見は「芸術の発展」において、芸術概念を三つの層に区分けしてみせる。
- 純粋芸術(pure art):伝統的で確立された様式と権威を持つもの
- 大衆芸術(popular art):マスメディアによって複製され、産業資本によって商品化され、消費されるもの
- 限界芸術(marginal art):前二者よりもより広大な領域で、芸術と生活との境界線上に位置づけられるもの
水越伸[2002]は、ファミコンによって大衆化する以前の1980年代前半までのコンピュータ・ゲームのあり方にこうした「限界芸術」としての性質を見出している。
しかし、1980年代後半以後については、「テレビゲームでインタラクションを楽しんでいるのではなく、テレビゲームの商品価値を消費するというゲームを楽しいんでいる」とし、大衆娯楽化したものと断じる。さらに、こうした限界芸術から大衆娯楽へと変化する過程を「異化」⇔「日常化」、「体系(システム)」⇔「個立(スタンド・アローン)」という二本の軸によって水越は整理し、異化・個立の段階から、日常化・体系化へとメディアの遊具性が変容していく過程が、メディアの硬直化と普及の段階において観察できると論じる。
こうした水越の「メディア」と「遊具性」という変数の関連を観察していく視点はホイジンガ[1938]などの遊戯先行論/文化先行論といった議論とも関連している。
参考文献 †
- 鶴見俊輔「芸術の発展」『限界芸術』1976年、講談社学術文庫 9―82頁
- 水越伸 第一章「遊具のためのメディア」『新版 デジタル・メディア社会』岩波書店 52―89頁
- ヨハン・ホイジンガ『ホモ・ルーデンス』(原著)1938年、(邦訳)1973年 中公文庫
記事情報 †
1.安川一[1993]は、ゴフマン社会学を下敷きとしつつ、コンピュータ・ゲームにおける「プレイヤー圏」なる概念を唱えた。*25
2.これを受けて、増田泰子[2006]は、プレイヤー圏を介して適度なルール・ブレイキングが行われることによって、プレイヤーがゲームとの距離を適度に保ちうる構造が成立していることを指摘した*26
B.公共圏とゲームの成立 †
3.稲葉振一郎は、ハーバーマスの公共性概念を手がかりに、ゲームにおける「やりこみ」行為と、プレイヤー同士の公共圏とが相互に支え合う構造があることを指摘し、両者がゲームを「面白い」と感じさせるためのサブシステムとしての性質を持つのではないか、と推論を述べる。だが近年では、プレイヤーの「やりこみ」行為を、ゲームメーカー自体が予期し先回りしてゲーム自体に組み込んでしまう。そのことがゲームの公共圏の活発化を阻害し、「ゲームの面白さ」の成立が難しくなっているのではないか、という。
*27
4.はてなの「予測市場」にみられるように、自らの利益を最大化させるゲームに参加するという個々のプレイヤーの振るまいを利用しつつ、それを公共的な予測機能などに活かすといった試みがはじまっている。
5.こうした試みの先にある究極的な未来を描くのが、東浩紀、桜坂洋らによる「ギートステイト」プロジェクトである。
参考 †
斎藤純一『公共性』岩波書店 2000
ほか。
プレイヤーが快感を感じるための要件としてしばしば指摘されることの一つ。「困難であるというように感じたことを克服するのが何よりも快感である」ということ。早い話が、いきなりスロットマシーンで、スリーセブンを出してしまうような人にとっては、スロットマシーンは、何の困難克服行為でもないので、さほど楽しいとは思わない、ということである。つまり、困難克服が困難たりうるためには、プレイヤーが「困難である」ということを感じ取ることが前提条件となる(→主観的難易度)
また、ゲームをはじめて最初に「困難である」と感じたところから、ゲームを終える「克服する」というところまでプレイヤーがゲームをプレイしてくれるかどうか、というのがかなり重要な問題となる。例えば「困難」を感じた瞬間、その壁のあまりの高さにプレイヤーが意気消沈してしまったら、それでそのゲームは見返されることもなく終わってしまう。プレイヤーが高い壁を乗り越えようと思えるだけの気力が導きだせるかどうか、ということが一つのポイント。(→ゲームバランス?)
基本的な手法としては例えば、そもそもの壁の高さをそんなに高くしすぎないようにする、とか。壁を高くするとしても、断崖絶壁の壁にするのではなくて、緩やかなカーブを描いて、プレイヤーが少しずつ実力が上昇しているのを実感できるような工夫をつけてやるなどといったことが挙げられる。 (→レベルデザイン?)
ゲーム理論系の用語。
AとBとCの三つの選択肢があった場合、どの選択肢が一番優れているというわけではなく、ジャンケンのようにしてAはBに弱いがCに強く、BはAに強いがCに弱く、CはBに強いがAに弱い、というような関係のもとにおかれているような選択のシステム。バーチャファイターシリーズの「ガード」「打撃」「投げ」や、ファイアーエムブレムの「槍」「斧」「剣」の関係性などがよく知られている。状況に応じて使い分けるということをしていかないとコロッとやられてしまう。
「トレードオフ」とは、こうした混合戦略の推移の過程であると言える。
宮本茂がゲーム批評1998年21号のインタビューで答えている非常に印象的な一言
「その没頭できる一番大きな部分を占めてきたのが再挑戦度ということ。この再挑戦度を難易度によって高めているという商品が殆どなんです。そしてもう一つの柱が「先を見たい」という物量での再挑戦度。この二つを外して、本当におおらかにただやっていることが楽しいという再挑戦度の高さを持っているものが今までにあったかというと、僕らもずっとそれを目指してきてるんですけど、そんなに無かったですよね。」(P25)
前後の文脈を抜いてしまったので、きちんとしたニュアンスは全文を入手していただきたいが没頭できる要因の主要部分を、再挑戦度だと言い切ってしまった宮本さんのこの発言は非常に興味深い。また、再挑戦が成立するためには、「困難克服」の構図が成立する必要がある。
ゲームというのは似たような作業を何度も繰り返すことの多いものだが、それが労働としてネガティブに感じられてくる場合がある。その状況を指す言葉。RPGの単調なレベル上げや、適当に作られた学習ソフトの自動なんたら機能の類などなど。
ただし、どのようによく作られたインターフェイスであっても、一定時間を越えれば「飽きた」と思われてしまう可能性からのがれることはできないし、実際、そういった「飽き」という要素に対して、コレクション要素やパターンの多様性といった物量作戦や、あるいは、より高い難易度で操作してもらう、といった形の方法が大作ソフトの常套手段となっている。
RMTと労働からの疎外 †
マルクス的にいえば、労働からの疎外。アーレント的にいえば、Actionではなく、laborの状態だという話だろう。
近年では、RMTや、プロゲーマーなど、ゲームのプレイヤーとして収入を得るという事態が韓国を中心に勃興しつつある。楽しみと労働を両立させた形態(=Action?)である、と思われがちだが、ゲームのRMTをめぐる労働は新たなプロレタリアートのあり方を誕生させているようなところがある。
中国では、数万人の人間が、収入を得るためにまさしく作業として、オンラインゲームをプレイしていることがよく知られている。
本当は難しいことをやっていないのに見た目が派手なためにすごいプレイをしているようにプレイヤーに錯覚させたり、一見怒涛のような攻撃の嵐と見せつつあらかじめ避けられるように発射されている攻撃だったり、移動中にテロップをつけることで「映画的」という雰囲気だけをかもしだしたり……。「錯覚」などというと否定的なニュアンスにとられるかもしれないが、実際にはプレイヤーに雰囲気を感じてもらうためにとても有効な手法。
プレイヤーに「すごい」プレイを実際にしてもらわなくても、プレイヤーが「すごい」と思えるように錯覚できるような映像を用意できればいいのだ、という発想。
普通、プレイヤーはただの人なので、何かを錯覚させてやらなければ、プレイヤーに快感でいてもらうことは難しい。
産業発展発展の話として、よくシリコンバレーの産業集積うんぬん、という話がみられるが、日本のゲーム産業においてもシリコンバレーと同様ではないものの、東京を中心とした産業集積が見られる。産業集積の状態および、その効果等については、半澤誠司「家庭用ビデオゲーム産業の分業形態と地理的特性」(2005)にまとめられている。*28
「死」をどのような形のものとして配置するかは、ゲームの表現上の難問の一つである。
例えば、ゲームの戦闘で簡単に死んだり生き返ったりするのが、ゲームのシステム上の要請としては仕方がないものの、どうにも軽すぎる感じがあるので、戦闘でHPが「0」になる現象が昔は「死亡」と書かれていたのが「戦闘不能」と記述されるようになったり、一回死んでしまったらなかなか生き返れないようなシステムにしてみたり、といった形で非常に多くの工夫がなされてきた。
詳しくは、参考URLを参照してほしいが、
概念系としては次のようなものを使って議論してきた。
- 隠蔽論と、悪影響論
- 死の偶有性
- 死の表現技術
- 快楽としての死
- 一人称と死と二人称の死の往復
UPしてないところでも、何度も、方向性の違う形で話を書いているのでそのうちまとめます。
参考 †
堀井雄二が好んで使う手法を勝手に私が用語化した。
過去―現在―未来と三つの時代から一つの世界を見つめたり、都市―個人の生活というマクロ―ミクロから眺めたり、AさんBさんCさんという3人の視点から一つの世界を見つめたりさせるような体験をプレイヤーに課すことによってゲームの世界が薄っぺらなものから重層的で複雑な感慨を持ってみつめることが可能なものになる。
また、ゲームにはゲーム特有の時間が流れている、という指摘はたとえば、ジェレミー リフキン*29などによっても指摘されているが、では「ゲーム特有の時間」とは何か。
「ゲーム」の様態が多様であるのと同様、「ゲーム特有の時間」にも様々なものがある。
「時間」がいかにして構成されるか、という問題は「物語」にとって重要な問題となってきた。そもそも、「物語」という経験は、「時間」と不可分である。
アシュタサポテの「観測、指し示し、時間性」(林[2002])や、ゲームを語ろうの「ゲームはいかにして物語となるか」などを参照。
時間は、時間を投入されたものに対して、代替不可能性を用意する。(賭けられているもの参照)
たとえば、そういう話をあからさまにやっている話の一つは『ひぐらしのなく頃に』である。ネタバレになるが『ひぐらしのなく頃に 礼』収録の賽殺し編では、(以下、反転して読んでください)主人公の古手梨花は、自分が100年以上にわたって、何度も何度も繰り返し死に続け、ゲームオーバーになり続けた悲惨な世界から、文字通り血の滲む努力の後にようやく、その悲惨な世界を抜け出す。だが、悲惨な世界を抜け出したとき同時に、血の滲む努力を投入してきた世界そのものから追い出され、別の世界へと投げ込まれてしまう。このとき、古手梨花は血の滲む努力の果てに幸せを勝ち得た世界へと戻るか、あるいはまったく別の世界の中で微睡むのかという選択を迫られる。苦渋の果てに、古手梨花は、自身の努力の果てにつかみ取った世界に戻ることを決断する。このとき、最終的な選択を指示したものは、言うまでもなく時間を投入したことこそが、その選択自体の代替不可能性を高めている*30。
あるいは、「不思議のダンジョン」シリーズにおいて、長い時間をかけ、深くもぐった場合と、短い時間で浅くもぐった場合ではどちらに価値を感じるのか。ファイナルファンタジーで、プレイ時間2時間のセーブデータと、200時間のセーブデータではどちらが消されたらショックなのか。そういうような事例で考えてもらってもよい。
→リアルタイムを参照
当サイトでは、実感として流通している「自由度」という言葉を解体するために、「自由」と「自在」という概念を区別した(「自在」は「自由」概念の中の部分集合)。
「自由」という概念の要件は「自由度」と同様
・ゲームに実装され可能であること
それに対して
「自在」の要件は以下の四点を全て満たしていること。
・ゲームに実装され可能であること(自由であること)
・プレイヤーがその行為を望んでいること
・プレイヤーがその行為をなすために必要な情報を知っていること
・プレイヤーがその行為をなすために必要なことを身に付けていること
かいつまんでいえば、「自由」というのがただ単に「できること」なのに対して、「自在」は「やりたいこと かつ できること」である。
関連 †
自由感自由度不自由主体
最初は意識して見たり判断したりしていたことも、毎度のことになってくるとほとんど意識せずに無意識のうちに動作をするようになってくる。これを動作が自動化されるという(逆に自動化されていないものを見たり聞いたりするのを「異化が行われる」とか言う。確かロシアフォルマリズムの用語だったと思う)。通学や通勤の動作などというのはほとんどの場合自動化された動作であり、それは無意識に行われるゆえにどのように動くか、どこに行くかなどはほとんど考えなくともよい。
ゲームのプログラムがプレイヤーの介入によらずに自律的に考えて行動を起こすこと。リアリティを感じさせる要素の一つとして重要な要素である。AI(人工知能)などのプログラム。…とはいっても本当は、たいして自律的なんかじゃないけど。
関連 †
インタラクティビティ臨場感?人工生命?人工知能?
カイヨワの遊びの定義の中の一つ。「遊戯者が強制されないこと。もし強制されれば、遊びはたちまち魅力的な愉快な楽しみという性質を失ってしまう」(『遊びと人間』)。つまり遊びへ参加する際の自発性(内的動機)がなければ、それは遊びだとは言えない、ということを言っている。(自由度の議論とは別)
遊び手の主体性という前提 ―「自由意志」モデルなのでは?という批判― †
これに対して、西村清和は『遊びの現象学』の中で「遊びつつ遊ばれる」という現象を例にだして、遊びへの参加に常に遊び手の主体性があるなどというのは嘘っぱちだ、と反論している。
が、しかし、そのような西村の厳密な主体性の有無の議論を回避して、遊び手自身に「自分は遊びたくて遊んでいるのだ」という錯覚が成立していることを遊び成立の要件に据えてしまえば、まあ、いいんじゃなかろうか、という気もするのだが、どうだろう。
あまり自由でない「遊び」 †
たとえば、映画鑑賞などが自由でない「遊び」として挙げられる。→ 観客
関連 †
→カイヨワ
→遊びつつ遊ばれる
「自由」とは何か、ということを考え始めるとその測定不能性や多義性は認めざるをえない。
測定不能性については、選択肢の数の多さ、というモデルのみに限定して考えるのならば、選択肢の数の多さ=(測定可能な)自由度、といってしまうことも可能なように思われる。だが、もし選択肢が単にあるとしても、選択肢を選んだ結果として起こる事態が選択肢によってどの程度・どのように異なるのか、そしてそのことを選択肢の選び手が選択肢の結果を推定可能か、といった問題がある。「選択肢」という形態ではない、もっと連続値が無限にありうるような場合、選択肢の数は常に「無限」になるわけだが、そのような選択肢の数が「無限」であることが直接に「無限の自由度」であるということを言いうるだろうか?たとえば、4950通りのパターンの物語を持つゲームと、1073741824通り(2の30乗)の方向選択のできるダーツのゲームとではどちらが自由だろうか?
多義性についていえば、人文科学的な用語法としては有名なI・バーリンによる「積極的自由」「消極的自由」という分類にとどまらず、デカルト、カント、ミル、セン等の哲学・倫理学における「自由」の特殊な位置づけや、フリードマンの言うような経済学的な視点からの自由などもあり、また、それらの「自由」という用語法をめぐる分厚い批判も数多く存在する。それらを統一的な概念として語るのは非常に困難であるといわざるをえない。
そう考えると、「自由度」などという言葉はありえず、「自由」という感覚がわきあがる瞬間があるだけだと考えるほうがこの問題にアプローチしやすいのではないのだろうか。小林秀雄風に言えば「ゲームの自由さというものがあるのではない。自由なゲームというものがあるだけである」。
関連 †
自由と自在?自由度不自由主体
ゲームの評価を論じる上でのマジックワードの一つ。ゲームがどの程度、自由か、という意味で使われてきた。
「自由度」という言葉がゲームの文脈で明確に使われ始めた時期は明かでないが、おそらく80年代後半からとみてよいだろう。主にゲームの面白さをはかる指標の一つとして「ゲーム性」などと言った言葉と同様に使われている。多くの場合、「自由度が高い」ことと「面白いゲーム」はほぼイコールで捉えられる。あるいは「ゲーム性=自由度」といった言い換えもたまに見られる。
「ゲーム性」と同じく、意味が曖昧であるにも関わらず、評価のための重要な指標として用いられる。そのため、人によってはこの概念を用いることを避ける人も多い。
オブジェクトかサブジェクトか。 †
「自由度」という概念を実体的に捉えるのはかなり困難が伴う。
たとえば、一つの作品の中でも「自由」の感じられ方は、都度ごと、人ごとに異なってくる。そもそも自由という概念が成立すると考えられる場合には、ある選択肢が「存在する」こと自体よりも、その選択肢を選びとる人間が、自分が選び取る選択肢についての認識、理解をしていることのほうが重視される(→自由意志?、選択前提?)。
たとえば、選択肢の意味をまったく理解できないような、ABCという3つの選択肢は、それぞれに何の差があるか測定できないのならば、選び取るという行為自体はまったく無意味なものである。Aを選び取った場合、Bを選び取った場合、Cを選び取った場合に、それぞれどのようなメリットとデメリットがあるかを認識できなければ、選択肢A、選択肢B、選択肢Cの差は実質的に消え失せる。重要なのは、選択肢が存在することではなく、選択肢を選び取る主体が選択肢を理解できる、ということである。
つまり、ここでは「自由なゲーム」や「自由なアーキテクチャ」がある、というよりは、「自由な主体」がある、という発想が一つには可能である。そう考えたとき、オブジェクトとしての「自由なゲーム」を考えるのはナンセンスな発想だと捉えられることになる。
ただ、上記のような原理論を横において、自由度という概念の測定可能性を操作的定義によって論じることは不可能ではない。ということで、とりあえずの測定方法について下記に提案を行いたい。
量的自由度:任意のパラメータ数 †
一つには、いくつかの自然科学で採用されている方式として、自由度を任意に決定可能なパラメータの数と捉えるという方法である。この方法を仮に「量的自由度」と呼ぶことにする。たとえば、
10=X-Y+3
という式があった場合には、任意に代入可能な変数はXとYの二点であるので、量的自由度は「2」と捉える。同様に
10=X-Y*Z+3
という式であれば、X,Y,Zの3つが任意となっているので、量的自由度は「3」と捉えることができる。
割合的自由度:任意のパラメーター割合 †
また、数ではなく、パーセンテージによって捉える、ということも可能だろう。この自由度を「割合的自由度」と呼ぶ。先ほどと同じ式
10=X-Y+3
ならば、10,X,Y,3のうち任意の変数の割合を捉えて、これを割合的自由度「50%」ということもできる。同様に
10=X-Y*Z+3
ならば、自由度は、10,X,Y,Z,3なので、割合的自由度「60%」と捉えられる。
パラメータの重み付け †
「10=X-Y+3」という式に登場する、XとYという二つの任意の変数が合った場合に、XとYでは、プレイヤーにとっての変数としての重要性が違う、という場合が存在しうる。
たとえば、80年代中盤以降の和製RPGを考えて見ると、しばしば論点になるのは「シナリオが一本道」かどうか、ということであった。一方で、戦闘でのキャラクターカスタマイズの量的自由度や、キャラクターの名前を任意に変更できるかどうか、といったことはそれほど大きな問題として見られていない。
このとき、シナリオ(X)が任意であることは、キャラクターの名前(Y)が任意であることよりも、より重要な変数として見いだされている。そのため、XもYも同じ独立したパラメータではあるが、Xの存在はYよりも強力な重み付けがなされている。
この重み付けの問題を計算するのは、ゲーム単体では不可能である。ユーザーの心理状況を勘案する必要がある。つまり、ユーザーに対して「どの要素が自由にことが、あなたにとって重要ですか」といったユーザーアンケートをその都度していく、といったことで、パラメータ間の重み付けを確認していくしか方法はないだろう。
次に、パラメータ関係性をどう考えるか、ということも測定上の問題になってくる。例えば、アバターの顔や、服装をカスタマイズできるゲームは近年では珍しいモノではなくなった。Mii*31のカスタマイズ機能と、Sims2のアバターカスタマイズ機能とを比べた場合に、量的にはSims2のほうがカスタマイズ可能なパラメータ数は多い。そのため、Sims2のカスタマイズ機能のほうが量的な自由度は高い、と言いうる。(全体的自由度は、ともに100%だとする。)
しかし、Miiは、Wiiというプラットフォーム自体の機能であるため、『Wii Sports』や、『Wii Fit』など数多くのゲームと結びついているため、Wiiというハード上で展開されるゲーム全体の自由度上昇に貢献していることになる。Sims2のアバターもネット上にアバターをアップロードしたりすることはできるが、他のゲームに対するAPIとしては機能していない。
ここでは、ハブとなりうる自由度において両者は大きく異なっている。これを、被ハブ的自由度、と呼ぶことにしよう。
被ハブ的自由度は、結果的な量的記述*32も可能だろうが、割合としての自由度を質的に記述することの方が意味があるだろう。
ここで重要なのは、固定された(標準化された)インターフェイスがどこにむかって開かれているか、ということである。例示すると、次のようになる。
- 開発企業標準:開発企業にとってのインターフェイスの標準化
- 例:Miiを転用可能であること(企業にとってのオープン・モジュラー化)、シリーズ前作のセーブデータを次回作に引き継ぎ可能であることなど(企業にとってのクローズ・モジュラー化)
- ユーザー標準:ユーザーにとってのインターフェイスの標準化
- 例:Sims2のアバターのアップロード可能な性質など、ユーザーが自由に交換可能なモジュールとして機能するような標準
- ゲーム・システム標準:ゲーム・システムを介して利用可能なインターフェイスの標準化
- 例えば、ポケモンは同じゲームシステムを介してのみ交換可能。Simsなども同様。
などである。
さらに、ゲームの目的を任意に選べる、ということと、ゲームプレイの方法を任意に選べるということでも、意味はまったく変わってくる。*33
さらに、目的の自由度は、至近目的の自由度と、究極目的の自由度*34を分けられる。至近目的の自由度とは、例えば「レベル上げ」だとか「シナリオ進行」だとか「アイテム収集」だとか、ここ数時間、数十分でやりたいこと。究極目的は、たとえば「エンディングA」「エンディングB」といったマルチエンディングの問題として位置づける。
実際のカウントの問題 †
まとめると、次のようになる
- 定量的測定のための概念
| 10=X-Y+3 | 10=X-Y*Z+3 |
| 1.量的自由度:パラメータ数 | 2 | 3 |
| 2.割合的自由度:パラメータ割合 | 50% | 60% |
| 3.重み付け評価を含めた自由度 | (アンケート結果で変動) | (アンケート結果で変動) |
実際のカウントの難しさ1:プレイヤー認識範囲との齟齬(自由と自在) †
ただし、上記のような算出方法も、認識の問題と不可分である(特に割合による算出)。「自由である範囲」、あるいは「自由であるべき範囲」の全体性をどのように認識しているのか、ということによる。
例えば、あるゲームに慣れておらず、ほとんど一つのことしか制御できないようなプレイヤーの場合を考えてみよう。
10=X-Y+3
という式が成り立つ場合も、プレイヤーが、
10=X+3
としか認識していない場合は、プレイヤーにとって認識可能な量的自由度は「1」であり割合は「33%」となる。
あるいは、あるゲームジャンル(RPGでも、格闘でもよい)に慣れたプレイヤーにとっての自由度、ということを考えてみるとこの逆の現象が起こりうる。
10=X-Y*Z+3
という式が成り立つ、とゲーム制作者が考えていても、あるジャンルに慣れたプレイヤーからすれば、他のゲームではいじれた要素iや、要素ii、要素iiiが固定されていることが気になって仕方がない、という場合がありうる。その場合、「10=X-Y*Z+3」という式は
10=X-Y*Z+3-(2+3*3-14/7-12/3-2*4+3)
という認識に変換されて認識されることになる。量的自由度は「3」で変わりなくとも、割合は「20%」まで下がることになりうる。
(この問題については、自由度に対する「自在」概念も参照のこと)
実際のカウントの難しさ2:パラメータの独立性 †
もう一点ややこしいのは、パラメータの独立性をどう考えるか、ということである。
たとえば、要素Xという独立したパラメータがある、といった場合に、
X=(Xi+Xii+Xiii....+Xn)
といった複数のサブパラメータの集合として、パラメータが成立する場合もあれば
X=(Y,Z,W,V)
といった、形で他の独立したパラメータとの関係性によってパラメータXが決定される、という場合である。
具体的には、アバターの顔をカスタマイズする、といった場合を考えてみよう。顔というパラメータXは、眉、目、唇、鼻、輪郭、髪型、髪の色…といったXi,Xii,Xiii,Xiv…の集合的なパラメータと考えることができる。このとき、「顔のカスタマイズ」を独立したパラメータとして考えるべきなのか。あるいはもっと上位の「キャラクターの体全体」を一つの独立した単位として捉えるのか、「眉」や「目」が独立した単位として適当なのか、ということである。
そして、例えば「眉」を独立したパラメータXとして捉えた場合、眉(X)は、目の大きさ(パラメータY)や、おでこの広さ(パラメータZ)、体毛の色(パラメータW)といった要素との関係によって成立することになる。眉(X)自体を調整することは可能だが、目の大きさ(Y)や、おでこの広さ(Z)と完全に切り離して調整可能なパラメータではない。いくつかのパラメータは、別のパラメータとトレードオフの関係にある場合が往々にして存在する。I.バーリンが積極的自由と、消極的自由の衝突を問題にしたように、あるパラメータXを調整する自由が、パラメータYを調整する制約として機能する場合がありうる。
以上、何をもって「独立した変数」としてカウントするかは、その都度、操作的に定義される必要があるだろう。(例えば、独立して交換することが可能だとか、上位レベル/下位レベルを定義して、基軸となる概念レベルを任意に定義するとか。)
実際のカウントの難しさ3:環境変化、パラメータの再帰的変化 †
ここまでの記述は、あくまで行為を行う環境が固定した状況下におけるものである。通常、アーキテクチャ=法の自動実行*35だとみなされ、これはコンピュータを介したメディアにおいて見られる「自由」の特徴として語られることが多い。それゆえに、これまでのような「自由の測定可能性」の議論はある程度まで成立させ得た。
だが、Rule-Breakingなどゲームの外側に広がるプレイヤ圏の問題を扱う「重み付け」問題や、そもそもプレイヤー達の集まりであるオンラインゲームなどでは、問題構成が現実社会に近づいてゆく。行為する環境自体が常に変化することになる。そのため、そこでは選択前提そのものが常に変化し続け、変数の独立性や、選択肢と選択肢の間の関係がより曖昧になってゆく。
- (A)アーキテクチャの不確実性による環境変化
- 例えば、セキュリティ対策もRMT対策も不十分なゲームを一般的なゲーム・プレイヤーが遊ぶ場合を考えよう。
- あるオンラインゲームが正式版がオープンしたとする。しかし、RMTが認可されていなくとも、一ヶ月もすれば、RMTが実質的に行われ、チーターたちが数多く存在するゲームになってしまう。すると、一ヶ月前に行おうとしていたレベル上げの戦略は通じなくなり、方法X,Y,Zまでだった方法に、RMT(W)、チート(V)という方法が加わる。そのことによって、方法X,Y,Zはスポイルされてしまう。W,Vの重み付けが大きくなり、通常のレベル挙げ方法の重み付けは大きく低下する。
- (B)再帰的変化1:予期の予期の発生(一意の指標による予期評価が可能な場合)
- あるいは、大航海時代Onlineのようなゲームを考えてみてもよい。大航海時代Onlineでは、世界的な貿易状況変化によって、どの港間で、何を貿易するのが有利であるのか、ということが変わってくる。言ってみれば、株式投資のシステムと同様の状況が成立する。このような世界では、他人の予期を推測して、こちらが動くという予期の予期、あるいは予期の予期の予期…といったゲームが発生する*36ことになる。こうした状況下においては、あるものが突然に流行ったり、かと思うと、バブルがはじけるというようなことも起こりうる。こうした形で、複数の人間*37が相互に予期を行いながら行動し、それによって価値変動が起こりうる。個々人は、世界の全体性を認識することが原理的にできない(常に変動するから)。パラメータの重み付け(選択前提)は、一度それが観察しやすい状態にさらされると、さらにメタ観察→メタメタ観察→メタメタメタ観察→…、を呼び起こしてゆく。パラメータの重み付けは、高速に変動してゆくことになる。この世界では、選択前提は原理的に観察できず、「選択前提を観察したことにしておく」ことしかできない。
- (C)再帰的変化2:予期の予期の発生(予期評価が一意に不可能な場合)
- ニコニコ動画のようなCGMや、プレイヤー間のRule-Breakingの問題を考えてみてもよい。
- ニコニコ動画では、「何が流行っているか」という全体理解がなされ、それに従ってフォロワーが生まれたり、あるいはズラしを行っていくことで新しい潮流を生み出していく動画職人がいる。この「ズレ」によって、発生する多様なバリエーションの評価は、先ほどの問題と同じく、誰が何を作るかを予期し、裏読みし…という予期の予期、という構造をトレースしている。
- しかし、大航海時代のような予期の予期は、あくまで市場価格という一意の指標によって事後的に評価可能、調整可能なものである*38。対して、ニコニコ動画のようなコンテンツの「ズレ」現象は、バリエーションを評価するする指標自体もズレてゆく。「ホモネタ」という評価指標が、「シュールネタ」の評価指標とまざったり、ズレたり、あるいは新しい指標が生まれたりする。行為だけがズレてゆくのではなく、行為を評価するフレーム自体も変動するため、予期の予期のバリエーションはどこまでも拡散してゆく。このような環境においては、「環境の自由度」の測定可能性は、極端に低下してゆくのではないか、と考えられる。
調査実例 †
当サイトで、2004年頃に行った簡易調査がある。
FFや、DQでは、シリーズが重ねられるほどに「自由度が上がった」という言説が登場しているが、ある程度まで実態として測定しようという方法提案である。これを参考に90年代後半に言われるようになった「FFは自由度が低い」という議論をパラフレーズしてみよう。
量的自由度については、DQにせよ、FFにせよ、任意に操作可能なパラメーターの数自体は上昇しているため、自由度が圧倒的に下がった、と言いうることは困難である。しかし、大きく低下している指標も見られる
一点目は、全プレイ時間中における操作可能時間である。言わば、割合的自由度が認識として低下した可能性が高い。プレイヤーが操作する時間よりも、ムービーシーンや、キャラクターごとの会話を聞いている時間が増えたのはほぼ間違いない。
二点目は、シナリオ進行の順序制御が行いにくくなったことである。DQにせよ、FFにせよ、ファミコン時代は、シナリオ進行の順序制御がわりといい加減に行うことが可能だった。しかし、スーパーファミコン以降は、シナリオの順序制御がプレイヤーの調整可能な要素ではなくなっていく。この要素が減っていくことについての「一本道だ」という形での批難が増えていったのが90年代RPGをめぐる日本の言説状況だった。つまり、シナリオの順序制御という要素が、他の調整可能なパラメータよりもより重要な要素としてユーザーから重み付けをなされていた、と考えることができるだろう。
三点目についてはDQ7では、シナリオの順序制御(エピソードの順序制御)はある程度可能になっていた。しかし、エピソードごとの目的は全て「シナリオ進行」のためであり、単に方法の量的自由度が少し上昇したに過ぎない。ロマンシング・サガ・シリーズのように、Aというキャラクターを獲得するためにこのエピソードを進めようだとか、お金を調達するためにこのエピソードを、Bという問題を解決したいからこのエピソードを、といった形での至近目的の量的自由度はほとんど増加していない。このために、DQ7のシナリオの順序制御可能な要素は、あまりにも予定調和的な印象を与えていた可能性が強い。単に方法のバラエティが増えただけでは、プレイヤーの認識に「自由」だという感覚を与えることが困難である可能性が高い。
以上は、分析の方法論的な例示である。
上記の分析の妥当性はそこまで強力に主張するものではないが、方法論として「自由度」概念を、上記のような分類によって捉えていくことはある程度まで機能するのではないだろうか。もちろん、上記の分類はまったく完璧なものではなく、単なるたたき台に過ぎないが、こうした基準を細分化させていくことで、一定の議論が成立可能となるのではないだろうか。
言い換え、関連概念 †
→混合戦略をみよ
→errand boy syndrome、自由感をみよ
「自由」と「自在」区分から、自在概念との意味上の差として記述するのであれば、
「ゲームが実装している、可能な行為の幅広さの度合い。」
という意味に限定し使用することができる。
要は、そのゲームで何ができるか、ということの幅広さである。
→自在をみよ。
参考 †
自由と自在?、自由感、不自由、放りだされる?、errand boy syndrome(やらされている感)主体
難易度という概念は、「度」という言葉がついているため、あたかも測定可能であるかのように感じられるが、実はかなりプレイヤーの主観に左右されている側面が強い。レベルデザインというようなことを考えた場合、それは単に難易度調整のことを考えるべきではなく、主観的難易度の調整こそがゲームにおける難易度概念の肝だと言える。
これは宮本茂などもたびたび、この手のニュアンスの発言をしている。
→難易度
主人公の定義はいくつか考えられるが三人称の物語であれば「物語における中心人物」(主に活躍している人)、一人称の物語であれば「物語の語り手」ということが多いと思うが、一人称の物語でも「物語における中心人物」を主人公としてしている場合もあるので、一概にはなんとも言えない。
ゲームの場合は、さらに事情が微妙になってきて、プレイヤーキャラ(プレイヤーが操作するキャラクター)とかインターフェイスといった要素がさらに「主人公」概念の状況を混乱させている。プレイヤーキャラという概念が主人公概念と同一でないことは、茂内克彦,2002,「ビデオゲームにおけるメディア特性――物語性と主人公に着目して 」(静岡大学大学院情報学研究科2001年度修士論文)において指摘されている通りであり、同論文中では、『AC04』を「プレイヤーキャラ」と「一人称の物語の語り手」とのズレに着目することによって物語を効果的に展開させることに成功した例として紹介している。
また、『シーマン』や『シムシティ』などのような作品においては、プレイヤーキャラや一人称の語り手、物語の中心人物といった、要素も登場していないため、残っているのは、インターフェイスぐらいになるため、プレイヤーキャラ、インターフェイスといった要素を統合的に捉える枠組みとして松谷創一郎は「代理主体」という概念を提出している。
要素を統合的に捉えるという発想もアリだとは思うが、私の考えとしては、問題のない限り、通常は、主人公とかPCといった曖昧(=統合的に捉えられた枠組み?)な言葉によって呼んでおいて、議論が混乱するようなことがあれば、「物語の中心人物」「物語の語り手」「プレイヤーキャラクター」「インターフェイス」などといった要素をバラバラに分解して要素ごとに考えられるような発想で、いいんじゃないかなあ。
関連 †
プレイヤーキャラ?主人公の身体という制度記号としての身体の喪失?身体ののっとり
プレイヤーによって操作される身体として主人公の身体が存在するわけだが、ゲーム内部の世界に介入していくのに、プレイヤーの分身としての主人公を用意する、ということは一つの選択された制度でしかない。ゲームの中で意志をもって行動するプレイヤーの分身を作ることによらずとも、ゲームの内部の世界に介入していくことは可能である。例えば『Roomania#203』などはそのヒントとなる
コンピュータ・ゲームには、二重の主体が存在する。
一つは、プレイヤー(P)である。ほとんどの場合、人間そのものであり、交換不可能な存在である。人間の身体そのものである。殴られれば、もちろん、痛い。(場合によっては、コンピュータのプレイヤーが問題となる)
もう一つは、プレイヤーキャラクター(PC、アバター)である。多くの場合、コンピュータ・ゲームでの、これは交換可能なものとなる。それゆえ、セーブデータの受け渡しや、RMTなどの対象となりうる。これは、身体のエージェントとして機能し、殴られても、痛くない(なんとなく痛いような気分になることはある)。
主体、存在、表象 †
プレイヤーキャラクターと、プレイヤーという主体の二重化現象によって生じていることは様々に存在するが、ここでは赤川学*39によれば主体(サブジェクト)概念の整理や、鈴木健による整理*40を参照しておきたい。
まず、赤川によれば「主体」とは二つの意味で用いられている。
一つは、「主体的に働きかける」という意味である。「積極的」という概念とパラフレーズ可能である。
一つは、フーコー的な意味での「主体化」。パノプティコンや、意味の内面化といったキーワードに関連づけられて理解されている。この主体は、意味を外側から受け付ける受動的な存在のイメージが前提となっている。(もちろん、意味を受動的に受け付ける、ということのみならず、それが単なる受動性ではないことこそが重要なのだが)
また、鈴木は、Present(存在)とRe-Present(表象)の区分を持ち出して、オンラインゲームなどの仮想世界におけるアバター(PC)の性質を説明する。
通常、人間のプレイヤーの存在と、人間のプレイヤーによる意味表象という行為は、分離して存在・理解されている。例えば、この文章の書き手である私という存在と、私の発話や文字は別のものとして理解することが可能である。人間の存在(Present)が先にあり、その存在が表象行為(Re-Present)を行うという理解が可能である。
しかし、オンラインゲームにおけるアバター(PC)は、そうではない。まず、表象(Re-Present)が先にあり、そのことによってのみ存在(Present)が確認可能となる。ここには逆転が存在している。
この逆転現象が顕在化するようなオンライン・ゲームでの事例は、Ms.Norway事件*41のようなものが挙げられる。
あるとき、有名なオンラインゲームのプレイヤーである「Ms.Norway」について死亡した、という噂がオンラインゲームのプレイヤーコミュニティの中で出回った。しかし、実際には、その情報はブラフであり、Ms.Norwayは生きていた。だが、Ms.Norwayの生死を確認する唯一の方法は、彼女自身が発する言葉でしかない。(逆に、Ms.Norwayが仮に死んでいたとしても、誰かがMs.Norwayと成り代わって生きているフリをしつづければ、Ms.Norwayの死は、確認できない。)*42
(書きかけ。)
P-PC-NPCをみよ
主体とエージェント †
そのうち書く。
エンディングが「マルチエンディング」という形式で幾通りものエンディングが存在したり、あるいはエンディング以降もいわゆる「やりこみ」要素がたくさんつまっていたりしてエンディングを一度見た後も延々とプレイできるような作品/または、「エンディング」そのものの存在が単なる一つの通過点に過ぎず、その後何度も何度もその世界をループすることがゲームを楽しむ過程であったりするような作品(ex:『ガンパレードマーチ』『ベイグラントストーリー』)では、物語の「エンディング」という概念が一般的なものとしては成立しなくなる。
こうしたゲームでは物語に明確な「終わり」はなく、プレイヤーの側によって意図的に物語を「終わらせる」ことを決断したとき/あるいはやらなくなっていったときにはじめて物語の円環の環は閉じられることになる。
コンピュータ・ゲームの物語構造のもつこうした特異性は必然的にコンピュータ・ゲームの物語の作られ方に強い影響をおよぼすことになる。
通常の小説/映画/漫画などのメディアであれば、物語は一冊の小説、二時間という時間の中で閉じられて終わる。そこでは起承転結のはっきりとした構造が好まれる。もちろんコンピュータ・ゲームにおいても物語の起承転結というような構造性は多くの場合に好まれる。だが、こうしたメディア条件の上になりたつコンピュータ・ゲームでは「一回のゲームプレイ」の中に全ての要素をつめこむ、というような作品設計がなされない方向性へと、物語設計が駆動されてゆくことになる。
たとえば、「一回のゲームプレイ」を絶対性を崩し、二回目のゲームプレイ、三回目のゲームプレイといった中でゲームの醍醐味を露出する構造へとつきすすませる。そして、それを最も自覚的に展開したものの一つが、『ガンパレードマーチ』(アルファシステム)だろう。
『ガンパレードマーチ』では、一回目のゲームプレイのみが「正規のシナリオ」となるわけではない。二回目、三回目のプレイがあり、そしてあげくのはてには、コンピュータ・ゲームのパッケージの中でのゲームプレイという状態すら抜け出し、アルファシステムの掲示板の中で『ガンパレードマーチ』をめぐるさらに別のゲームが展開されてゆく(参考:中川大地ほか『アルファ・システム・サーガ』)。
ここでは、「正規のシナリオ」は存在しておらず「設定」が存在しているだけである。
また、こうした「物語」の存在が<オリジナル>ということではなく、プレイヤの側によってその幅が決められいるというような状況は、同 人誌などをもゲームの物語の一部として受け取るというような感性とも接続される。
NPC同士が、勝手にいざこざを起こしたりするといったような現象が、最近のゲームでは少なくなくなってきたが、だが、それは、単にそういう「出来事」が起こっている、といった印象があるのみで、それが、ゲームの中でのれっきとした物語性をおびた事件として蓄積されることはあまりない。あるNPCとあるNPCの喧嘩が数値的には表現されているにも関わらず、シナリオの上では、仲がよかったりすることがしばしばある。だが、それでは数の上での変化にしか思えない。
問題は、それがNPCたちの認識の上できちんとした物語をおびた事件として認知されることだろう。そのように人々によって認識され、語られない出来事は単なる数値上の「出来事」でしかない。 そういった単なる「出来事」が、人の口を借りて、発話される中で単なる数値の関係性が「物語」っぽくなる工夫という点で言うと、スポーツゲームの「実況」は極めて素晴らしい。また、『ピクミン』や『FFCC』で見られたような、PCが毎日「日記」をつけるシステムや、シムシティなどの「新聞」といったシステムもこういった工夫としてよく考えられている。
関連 †
プロット?、ナラティブ?、ストーリーテリング?、物語
「勝利」という概念の難しさは、「試合に勝って勝負に負けた」あるいは、「試合に負けて勝負に勝った」といった言い回しによく現れている。
フォーマル・ルールと、インフォーマル・ルール:基準の複数性 †
「試合に勝って勝負に負けた」という言葉が言い表しているのは、フォーマル・ルールと、インフォーマル・ルールの違いである。*43
「勝利」という概念について、トートロジカルな定義をするならば「勝利条件を達成すること」である。ただし、人がゲームを遊ぶとき、競われる優劣は必ずしもフォーマルな(公式の)ルールだけではないという点に注意したい。
例えば、将棋をするときに、わざと難しい手筋を選んでプレイしようとすることにこだわっているプレイヤーがいたとする。そのプレイヤーは、難しい手筋で勝つことこそが、彼自身にとって本当に望む勝利であり、単に勝つだけでは物足りないとしよう(将棋漫画『月下の棋士』の主人公など)。そのような人物にとっては、普段心がけている「難しい手筋」でプレイをすることが彼なりの「勝利」の必要条件の半分であり、公式ルールの中で勝つかどうかということは、勝利の必要条件の残り半分にすぎない。このプレイヤーが、何かしらの理由で、自分の望むような「難しい手筋」での勝利ではなく、「ただの勝利」をしてしまったとき、フォーマル・ルールでは確かに勝利したと言えるわけだが、彼自身のインフォーマル・ルールにおいては必ずしも勝利したと言えないという事態が生じることになる。
一回限りの振る舞いと、複数回における振る舞い †
また、しばしば混同されるが、ゲームにおける「勝利」と、ゲームに「強くなること」は全く別の事態である。
簡単に言えば、
- (a) ある一回のレースをするときに「1位」をとれることが100回中3回ぐらいあるが、平均的な順位は「18位」というダークホース・プレイヤー山田太郎と、
- (b) 100回のレースがあった場合に、常に「2位」とり続け、平均的な順位が「2位」という強豪プレイヤー鈴木次郎
という二人のプレイヤーを比べた場合に、強いのは後者のプレイヤー鈴木次郎だということになる。しかし、「勝つ」確率で言えば、鈴木次郎は山田太郎には全く及ばない。
「適応すること」 †
さらに、上記の二つの分類の複合的状況を考えて見ると、特殊な「勝利」の形態としての「適応」という事態を見いだすことができる。
表:勝利についての分類
| フォーマル・ルールでの勝利 | インフォーマル・ルールでの勝利 |
| 一回限りの試合 | 公式な「勝利」概念の成立 | 非公式基準における勝利。「試合に勝って、勝負に負けた」という事態の成立 |
| 複数回の試合 | 公式な「強さ」概念の成立 | 非公式基準において「強くなる」事態の成立。インフォーマルな「適応」を含める。 |
たとえば、『ひぐらしのなく頃に』シリーズにおける(以下、反転して読んでください)古手梨花の振る舞いなどがこれにあたると言ってよい。古手梨花は、雛見沢村のゲームの勝利条件(昭和58年の6月を終わらせること)はなしえないわけだが、雛見沢村において「強い」存在にはどんどんと近づいていくことになる。「勝利条件」に到達することが不可能だと気づいた彼女は、長年「諦め」を抱くことによって、精神的に適応し、状況に対して「強くなる」ことに成功している。だが、そこでは「強くなること」と、「勝利すること」が決定的に乖離している。別の言い方をすれば、囚人のジレンマゲームに負け続けることに対して、メンタルに「慣れる」ことによって、囚人のジレンマゲームから決して抜け出せない。その代わり、常に「辛くないゲーム」をし続けることが可能になっている。
「ゲーム・に対して・勝つ」ことと「ゲーム・において・勝つ」こと †
さらに、言うのであれば「ゲーム・に対して・勝つ」ことと「ゲーム・において・勝つ」ことを分けてもよい。ゲームの枠組みそのものから抜け出すことと、ゲームの枠組みの中で最適な振る舞いを行うこと、はまったく異なっている。
「ゲーム・に対して・勝つ」とは、フォーマル・ルールに対してインフォーマル・ルールが優位となってしまうような事態であり、「ゲーム・において・勝つ」こととは、フォーマル・ルールがインフォーマル・ルールよりも優位となっている事態のことである。
この優位性の転換はいかにして生じるのだろうか。
これを、フォーマル・ルールと、インフォーマル・ルールの協力(共犯)関係/非協力関係、として捉えてみることができる。ふたたび、『ひぐらしのなく頃に』の例に戻ると、雛見沢村におけるフォーマル・ルール(昭和58年6月攻略)の優位性は、インフォーマル・ルール(古手梨花と羽生の「諦め」による適応)と共犯関係にある。フォーマル・ルールへの挑戦があまりにも困難すぎるために、「フォーマル・ルール下で勝利できないことで満足する」というインフォーマル・ルールが、ここでは成立している。フォーマル・ルールが、フォーマル・ルールであり続けられているのは、フォーマル・ルールとは異なる水準の複数のルールが、フォーマル・ルールに貢献してしまうような形で作動し続けているからに過ぎない。ある特定のルールが強力に機能しえているのは、そのルールがうまく機能するために、他のルールがそこに屈服/協力するような状況があるからだ。
これは、決して例外的な状況ではない。通常、人がゲームを遊ぶとき、ゲームの外側の一次的現実の諸ルールは、脇においやられる。それは決して存在していないわけではない。「試合に勝って、勝負に負けた」といった言葉が言い表しているように、ゲームのフォーマル・ルール以外の、インフォーマル・ルールがゲームの中に入り込むという事態は頻繁に生じうる。しかし、ゲームを遊ぶときは原則的には、フォーマル・ルールが優位だという事態を「みんなで守っている」ということに過ぎない。
フォーマル・ルールに、インフォーマル・ルールを屈服させる、という方式は一人遊びのコンピュータ・ゲームではしばしば、簡単に崩壊を起こしやすい。「裏技」や「俺ルール」といった、Rule Breaking(増田[2006])をプレイヤーが、その気になればいつでも起こすことが可能である。フォーマル・ルールは、一人のプレイヤーによってボランタリーに「守られている」に過ぎない。パラダイム・シフトは、極めて高頻度で発生しうるのだ。
一方で、複数人遊びの場合は一人遊びよりも事態は面倒になる。ルールを守っているのは、私一人ではなく、「わたしと対戦相手」であったり、「ゲームに参加している30人」であったりする。そのような状況下においては、フォーマル・ルールの崩壊を起こすためには、ゲームに参加している全員の合意が必要となる。このとき、パラダイム・シフトを起こすための労力は、一人遊びの何十倍にもなる。*44
シチュアシオニスト(状況主義者) †
1950-1980年ぐらいまでの間にギ・ドゥボールの『スペクタクルの社会』(木下誠訳、平凡社、1993)などを理論的支柱としつつ成立していた運動。
『スペクタクルの社会』を読んでみると、たいへんに当時の時代を感じさせるマルクス的な話になっている。資本主義社会が成立させる「スペクタクル社会」の下では、人間はスペクタクルによって支配されるという。全ての商品――ここで言う商品とはパッケージ化された商品だけではなく「労働力」という商品も含む――がスペクタクルにおおいつくされ、スペクタクルによって人間は社会から疎外されていくのだという。
そうしたスペクタクルによって世界が覆われるいくのを打破する手段として、「状況」(シチュアシオン)を構築していくことが、シチュアシオニストたちの使命となっていた……ようである。
具体的に何をやるのか、というと、やっていることは1960年代に日本でも、フランスでもあったような左翼学生運動のようなことなのだが、それを支えている理論的な枠組みが面白い。
「「状況の構築」のためには、空間をブルジョワ的に組織することで人々の生活をブルジョワ的に組織するこうしたブルジョワジーの都市計画を批判することから始めなければならない。そして、既存の都市の奥深く入り込み、その正確な地図を作成するとともにその都市の弱点を探し出さねばならない。LIがそのために編み出した方法が、「心理地理学」と「漂流」もしくは「偏流」と呼ばれる活動である」(P216,木下誠による解説)
「心理地理学」とは、「意識的に整備されたものか否かを問わず、地理的環境が、諸個人の情動的な行動様式に対して直接働きかけてくる、その正確な法則と厳密な効果を研究すること」であり、偏流とは心理地理学を成立させるためのフィールドワーク的(かつ政治的)な方法論である。
また、「状況の構築」のために彼らは「転用」と呼ぶ方法を重視する。「転用」とは「物を本来あった場所から逸脱させること、本来の方向を逸らすこと」の意味だが、既存のものの意識的な引用、位置ずらしによってそれまで意識されていなかった側面を暴露することなどである。こうした「転用」に基づいた映画をドゥボールらは制作し、これらの活動は後のゴダール映画などにつながってゆく。
状況主義から、オルタナティブ・リアリティへ。 †
現在では、状況主義者を継承・乗り越える立場から、オルタナティブ・リアリティ・ゲームのようなものを見直し、評価するという議論がある。 →オルタナティブ・リアリティ・ゲーム?
日常世界と、ゲームの世界の境目を意図的に攪乱してみせることで、現在の都市/遊戯/消費/政治をめぐる様々な想像力にオルタナティブをもたらすもの、として、オルタナティブ・リアリティ・ゲームへの期待がもたれている。
大塚英志は、80年代に起こったビックリマンチョコなどの大ブームなどに見られる消費を「物語消費」とよんだ。子供たちが商品を単に機能的/享楽的に消費するのではなく、背景に広がる物語世界とセットで商品を消費していく状況を、当時の同時並行的に起こった多くの事件との関連を説得的に提示しつつトータルに呼び当ててみせた。
こうした大塚の見通しは、マーケティングの分野では福田敏彦などによって「物語マーケティング」としてマーケティングの理論ともなっている。(→物語消費?、物語マーケティング?)
また、DQ,FFをはじめとするゲームの売り方も、物語消費の一形態である、と整理されている。
こうした方向性は、言ってみれば社会全体のスペクタクル化とは言わずとも、ミクロなスペクタクル化を意図的に成し遂げようとする方向である。まさに商品のスペクタクル化のような様相を呈している。
つまり、現在では、ドゥボール的な目論見の先に、オルタナティブ・リアリティ・ゲームがある一方で、ドゥボール的な目論見の反対にもコンピュータ・ゲームが待ち構えているのである。*45
ストーリー・デザイン †
Henry Jenkinsの議論を、韓国のオンラインゲームの事例によって論じることを試みている、ハン・ヘウォンによれば、オンラインゲームにおけるマップデザインなどを通じた、空間の意味的デザインがゲームのストーリーテリングを考える上で重要な意味を持つ要素の一つだと、捉えている。
こうした、ゲーム内の地理的構成が、プレイヤーに与える心理的影響の関係性は、堀井雄二などがきわめて意図的に行っている。(→http://www.critiqueofgames.net/talk/005_3.html)
参考 †
ギ・ドゥボール『スペクタクルの社会』
プレイヤーの忠実な分身としての主人公が存在していない中では、プレイヤーは主人公の身体に憑り移り、主人公の身体を一時的にのっとるというような体験をしているといったほうがよい。(EX:『街』『かまいたちの夜』『FFX』など)
このような状況が成立しているとき、「主人公=プレイヤー」という構図は崩れている。(この構図が崩れることが悪いことなのではない)
関連 †
主人公の身体という制度プレイヤーキャラ?主人公
飛行機などを操作した時、はじめのうちは「飛行機を操作している」ということに喜びを感じる……というか「大きなものを支配している」だとか「空を支配している」というようなある種の支配感、「何かを手に入れた」という感覚が伴っていると思うが、次第にそういった感覚は薄れ、「巨大なものを動かしている感覚」はいつのまにやら「この飛行機を動かすことは自分の身体を動かすことの延長線上にある」という感覚になっていくことだろうと思う。そうなると「何か大きなものを支配している」という感覚はなくなり、ただ自分の進退を動かすような「歩く」だとか「走る」とかといった行為の一つになってくる。
そのような支配感喪失の過程は、ただ単にその乗り物を操作すること(あるいはゲーム上のキャラクターを操作すること)への「飽き」でもあるが、同時にそれは「なれる」という過程でもある。「なれる」ということの後には、ただ単に乗り物(身体)を操作することを楽しませるというだけでは不十分であるが、逆にそれは、その乗り物(身体)を使って何をできるのか、どのような外への働きかけができるのか、ということを楽しませてゆくための準備段階が終了した過程である、と捉えることもできる。
つまり、支配感の喪失と、インターフェイスの身体化は引き替えにおとずれるのである。
関連 †
ゲームにおける人工知能などの存在は、プログラムされたものに過ぎず、そしてまたゲーム機を起動させることによってはじめて動力を与えられるような存在に過ぎない。それゆえに、プレイヤーはゲームの中のプログラムに現実世界における人間の「人格」に値するようなものを認めることができにくい。
ゲーム内のプログラムに「人格」を認めてしまうような状態には当然数多くの批判があるだろうが、ごまかしではあるが、ゲーム内のプログラムに人格があることを錯覚させられるような作品も少なからず存在する。
関連 †
人工生命?人工知能?
一般的なRPGなどでは、プレイヤーキャラクター達のパラメーターは直線的に成長していくことがほとんどだが、『ダービースタリオン』『俺の屍を越えてゆけ』『ヴィーナス&ブレイブス』などでは、パラメータが衰退していく、というシステムを設けることによって、「成長のピーク」という概念を導入し、刹那的な瞬間の栄光のようなものを表現することに成功している。
だが、「衰退」という方法を安易に導入することは、諸刃の刃でもある。
「衰退」という要素をとりこむことでゲームバランス調整が困難になり、それまで積み上げられてきたRPGのバランス調整のような発想が根底から覆されてしまうということになる。特に、直線的にどんどんと強くなっていく「敵の強さ」のバランス調整を、ゲーム自体の進捗とは無関係なところで行わなければならない。特にそこで物語性の強烈に打ち出そうとしてしまうような『サガ・フロンティア2』のような作品を作るとなると、ゲームバランス調整では完全に失敗してしまうという苦い経験を味わうこととなる。
ゲームとして取り扱い可能な形式 †
ゲーム内において愛情、友情、忠誠心など、あるいは人気、魅力、正義心、等々そういったものを有機的な形(動的に変更可能な形)で表現しようとすると、魅力値がいくつなのか、とか「好き」のフラグがたっているか、とかどういう属性に属しているのか、とかそういう形での表現に落とし込まれざるをえない。
当然、それを複雑化していけばかなりいろいろなものができるのだが、複雑化をしていくというよりも、あらかじめ用意されたテキストや条件制限などを使っていかに単調さをごまかし、隠蔽していくか、というやりかたの方が一般的である。
数、でしかないということ †
ゲームがいくら感動的であっても、所詮、数値化可能なもの/反復可能なものだろう、ということに気づくと多くのプレイヤーは醒めてゆく。
代表的なのが、恋愛シミュレーションゲームでの「フラグ」だろう。
恋愛シミュレーションゲームで、特定の異性が、主人公を好いてくれるかどうかというのは、フラグが立つかどうか、ということにかかっている。そもそも主人公を好きになるというフラグが用意されていない、異性にいくら執着したとしてもフラグが存在しない異性は好きになることはない。また、どんなに特定のキャラにアタックをかけたとしても、フラグの立つポイントを抑えているかどうか、ということが最大の問題となる場合が多いので、そこのところのあまりにデジタルな感触に萎えてゆくプレイヤーが多い。
一方で、こうした感触が逆輸入し、現実の恋愛でも「あの子、オレにラブラブになるっていうフラグが立ちそうだYO!」といった会話をするゲームプレイヤーも少なくない。
「数」であることの恍惚 †
一方でゲームのコミュニケーションが「数」であることに対する恍惚を表明するというゲームプレイヤーもいる。もっとも自覚的に宣言しているのは、ゲームバランスとは何か、トレードオフとは何か、ということストイックに追求するような作品の制作を続けているアマチュアゲーム作家のporn氏だろう。
たとえば、porn氏の思想は次のように記述されている
カードでもいい。麻雀のようなテーブルゲームでもいい。まるで現実の自分の預金残高のようにその数値を愛した心理状態とサイコロの偶然とが創り出した一瞬に、一度でも奇蹟を感じたことがあるなら、そして再びそれに手を伸ばそうと思うのなら、あなたは我々の同志だ。
その瞬間は聖域だ。“感じた”という一点においては確実に事実だ。どんな現実も手出しはできない、完全に自由な精神領域だ。その尊い奇蹟を、今一度再現したい。生涯を費やして求めるだけの価値が、その黄金にはある。これは妄想ではない。思想である。その実現を求めるための議論と実験の反復なのである。
一方、porn氏が言及しているのはあくまで、日常世界とは隔離された場所としてのゲームでの数字のやりとりの話だが、RMTなどではフィクションであったはずのゲーム中の数値が、現実の価値とリンクしている。
ゲーム内での数値によって成立しているコミュニケーションは一見するとフィクションそのものだが、それをフィクションだと感じずに日常世界の価値と交換可能だ、と感じるプレイヤーがいれば、それはいくらでも、日常世界を浸食しうるのである。
『ガンパレードマーチ』のオープニングに登場するテロップに「それが世界の選択である」という台詞がある。
ゲームという人工世界は、パラレルワールドというわけではないが、ある意味「我々が今現在生きているこの世界」というものに対抗しうる「もう一つの世界」を作り出している、と言える。それは例えば「人工生命」というのが我々という「生命」が作り出したもう一つの「生命」であるように、人工世界もしかり。
それは憧れの対象ともなりえ、現実からの逃避の対象ともなりえるが、同時に「我々の世界」そのものを「絶対的な一つのこの世界」というもの対置され選択される「相対的に選び取られる世界」という地位におとしめ脅かすような潜在的可能性を持った存在として感得することも可能である。
『ガンパレードマーチ』ではそうした感覚が呼びおこされるような仕掛けが複数施されていた。
関連 †
人工生命?人工知能?
詩や文学が「言葉」という手段によって、世界を捉える仕方を提示するのと、同じように、ビデオゲームは、ゲームの「システム」という手段によって、世界を捉える仕方を提示することがある。
1.システマティックな世界理解 †
たとえば、倫理的に推奨されるような行動をしなければシステム的にやっていけないようにうまく仕組まれた『伝説のオウガバトル』や、きちんとした生活をしていないと人間として腐っていくようなシステムになっている『シムピープル』をやってみれば、おそらくプレイヤーは「あー、やっぱり、こういうときは、こういう風にこういうしなきゃなー」とか「ああいるいる、こういう奴」みたいな理解をシステムを通じて獲得するはずである。
こうした方向性をつきつめた議論として、ゲーミング・シミュレーション研究や、シリアス・ゲーム研究などがある。
2.日常世界の超越する想像力 †
また、同時に、街の中を自在にスライディングする『ジェットセットラジオ』や、街の中の物体を自在にまきこめる『塊魂』のような作品の場合、現実を理解するシステム的な表現に納得するのとは逆に、現実の街を見たときに、新たな視点で妄想してながめるというような、現実の限界を補完するような世界解釈を獲得することになる。
映画『マトリックス』シリーズでは、『バーチャファイター』『三国無双』などのゲーム経験を手だてとして、現実世界を超越した想像力を発揮することに成功している。
3.イデオロギー伝達装置 †
近年では、ゲームはイデオロギーの伝達装置としても機能している。
たとえば、イスラエル人を倒し傷ついたパレスチナ人を助けて回るFPS『UnderAsh?』や、アメリカにて共和党の税制政策を批判する『TaxInvader?』。そして、アメリカのナショナリズムを称揚する『フリーダム・ファイターズ』『スプリンターセル』『メダルオブオナー ライジングサン』などの数多くのFPSが存在しているのが現状である。
ただ、シリアス・ゲーム研究において理論的支柱となっている、James Paul Geeは、こうした多様なイデオロギーを伝えるゲームが、複数同時に存在すること自体を知ることによって、マルチカルチュラルな世界理解に促す可能性がある、と肯定的な捉え方をしている。
4.世界理解の脱構築 †
システムの中に深くコミットすることで、システムそのものの限界や欺瞞性を理解する、という形式のゲームも増えている。
Ian Bogost[2006]は『Tax Invader』のようなゲームを「フレームを強化し/すり込むゲームでしかない」とした上で、監視社会を取り扱った『Vigilance』というゲームを取り上げている。このゲームでは、プレイヤーはちょっとした「ビッグ・ブラザー」となることが可能である。しかし、ビッグ・ブラザーとして街を監視するうちに、ビッグ・ブラザーとなっている自身の存在に違和感を覚えていくことが可能になる。
また、澤野[1993]は、『女神転生2』における、「アクマを殺して平気なの?」「はい/いいえ」という選択をめぐって論を展開する。そして、「はい」あるいは「いいえ」を選ぶ内に、ゲームをプレイするプレイヤー自身の存在がいかに特殊なものであるか、ということを気づくような構造があることを指摘している。
参考文献 †
James Paul Gee"What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy" 2004
Ian Bogost “Frame and Metaphor in Political Games” In Worlds in Play�邦訳:「ポリティカル・ゲームのフレームとメタファー」(『Inter Communication No.59 Winter 2007』所収)
澤野雅樹 1993「百戦錬磨の『殺戮者』へ」(『人はなぜゲームするか』洋泉社所収)
ゲームを構成するルール・規則の中でも、制限・禁止を伴うもの。たとえば、手を使ってはいけない、とか。声に出してはいけないなどといったようなルール。⇔拡大ルール
我々の日常的な現実の身体のあり方をさらに制約された形で、ゲームの中の世界で行動させられること。
(1)ゲームの中の身体は、我々の生身の身体よりも、遥かに異常なことを成し遂げられる反面、我々が日常において可能な行動の10分の1も行動をとることができない、という意味において、ゲームの中の身体は常に制約されている
(2)シムアントのような、現実の人間の身体よりも、感覚的なレベルで非常に貧弱な身体しか与えられていないような場合。実際に人間の身体よりも、アリの身体のほうが貧弱であるとは言っても、そのような異常な身体を与えられること自体は特殊な体験として楽しむことはできる。
関連 †
拡張される身体
コンピュータ・ゲームというメディアが他メディアよりも優れた表現力を持つと思われる表現分野。「同じ作業を繰り返す毎日」という「生活」という行為がそのままプレイヤーによって体験されるのはゲームならではといえる。生活表現が可能になることによって、語ることの可能な物語の幅が増えることは言うまでもない。
こうした可能性は長く存在していたが、大きな成功を遂げたのは2006年の『おいでよ 動物の森』大ヒットである。
→詳しくは前意識を参照
「戦略性が高い作品」というのは具体的にどういった機構をそなえたものなのだろうか
とりあえず、当サイトでは
(1)選択肢の幅が多いこと
(2)どの選択肢をどの状態で選んでも簡単にことが済むわけではなく、状況によってどのような方法をとることが有効かを考えさせること、
の二点が満たされている作品、と言ってみよう。ただ、選択肢だけ多くても有効な選択肢が一つしかない、であるとか、有効な選択肢がどのようなものなのか、いくら考えても全くわからない(というか裏技的な発想だったりしかしない)というのは、「戦略性が高い」という表現があたるのかどうか疑問。
ゲーム理論における「混合戦略」「一般戦略」などといった概念も役にたつ。
聞いた話、「戦略」というように普通言う場合は、一般戦略であるらしい。
関連 †
トレードオフ
意識/無意識という概念の素朴な理解としては、「意識=現在、気づいているもの」「無意識=気づいていないもの」という二分類が一般的だが、認知科学や精神分析の分野では、その中間領域を注目する。フロイトは、この領域を指して「前意識」と呼んでいる。
下條信輔[1999]はこれをサールの「中心」と「周辺」という区分によって説明している。
たとえば、運転しながら哲学の問題を考えている状況を想像して下さい。考えに夢中になると、ほとんど意識しないうちに、あるいは運転しているという自覚なしに、いつの間にか無事に家まで帰り着いている、ということがよく起こります。これは無意識に運転したのではなく(そんな乱暴なことはできるわけがありません)運転に必要な近くや記憶は意識の周辺にずっとあった、と考えられます。ただ「気づき」がなかっただけなのです。意識の周辺にあるものは全て無意識的、と言いたくなる誘惑にかられるかもしれませんが、やはり違います。というのも周辺にあるものは、その気になれば意識の中心に持ってくることができるからです(運転の途中でふと「我にかえり」信号に注意を向ける、など)。(P190)
一方、無意識とは、注意を凝らしたり、あるいは条件によっては意識化できるといったようなものではない。例えば、いくら理屈で言われても、同じ長さが違う長さに見えてしまったり、同じ色が違う色に見えてしまうような錯視の類などは、こうした「無意識」の性質によって構成される性質であると考えられる。
前意識の意識化という苦痛 †
日常生活において半ば自動的にこなしてしまう行動(ex.通勤、通学)はゲームの中では省略されることが通例である。そのような行動は多くはプレイヤーに緊迫感をもたらすものではなく、ただの労働とみなされる場合が多い。プレイヤーにとってみれば、普段、前意識のレイヤーでルーチンワークとして処理しているために気にならない反復作業を、むりやりに意識化され「意識的に同じ作業の反復をしなければいけない」経験である。日常においては、通学や通勤といった行為の最中には、頭では別のことを考えていたり、本を読んでいたりするため、通勤や通学の時間に行われている反復作業は必ずしも苦痛を伴うものではないのだが、ゲームで通勤や通学を表現しようと思うと、「反復作業を意識的にやる」ことを強いられることになる。プレイヤーはいつも「どう動くか」という判断に頭を使っている時間が多く、ゲームをやりながら他のことに意識を向ける余裕が必然的に少なくなる。こうした理由から、ゲームの中で日常的なルーチンワークそのものは、表現される対象になるよりも省略されるケースのほうが多い。
ルーチンワークの悦楽 †
だが、一方でルーチンワークを表現しようとする例外的な事例も数多く存在する。代表的なタイトルとしては『Grand Theft Auto 3』や『Sims』といったゲームが挙げられる。
- GTA3:ルーチンワークを行為することの悦楽
- Gonzalo Frascaは、Grand Theft Auto 3における車の移動が、ある種の日常的な作業二塁するものであると位置づけながらも、車の運転をすること自体が楽しさを持ち得ているということを指摘している。ただしGTA3の運転はあまり楽しくないという人も存在しており(たとえば、私は全然たのしくなかった)、車の運転そのものが好きかどうかにも依存しているように思える。車の運転の「楽しさ」をFrascaがわざわざ指摘しているのは、A.ルーチンワークとしての性質と、B.娯楽としての性質との二面性を備えた行為としての車の運転、という行為が見いだされるということだろう。ルーチンワークは必ずしも、退屈でバラエティのないものだとは限らない。
- Sims、FF12:ルーチンワークを設計することの悦楽
- また、『Sims』も、ゲームキャラクター日常的な諸々の作業を表現したゲームであるが、それほど苦痛ではない。Simsでは、日常的な些末な作業が数多く表現されるが、日常的な些末なルーチンワークそのものはゲーム内のAIキャラクターが代行してくれる。その代わりに、プレイヤーは、ルーチンワークをAIキャラクターたちが行うためのアーキテクチャである家の構造や、目覚まし時計の時間などをセットする。こうした、前意識的行動を制御するアーキテクチャ・デザインにこそプレイヤーは注力することができる。
- また、これに類するゲーム・デザインとして成功した例として、FF12の戦闘システムも同様の発想が行われている。RPGのレベル上げのような単調作業や、非常に熟練したゲームをやっているような場合は、あまり強く意識せずにコントローラーを動かしていることも多い。特にRPGにおけるレベル上げは「ゲームの中における退屈なルーチンワーク」の代表例だろう。FF12では、レベル上げをプレイヤーに「行為させる」のではなく、「設計させる」ものとした。実際の戦闘は、AIたちが行い、プレイヤーはAIの行為をデザインするだけでよいのだ。(この発想の萌芽は、DQ4のAI戦闘がバラエティを持ち始めたようなところからたどることができるだろう。)
以上、数多くの行為の「反復」を前提とすることの多いゲームというメディアでは、日常的な前意識の領域に属するルーチンワークが表現しやすいといった特質すら見られる。
関連:→生活表現
参考:下條信輔,1999『<意識>とは何だろうか』講談社現代新書
動機付けの理論は、
- (1)経営心理学で言えば、経済的動機よりも親和動機(関係性の利益)を強調するホーソン実験や、マズローの階層性理論などが古典的なものとして挙げられる。
- (2)基礎心理学では、伝統的に動機付けを「外発的動機付け(extrinsic motivation)」と、「内発的動機付け(intrinsic motivation)」に分類する。
- 外発的動機付けは、ソーンダイクによるネコの問題箱、スキナーによるスキナー箱の実験など、行動主義の流れの中で強調された。(弁別学習の議論など)
- 一方、内発的動機付けに関する研究は、1960年代から増加する。デシによるアンダーマイニング効果(内発的動機の減退効果)の議論や、ドウェックによる再帰属訓練の実験などがある。
- 内発的動機付けの議論をささえる、ベースとして「随伴性の認知」「学習的無力感」「結果期待/効力期待」といった概念がある。以下は、ワイナーによる「帰属」の分類
表:学習の正否の帰属の2次元的分類(出典:市川伸一[2001])
安定性
\
原因の所在 | 安定 | 不安定 |
| 内的 | 能力 | 努力 |
| 外的 | 課題の困難度 | 運 |
特にゲームと動機付けに関する議論としては、チクセントミハイや、ラフ・コスターの議論などがある。
関連項目として、errand boy syndromeを見よ。
参考
- 市川伸一『学ぶ意欲の心理学』(2001、PHP新書)
- ミハイ・チクセントミハイ
- ラフコスター
チュートリアル水準、マーケティング水準 †
遠藤雅伸などはゲームの「導入」部分を上手くつくることこそが、ゲーム開発の肝だ、という話をいろいろなところで言っている。宮本茂の「難易度ということをきちんと考えろ!」という発言もだいたい似たようなものだと言えるだろう。
実際、「隠れた名作」になっていたり、危うく「隠れた名作」になりそうだったものは、導入がうまくいっていないものが多い。たとえば、『ひぐらしのなく頃に』『カオスシード』『セブン―モールモースの騎兵隊―』などが、導入がヘタな「名作」or「隠れた名作」だろう。
上記はチュートリアル水準での導入が上手くいっていない事例だが、もっとマクロなマーケティングの水準での導入がうまく言っていないと、これも厳しいことになりがちである。たとえば『コードエイジ エイジ コマンダーズ』は、それほどひどいゲームでもなく、一般のゲーム誌でのレビューはそれほど悪くないが、ネット上のamazonや、mk2などのレビューサイトでの評価は著しく低い。最大の原因は、難易度が少し高めのアクションRPGだったにもかかわらず、RPGとしてCMを打ちまくったのがかなりの敗因となった。スクウェアエニックス発売のヌルいRPGをプレイするユーザー層が期待して購入したにもかかわらず、ハードなアクションRPGだったため、需要と供給のわかりやすい不一致が起こっていた。これはスクウェアエニックス系統の作品ではよくある話で、松野泰己が指揮をとった『ベイグラントストーリー』なども、スクウェアのメインユーザー層であるライトユーザー層に購入された結果、同様の不評を買っていた。
アーケードゲーム開発と、「導入」概念 †
こうした「導入」概念は、とりわけチュートリアル水準での導入は、アーケードゲームの開発と不可分に発達してきた。PCや、家庭用ゲーム機において要求される「導入」の水準と、アーケードゲームにおいて求められる「導入」の水準では、アーケードゲームの場合のほうが明らかに高度なものを求められることになる。
理由は単純で、パッケージのゲームは家というくつろげる場所でプレイする上、ゲームが5000円なり8000円なりで購入させてしまうことができれば、プレイヤーはゲームを最後までやってくれる可能性が高い。だが、アーケードゲームの場合は、100円を投入して数分後にゲームオーバーになってしまうまでの一度のプレイの中で、そのゲームがどういうゲームでどう楽しいのか、を伝えることができなければお客は繰り返しゲームをプレイしてくれず、そのゲームが儲けを出すこともなくなってしまう。
宮本茂、遠藤雅伸ともに80年代初期にアーケードゲームでデビューした開発者である。アーケード出身の、この二人がともに、ゲームの「導入」の大切さを繰り返して説くのはおそらく偶然ではないだろう。
はじめサクサク (⇔問答無用) †
作品の導入部分に関する方法論としては「はじめはサクサク進む」というのが日本のゲームでは一般的である。ゲームをはじめてやりはじめた人のために、ゲームをやりはじめてから間もなくはサクサクと話が進むようにしたり、なんらかのわかりやすい目的を与えてやったり、丁寧なチュートリアルや解説などを付けてやったりする。そのようにしてある程度プレイヤーがゲームに慣れてきたら難易度を少し上げても、プレイヤーがそれに対応するだけの技術と気力をすでに備えているはずなので大丈夫だぞ、という方法論。
ただ、注意しなければならないのは、単にサクサクと話がすすむだけではプレイヤーの技術はつくかもしれないが、プレイヤーの気力が満ちてくることは期待できないので、サクサクと話がすすむのと並行してプレイヤーに作品の魅力を感じておいてもらうのもかなり重要。ばっちりとハートをキャッチ、するのには、錯覚させるなどの手法が有効。単にはじめサクサクとは言っても導入部のやり方というのはいろいろと難しい。
クロフォードによれば「クローズド」、カイヨワの定義では「隔離された活動」「規則のある活動」「虚構の活動」などと言った言葉で言い表されている。
「日常空間とは違った独立したルールの支配する時間・場所がゲーム(遊び)の特徴である」という、ほとんどの人が言っているゲームの定義論。また「クローズドなゲームは、ゲーム中に起こりうるすべての事象をルールがカバーしている」(クロフォードのゲームデザイン論)という点も重要
ゲームの定義論、カイヨワ、ゲームデザイン論
1.一人遊びにおいてゲームのスキルを上達させていく際、心の片隅で「いつか誰かに見せたい」と未来に見せびらかすことを期待している今はまだ会っていない観客。(カイヨワ)
2.一人遊びのゲームの内部においてもすでに評価者として存在している観客。オウガバトルにおけるモラルを強制する視線などの擬似的な観客。未来において期待されているのではなく、その状態ですでに存在しているもの。(井上)
3.遊ぶ自分を見つめる自分自身の視線。評価者として自分自身の視線。例えば最近のレースゲームなどでの「ゴースト」(前の自分のプレイを再現している車)などを思い浮かべるとわかりやすい。ある種のナルシズム?自己満足?(井上)
観客一人遊び?
ゲームをクリアーする難しさの度合い。
試しに分類してみると気力、思考力、反射神経、の3つにわかれる。
- 気力:昔の洋ゲーのようなものをなんなくクリアーしてしまうような気力、根性、体力そしてヒマが必要だといってもいい。
- 思考力:パズルなどの謎解きをこなしてしまうような頭脳労働等。
- 反射神経:アクションゲームやシューティングゲームで発揮される反射神経、動体視力、瞬時の判断能力(これは知恵か?)など。
難易度の測定というのは、実はけっこう難しい。
たとえば、単なるタイミングをあわせてボタンを押すだけのゲームAとゲームBがあったとしよう。双方とも、タイミングを合わせる際に要求される正確さは同程度のものである。
ゲームAは成功するとご褒美として二次元の萌え絵美少女が一枚ずつ服を脱いでいくゲームで、ゲームのやり方に関する丁寧なチュートリアルもついていてプレイヤーはチュートリアルで簡単な練習ステージをクリアしてみることもできるようになっている。しかも、タイミング的に惜しければ「惜しい!」ということを萌えキャラが教えてくれる。
ゲームBは、何のご褒美も、画像も設定されておらず、説明も「タイミングをあわせてボタンをおせ」の一言しか書いていないゲームだとしよう。
この場合、数値化可能なレベルでの難易度はゲームAもゲームBも同程度ということになるが、実際には、ゲームBのほうが若干難しく感じられるのではないだろうか。ゲームAの場合、クリアーしてやろうというインセンティブが働くようになっている上、チュートリアルで練習できるので「どの程度でクリアーできるのか」という感覚をプレイヤーがつかんでいるので一度や二度失敗してもゴールまでの困難がだいたい見えており一回一回の失敗がそれほど苦痛ではない。それに対して、ゲームBでは、何のインセンティブも働かず、失敗したときにそれが「どの程度の失敗なのか」の感覚をつかみようすらないときにプレイヤーが感じる負担はけっこう重い。
こういった要因を考えるとプレイヤーにとっての「主観的な難易度」というのは、どのようにゲームがデザインされているのか、によって大きく変わってくることことがわかる。
また、このほかに、ゲームの難易度の測定の困難さを支えている要因としては、プレイヤーがそもそもあるジャンルに対してどの程度興味をもって接しているか、といったことや、プレイヤーの平均的なゲームの上手さがどの程度のものか、といった要因によって大きく変わりうる。
→主観的難易度、レベルデザイン
ゲームバランス †
→ゲームバランス?
プレイヤープレイスタイル禁欲的娯楽
ゲームというものが体験される際、それは単にクリエイターの作ったものを見たり読んだりするだけの形でゲームを体験するのではなく、例えばシムシティであれば、ウィルライトというクリエイターが作ったプログラムを下敷きにして、プレイヤーが街を作っていくことでゲームが体験される。それには「ウィルライト」というクリエイターが関係していると同時に「プレイヤー」という存在も同時にクリエイターとして存在しているのでなければゲームという体験はなりたたない。そこに二重の創作が存在している、と見ることができる。
この発想は遊び全般の分析にかなり応用の幅が広い。ドイツの哲学者ガダマーが「ゲーム」を援用して、解釈行為とは何か、ということを言おうとしたのもだいたいこういうような話だった(はず)
参考 †
井上明人「宮本茂をめぐって コンピュータ・ゲームにおける作者の成立 」ユリイカ2006年6月号
ゲームにはゲームプログラムを開発した製作者――今回の例でいえば宮本茂および任天堂スタッフたち――、とゲームのプログラムを実際に実行してそれを遊ぶプレイヤーたちという二重の存在である。例えば『スーパーマリオブラザーズ』であれば、宮本茂という製作者が主導して作ったゲームプログラムを下敷きにして、ゲームのプレイヤーがマリオを操作し、攻略していくことではじめてゲームが成立する。それには「宮本茂」という製作者が関係していると同時に「プレイヤー」という存在も同時に存在しているのでなければゲームという経験はなりたたない。プレイヤーと、ゲーム製作者という二つがあってはじめて、コンピュータ・ゲームは成立する。
作者の二重性の問題は、ただ単に存在しているというだけではない。たとえば、作者の側がプレイヤーに特定の行動を強力に促すようなゲームを作ったとしよう。すると、それは、あらかじめ決められた選択肢をなぞっていくだけのようなものとして「覚えゲー」「一本道でつまらない」という反感を買ったり、「ゲームというよりも映画みたいだった」ということで別のメディア作品としての評価へ転じたりすることになる。
逆に、作者がプレイヤーに対して極端に弱く出て、その世界の中で何をするのかという目的も、方法も、なんでもプレイヤーの自由になるようなものを作ったとする。すると、今度は逆にプレイヤーが何をやってよいのかがわからないような、ゲームというよりも電子おもちゃだとか、『RPGツクール』のようなツールのような方向性になりかねない。
つまり、常に製作者とプレイヤーがどのようなバランスをとるのか、という問題が意識され、プレイヤーがゲームにどのように関わっていけるのかということを意識しなければならない。作者の二重性とはそのような厄介なものである。
関連 †
物語製作キッド?意図せざる製作/意図的な製作?ヤコブソン?自由度ゲームの定義?
ゲームプレイヤーの能力の分類は様々な水準で行うことができる。
1.能力の帰属による分類 †
オンラインゲームではしばしば、ゲームプレイヤー本人のゲームの強さを「プレイヤースキル」と呼び、ゲームキャラクター(アバター)の強さを「キャラクタースキル」と呼ぶ。
キャラクタースキルは、運によって変わったり、RMTによって取引可能なものだったり、プログラムにチートを施すことによって操作することが可能である。いわば、プレイヤーの身体と切り離して扱うことが可能である。
一方で、プレイヤースキルはそうした「ずるい」手段をとりにくく、「努力」によって手に入れるしかないものだとされる。
2.能力の性質による分類 †
- 知的:記憶力、論理的能力など
- 運動能力:反射神経、筋肉など
- 忍耐力:長時間プレイを続けることなど
難易度の項目も参照のこと。
特に90年代後半から、宮本茂が『ゼルダの伝説 時のオカリナ』の宣伝などをする際に多様しはじめ、「箱庭RPG」「箱庭感覚」などという言葉がいつの間にやらゲームの批評で言われるようになった。が、一体「箱庭」という言葉にどういう意味をあてているのか。
宮本茂の言う「箱庭」の意味については、
井上明人「宮本茂をめぐって コンピュータ・ゲームにおける作者の成立 」ユリイカ2006年6月号
に書きました。
メディア表現の変容を、社会の変容を原因として説明するような仕方のこと。たとえば、「90年代のサブカルチャーは、社会に蔓延する世紀末の雰囲気を受けて、終末をテーマとしたものが激増した」といったような見方は、「社会の雰囲気=世紀末的」というのが説明変数であり、「サブカルチャー作品のテーマ=終末」が被説明変数となる。
逆に、文化やメディア表現の変容によって、社会の変化がもたらされるとするようなタイプの議論は、言ってみれば観念論(?)。作品/社会の両面の双方向的な因果性を志向するのは言ってみれば、弁証法(?)だろうか。
また、宮台真司はこれらのいずれとも異なる立ち位置として、『サブカルチャー神話解体』(1993)の中での分析を「システム論?的」分析として位置づけている。
たとえば、漫画評論の分野で、反映論的な議論をしているものの一つに、夏目房之介『マンガと「戦争」』がある。夏目はこの中で、同時代の社会が「戦争」に対していかなるコードをもっていたか、によって、戦争の表現そのものが変容していった点について議論する。だが、同時に、夏目はこの本の後書きでは、本当は反映論ではなく、表現論をやりたかったのだが、戦争表現を通史的に書こうと思ったときに、反映論をとらざるをえなかった、ということを告白している。
ここで夏目が、反映論に対して距離を取ろうとしている理由の一つは、「反映論」を行ったときの自らの議論が「社会」をどのように規定するか、という問題によってどうとでも言えてしまうことへの忌避であろう。つまり、反映論は、メディア自体を語ることとは無関係に成立しえてしまう。社会を語ることによって作品が語れてしまう、ということは、作品の表現そのものの内実をそこまで詳細に読み込んでゆかなくともよい。作品の表現手法/内実を分析することに賭けている夏目からすればそうした分析から距離をとろうとするのは、ある意味あたりまえの態度と言えるだろう。
一方、こうした態度にたいして積極的に反映論を支持する立場がありうる。それは言うまでもなく、「社会」という変数こそが、作品にとって重要な役割を果たしている、という立場である。同じく漫画をめぐる言説としては、大塚英志『「ジャパニメーション」はなぜ敗れるか』ではは、そのような立場から手塚を分析してみせる。大塚は、戦後のイデオロギーと密接に関わった者として手塚を描く。
以上のように反映論を採用する/距離を取る、という二つの立場があるわけだが、どちらが正しいというわけではないだろう。
夏目は、社会について政治的に語ることからの「中立」を求めるが、それは「中立」であると同時に、表現が政治性を持つことを忘却させる装置としても機能する。表現は常に社会と関わる。「社会/政治について語らないこと」、が「社会/政治からの中立性」と読み替えられるのならば、反映論から距離を取る態度はそのナイーブさを批判されてもいいかもしれない。
社会反映論は、社会について語る。それゆえに、作品そのものに対してどこか不誠実なところがある。だが、作品そのものの内実のみを論じることも、同様に社会に対して不誠実なところがある。それは、分析がいいかげんだ、ということではない。分析の方法はいくつもあり、反映論にせよ、表現論にせよ、その一つの立場なのである。
参考 †
- 大塚英志・大澤信亮『「ジャパニメーション」はなぜ敗れるか』2005 角川書店
- 夏目房之介『マンガと「戦争」』講談社現代新書、1997
- 宮台真司、石原秀樹、大塚明子『増補 サブカルチャー神話解体』1993=2007 ちくま文庫
カイヨワの遊びの定義の中の一つ。「財産も富も、いかなる種類の新要素も作り出さないこと。遊戯者間での所有権移動をのぞいて、勝負開始時と同じ状態に帰着する」
この定義を採用するとなると、近年のRMTなどが行われるゲームは、ほとんど遊びじゃないという話になる。
美学においては、作品の価値に関しては、外面形態の知覚や感性に関わる美的価値と、精神的な内実にかかわる芸術的価値、あるいは、美的特質と芸術的特質について分けて考えられてきた。
19世紀にリアリズム文学が登場したときに、醜悪なものであっても現実を忠実に表現することに価値がある、とみなす動きが出てきたが、それ以前は、芸術と醜悪さは結びつき難い概念であったため、芸術的価値と美的価値の差異が激しく問われることがなかったが、現在ではこの両者の価値がセットになりうるかどうか、というのは論争的である。
参考:西村清和『現代アートの哲学』1995,P55-P56)
ゲーム自体の評価について †
→批評?
→レビューシステム
ゲームを成立させるものとしての「評価」制度 †
ルール、目的などと同様に、狭義の意味での「ゲーム」が成立するために必須の要素の一つであるといえる。「何をどうしたら成功といえるか」というような形で「評価」という問題を考えていくと、成功という評価=目的設定、という問題とつながって、「目的」という概念との明確な線引きが引けないということが面白いと同時に困った点。
評価関係のコミュニケーション †
対人関係の一つの要素として、自分が相手に評価を下し、相手が自分に評価を下す、という関係性がある。それは良好な関係であれば満足感を伴うが、うまくいかなければ疎外感をともなったりもする。
とりあえず、対人関係のそのような側面を表現しえているジャンルとしてギャルゲーというのは重要なジャンル。
ビデオゲームが狭義のゲームして成立するためには最低限のこととして目的とルールが必要だが、それらは言い換えれば「不自由」「制約」「条件」とも捉えられる。
リアルな人工世界を作ろうという観点からすればこれらはプレイヤーの行動の多様性を妨げ一つの方向性を強要する要素であると言え、ルールや目的の制約の仕方によってはプレイヤーは「やらされている」というネガティブな感じを抱くことにもなりうる。「プレイヤーの介入要素そのものがなくなってしまった」という不自由ではプレイヤーは退屈にならざるを得ない。
また、『伝説のオウガバトル』では、プレイヤーの行動が大衆の評価を受けることによって制約され、調整されるという面があったが、そのようなシステム上の演出は、プレイヤーにいろいろと注文をつけてくる「他者」のリアリティを喚起するものとしても機能するという、役割を担っていた。
1.出来事が順序だてて構成されること。物語論などではストーリー、ストーリーテリング、ナラティブ、プロットなどといった概念を区別して論じる。物語論の概念
2.イデオロギーや、社会に共有されているビジョンなどのことを指す。リオタール「大きな物語」など。→状況
特にRPGなどにおいて顕著なことだが、「物語」というものがどのような形で展開していくのか、ということがゲームの課す「目的」と不可分になり、そこで物語が多様に展開をゆるされず「目的」から束縛をされ、目的に沿った形の物語しか展開されてゆかないという問題がある。
例えば、「最強の敵」を倒すことが目的として課されている、冒険物語などは、どんなにゲームシナリオのライターが頭をひねったところで、大枠では「目的に向かって成長していく主人公」という形式のお話にならざるをえない。構造的にそうなっちゃってるのだから。
分類 †
ゲームにおける物語の類型分類は様々なものが提出されており、どのような観点から「物語」の分類を提出するかによって、その分類の仕方も当然多様になるが、「物語展開」の類型化をするならば以下のようなものが考えられる
- (1)一本道のシナリオ(一般的なDQ、FF等のRPG。用意されたシナリオが一本だけ存在し、それをたどっていく。)
- (2)マルチシナリオ(サウンドノベルなど。あらかじめ用意された複数のシナリオのうちの一本を選択する)
- (3)フリーシナリオ(ロマンシング・サガなど。複数用意された物語要素1、物語要素2…物語要素Nをプレイヤーがつないでいくことで、組み合わせの数が無限個に近くなる。開発者が細かく物語展開を管理できないため、ややちぐはぐな展開になりやすい)
- (4)シミュレーション(ガンパレードマーチや、シムピープルなど。用意された物語がほとんど存在せず、ゲーム中に存在する箱庭的な世界の中でほぼ無限に近いパターンの物語が展開されることになる。)
また、一本道のシナリオを、「映画や小説と変わらない」という人もいるがそんなことはない。確かに大枠の話が一通りしかない、という点では、同じようなものだといえるが、ゲームの中にあらかじめフォーマットとして焼き付けられた「物語イベント」のテキストやムービーのデータの他にも、戦闘や街の人との会話といった部分は選択的/偶然的に行われており、そういった形での「体験」というあり方が存在するという点では、映画や小説とは別モノである、という言い方をすることができる。
自動生成の可能性と問題 †
物語が成立するためには、因果関係について物語の聞き手/読み手が想起可能であることが必要条件である。
フリーシナリオと言われるシステムや、シミュレーションゲームは基本的には物語の成立している背景を想像するエネルギーを読み手に任せてしまうものだが、成功しやすいものと成功しにくいものがある。
たとえば、『シムピープル』と『エヴァンゲリオン2』は比較的似たシステムを持つが、前者と後者では後者のほうが物語を成立させるための設定が細かかったにもかかわらず、違和感/ちぐはぐ感の残るものとなっていた。
なぜか。
理由は簡単で、設定がいろいろとあるとなると、展開の自由度に限界が生じるからである。設定がいろいろあるということは、展開A→B→Cということはよくても、展開C→A→Dだと齟齬が生じてくるようなケースをしばしば引き起こす。AがBの前提条件であり、BがCの前提条件であるというような場合に、Cを無視してAが起こったり、Aを無視してCが起こったりすれば因果の順序は目に見えて破綻してしまう。
一方、設定がほとんど語られなければ、そういうややこしい自体は消える。そのぶん何をやっているのかさっぱりわからなくもなるが、破綻するためのバグフィックスをする必要もなくなり、ある程度違和感のないものが生成可能になる。『シムピープル』はそもそも、「家」というきわめて狭い空間から出ることがない。それゆえに、意味関係がすべて「家」という狭い空間の、狭い関連づけのみで処理可能なのである。
宮本茂のお言葉。
ゲームプレイヤーのテンションにとって重要なことの一つに「ゲームをすすめていった先にどのような報酬(モノ)が用意されているか」ということが挙げられるが、その用意されているモノのことを「物量」と呼んだものと思われる。
物量、が常にゲームのデータの中に用意されているというような形になるとゲームを作る側の負担はどんどん膨らんでいくが、ネットワークゲームや対戦ゲームのように、ゲーム世界の外部に目的対象が存在していれば、物量の上での負担は軽減する。
難易度の測定?目的
アバター。
プレイヤーの分身としてゲームの内部に存在している身体。基本的には主人公あるいはプレイヤーキャラクターのことをさすが、「分身」という比喩を用いることの妥当性については、厳密に言えば微妙な場合が多い。たとえば『アナザーマインド』『ポートピア殺人事件』『バテンカイトス』などのゲームでは、プレイヤーキャラクターと、分身の存在が別々に成立していたりする。
だが、「プレイヤーキャラクター」という概念は、ゲームというメディアのもっているかなり独自な概念なので、「主人公はきみの分身だ」という説明がゲームの初心者にとっては一番わかりやすい説明となっているという状況があり、80年代のファミコンの説明書には、だいたいそういう説明が書いてある。→参考:ドラゴンクエストを老人に説明してみてください
一方、近年では、ハンゲームなどをはじめてとして、アバタービジネスが盛んである。アバターそのものが自分の分身として機能するという状況がこんなに全盛になるとはかつては思ってもみなかった。
また、仮想キャラクターへの拷問についての調査研究なども。
オンライン公共科学アーカイブ“PLoS ONE”(英語)→日本語の記事 http://www.gpara.com/kaigainews/eanda/2007011103.php
関連 †
主人公の身体という制度、分身としての身体の喪失 、感情移入
ムービーシーンなどがそれにあたる。ムービーシーンというのはそれまでプレイヤーによって操られていた記号的な身体、あるいはあやつり人形であった身体が、とつぜんあやつり人形としての存在をやめて自律的に動きはじめ映像的にも別物になりかわることで分身として身体が喪失される体験であると言える。
→カットシーン
FPS、格闘ゲーム,落ち物系パズルゲームなどでは、プレイヤーのゲームをプレイする能力に対してゲームの結果が変化する。ヘタな人は負け、上手い人は勝つ。その意味では、こうしたゲームシステムは不平等なものである。
ただし、ゲームプレイの能力を鍛えれば、だれでもきちんとゲームに勝つことができる。その意味において、FPS,格闘ゲームなどは能力に対して平等(公正)な結果を返すことが期待されるシステムであるといえる。
ここでいう「能力」とは、そのゲームごとに求められる訓練可能な反射能力/知的能力である。(訓練可能でない能力は、平等とは結びつかない)
ただし、上記のようなFPSや格闘ゲームは、プレイヤーの投下時間に対する平等は保証しない。
こうした形の能力強化に興味を持たないプレイヤーもいる。そこで受け入れらたものの一つが、プレイヤーがゲームに費やした時間によって、結果を平等に保証するシステムである。具体的にはゲームにおけるプレイヤーキャラクターの「成長システム」と呼ばれるものだ。これは、特に日本ではRPGで発展し、現在では各ジャンルのシステムに幅広く取り入れられているが、
80年代後半に、『ドラゴンクエスト』が広く受容されたのは、当時大流行していた『スーパーマリオブラザーズ』がプレイヤーの能力を問うものであったのに大使、ドラゴンクエストはレベルあげを時間をかけていけば、いつかはかならずクリアできる。そのような形で「万人が(時間さえかければ)確実にプレイできる」ものとして和製RPGは当初受け入れられた。言い方を変えれば、
時間に対する平等、ということは、ゲームプレイの能力のないプレイヤーに対する救済措置として機能する。ただ、一方で、時間に対する平等な結果の保証は、能力に対する平等な結果の保証とはならない。
両者を混同させる戦略 †
両者を混合的取り入れることで、平等のあり方を意図的に混同させてゆく戦略をとるようなゲームはマジョリティ向けのゲームでは多い。
たとえば、『スターウォーズ バトルフロント』は能力が問われるFPSだったが、欧米で大ヒットした後の『スターウォーズ バトルフロント2』では、純粋なFPSだけでなく、そこに成長システムが加わる。このようなシステムの下では、プレイヤーは自分が上手いから強いのか、単に時間をかけてプレイしたから強いのか、が曖昧になる。しかし、理由はわからずとも、とりあえずプレイを重ねるにつれてどんどん勝てるようにはなっていくため、プレイヤーにゲームを持続させることが可能になる。
『スーパーマリオブラザーズ』の場合、基本的には能力が問われるゲームということになっているが、 †
三つ目の競争システム:現実世界における競争システムとのリンク †
→RMT
放り出される ゲームにおける「自由」の一つのありかた。この語のネガティブな印象としては、昔多かった「何の説明もなく、スタートボタンを押したら突然、ゲームの世界にホッポリ出されて何をやっていいのかがわからない」という問答無用な展開のことだが、最近はそういうものではなく、むしろ、作りこまれた世界にポツネンと放りだされたあたりに孤独感が漂っていたり、切ない感じが漂っていたりしてそこがよかったりする。
自由感自由度
どうやって一つのゲームを持続的にプレイしてもらうことは可能なのだろうか。
たとえば、「ゲームに没頭している」と言ったとき、どういう状態が思い浮かぶだろうか。
典型的なイメージの一つとしては、「あっ、クソ!負けた!もう一回!」といってステージクリアーに燃えているプレイヤーの姿などが考えられる。そのような「再挑戦」という行為に根ざした形が「没頭」の大きな要素であり、単にゲームをいじっているだけで面白いというのは、一昔前までは「やりこみ」というプレイ方法を除けばさほど一般的なものではなかった。
しかし近年のMMORPGに見られる、いわば「チャットブースター」としてあり方や、目的もなく世界をとびまわるだけで楽しいという『ジェットセットラジオ』のインターフェイスの楽しさ、延々と馬を生産して馬のクオリティの上下の波を味わいのんびりと馬をみつめられる『ダービースタリオン』、あるいは同じ物語であっても「テキストを味わうために」プレイするというノベル系エロゲーのプレイヤー、といった形で、「再挑戦」を軸とする「没頭」のあり方は必ずしも絶対的な方法論ではなくなってきた。
ゲームにはまっている度合い。「はまる」とだいたい似たような意味。「はまる」の中にも様々あり、例えばテトリスなどのパズルゲームがやめられないような状態になっている時は単にテトリスという遊びが楽しくてはまっているわけだが、RPGやアドベンチャーゲームがやめられなくなっているような場合には、単に遊びが楽しいという意味のみならず、「ゲーム内の世界の住人になってしまった」というような意味で没入している場合もある。もっとも「ゲーム内の世界の住人になる」というところまでゆきつかなくとも、プレイヤーが主人公に共感したり感情移入をしている形でゲームに没入していることは多々ある。
はまる?意識の距離?
漫画記号論 手塚治虫の主張する漫画論などに見られるような漫画論を指す言葉。
漫画表現は明らかな誇張や変な表現をしているのにもかかわらずスラッと読まれる(例えば目玉のとびでる表現とか、過剰にはっつけられるバンドエイドとか)。あるいは (^-^)/ みたいな程度の描きかたでもそれが「顔」として認知される。それは、漫画の絵がリアルな模写としてではなくて、一種の「記号」として見られているからだ、という議論。
手塚の初期の漫画などはまさしくその通りだと感じはするが、現在の漫画を眺めてみて、例えば『バガボンド』や『ジョジョの奇妙な冒険』とかを記号と言ってしまっていいのかどうかは微妙。記号的な部分も存在しているが、「記号である」というのは苦しい(パースの記号論なんかをもってくるとまた議論が違ってくるかもしれないが)。 どうしてこの話が重要なのかというと、ゲームのビジュアル表現はその多くが漫画・アニメの表現手法からひきつがれており、ゲームのビジュアルの表現は記号かどうか、というような議論がなされることがあるので。
リアリズムの特権化
カイヨワの遊びの定義の中の一つ。「ゲーム展開が決定されていたり、先に結果が分っていたりしてはならない。創意の必要があるのだから、ある種の自由がかならず遊戯者の側に残されていなくてはならない」
例えば、手塚治虫はアニメーションを作ることの楽しみというのを絵が動き、そこに命がふきこまれているように感じることが楽しい、と言ったがゲームにもそういう楽しみはあるように思う。例えば『シムシティ』で無人都市だった場所に人が入りはじめ開発されはじめて、風景が動き出した時に、そこに命がふきこまれたような感触を覚えるのではないだろうか。あるいは自信の無いプログラムが予想通りに動いた時、音を自在にかきならすことが出来たときなどなど。
他にも、独楽やヨーヨーや凧もそういった楽しみを持っているのではないかと思う。
ちなみに、「アニメ」の語源?である「アニマ」とは魂の意味。
ゲームがゲームとして成立するために必須の要素であると同時に、「目的」という制度から逃れられないために、ゲームは様々な制約を課されていると言ってもいい。RPGが常に成長物語としかならず「ラストボス」とか達成の末に存在する「何か」を必要とするな構造しかとれないのもこのためである。
ただし、ゲーム内に目的が存在するのか、ゲームの外に目的が存在するのか、それともプレイヤーが独自に目的を設定するのか、またはゲームの目的を多様な形にして多種多様なプレイをするのか、などといった対策もないことはない。
- ルール内目的:敵や報酬など。
- ルール外目的:物語や「算数の勉強」だとか。 もう少し具体的に言うと、例えばバラモスやハーゴン、あるいはエンディングムービー、ゲームセンターでの対戦相手といったものは、ゲームのルールにのっとった目的対象物だが、ドラクエのストーリーや、EMITでの「英語学習」だとかは、ゲームのルールそのものには関与しない要素。
ルール内目的とルール外目的の裂け目は、ゲームをめぐる評価/制作において常に問題となる。
たとえば、80年代中盤以降のDQ,FFを中心とした和製RPGでは、ゲームのシステムをめぐる評価と、ゲームの物語をめぐる評価の差異をどう処理するか、ということがしばしば問題にされた。「RPGは物語の善し悪しが大事!」といった言説は80年代後半〜90年代にかけて支配的になっていくが、こうした言説ではゲーム外目的を達成しているかどうか、ということが常に評価の対象とされてきたわけである。
また、学習ゲームでもこれは頻繁に問題となる。「数学の定式をプレイヤーが習得すること」(ルール外目的)と、「プレイヤーキャラクターがレベルアップすること」(ルール内目的)は別のことだが、この両者の折り合いをどうつけるか、あるいはそもそも一緒にしてしまっていいものなのか、ということがゲーム制作者の頭を悩ましてきた。
ゲーム世界内目的、ゲーム世界外目的 †
- ゲーム世界内目的:ゲームにそもそもプログラム済みであるNPCの敵キャラクター。プログラムされたもの。
- ゲーム世界外目的:ゲームにはプログラムされていないPCの敵キャラクター(対戦相手)。プログラムされていないもの。
両者とも基本的にはゲームルールに沿った形での目的対象として存在しており、共にゲームルール内部目的である。
目的がゲーム世界内で完結してしまうことは、ゲームのプレイ時間の限界を必然的に要請する。RPGのラスボスを倒してしまって以降、ゲーム世界内には「やりこみ」という特殊プレイを行う以外にはやることがなくなってしまう。(このため、90年代のファミ通には、壮絶な「やりこみプレイ」の数々が誌面をかざった)
ゲームの目的が、ゲームの世界外にいる対戦相手などであれば、「ゲームが終わる」ということはない。だが、ゲームの世界外に配置された生身の人間は、ゲームの難易度設計とは無関係に存在してしまう。そのため、アーケードゲームや、オンラインゲームでは「初心者」がどのようにして、すでに成熟したゲームプレイヤー・コミュニティへとコミットしていけるか、ということが問題となる。
関連 †
評価目的設定多様性開拓される目的?与えられる目的
プレイヤーが何を目的と据えるか、ということ。ゲームの中で支持された「ラスボスを倒す」などといった目的をそのまま目的とするプレイヤーが基本的だが、プレイヤー自身がただ目的を与えられるだけではなく、もっとアクティブに目的を設定する場合も数多く存在する。
いわゆる、「やりこみ」プレイや、ゲームセンターで対戦相手を探すなどといったことがすぐに思いつくが、そういった形での、様々な目的設定がなされるほかにも、もっと小さなところでプレイヤーはさまざまな形で「これをこうしたい」といった欲望を抱いているはずである。
#include(): Limit exceeded:
遊びつつ遊ばれる
#include(): Limit exceeded:
遊びの定義
#include(): Limit exceeded:
遊び研究
#include(): Limit exceeded:
遊び相手
#include(): Limit exceeded:
遊技先行説
#include(): Limit exceeded:
与えられる目的
#include(): Limit exceeded:
欲望